食と農
楽々ランチde試食会
応募者多数で抽選に ~プライベートブランド「わたしのこだわり」商品試食会を開催!
皆で調理

並んだ多種類の試食品
初めて試食した商品も
東都生協は、独自のプライベートブランド「わたしのこだわり」(*)商品を使った調理試食会を2回にわたって開催。
ブロック委員会不成立ブロックから参加の方々を中心に両日とも定員を超える申し込みがありました。
「わたしのこだわり」は、東都生協の組合員と産直産地・メーカーが一緒に作る商品ブランド。不要な添加物を排除し、国産原料を優先的に使用するなど、安全・安心とおいしさ、使い続けられることを追求しています。
(*)「わたしのこだわり」の詳しい説明はこちらをご覧ください
【2016年11月19日(土)】会場:セシオン杉並
土曜日開催ということもあり、申し込み多数で抽選となり、保育希望も多く、にぎやかな試食会となりました。
「初めて食べる商品があり、簡単にできておいしかったので、次回買ってみたい」という声が多く聞かれました。(24人参加)
<当日メニュー>(試食品)
東都ピーマン肉詰め
東都南国元気鶏フライドチキン
東都肉ワンタン
東都白身魚の便利カット
東都エビピラフ
東都焼きナポリタン
東都三陸産カットわかめ
東都ミックスナッツ
東都麩菓子
東都国産果実の実ゼリー
野菜サラダ 他
【2017年1月23日(月)】会場:西荻地域区民センター
第2弾! 開催も申し込み多数で抽選となりました。男性の参加者もあり、多くの世代の方が集う楽しい試食会となりました。
「簡単にできてボリュームもあった」「お気に入り商品を見つけられた」というお声を聞くことができました。また、東都ファームのにんじんドレッシングも大好評!(25人参加)
<当日メニュー>(試食品)
東都霧島黒豚ハンバーグ
東都鶏ごぼうしゅうまい
東都スイートコーンの中華スープ
東都金芽米焼おにぎり
東都エビピラフ
東都北海道産栗かぼちゃ
東都北海道産栗かぼちゃ
東都薫るよもぎ餅
東都惣菜屋さん 国産ひじきとゆば煮
いわしのおかか煮
東都国産若採り里ごぼうのおつけもの
東都信州りんごジュース
野菜サラダ 他
ふっくらおいしい煮豆の製造現場を見学しました
㈱南部フーズ交流訪問の報告
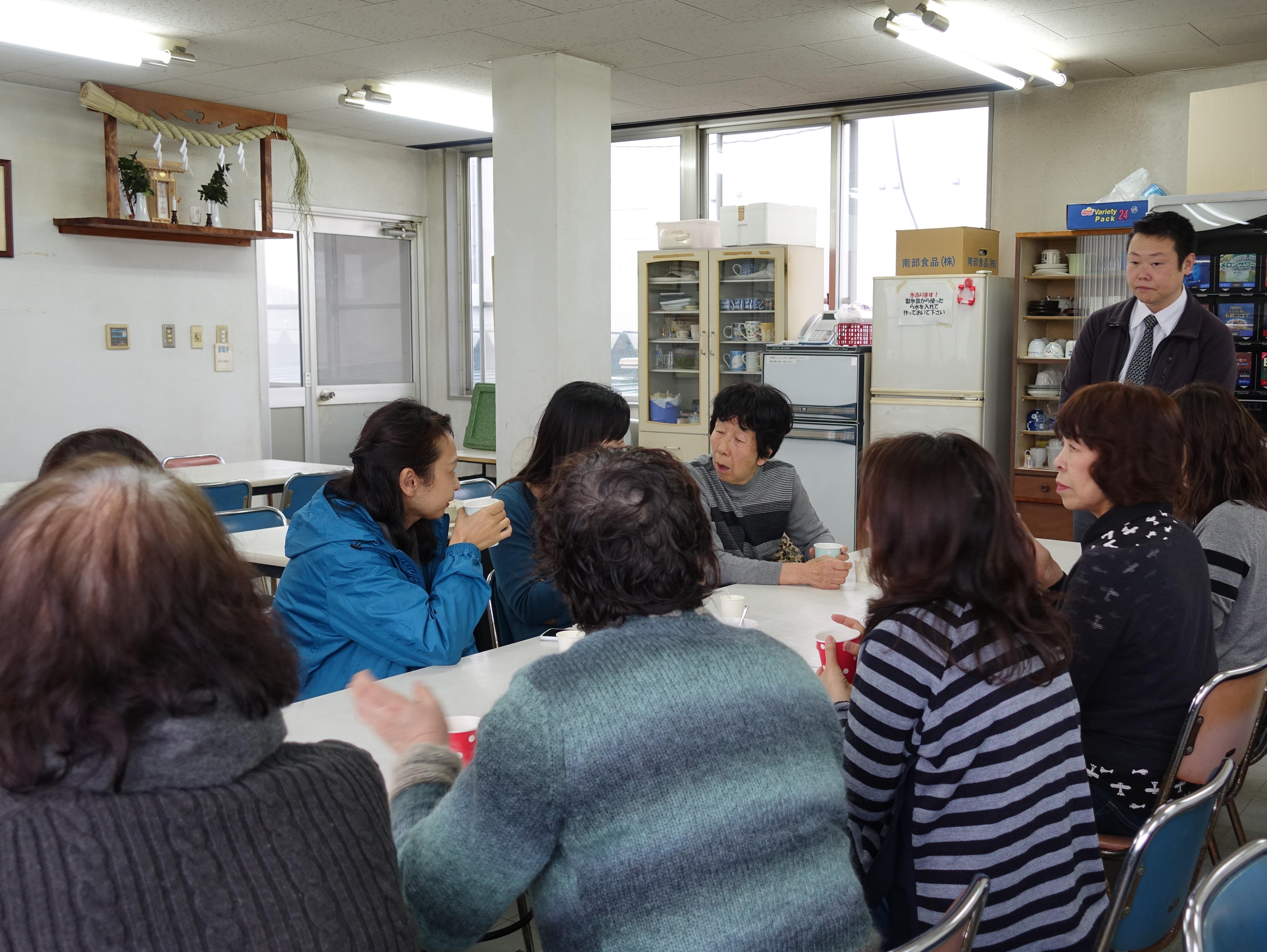
現場の苦労話なども聞きました
2017年2月23日、野毛ブロック委員会は「東都田舎金時豆」「東都須黒さんの味付けいなり」などの煮豆・惣菜を製造する㈱南部フーズを訪問しました。
工場の煮豆用の釜は、人間一人が入れるような大きさの二重構造。直火でなく蒸気で蒸す方法で約1時間半、おいしい煮豆が出来上がります。
試食で出された煮豆はどれもふっくらと柔らかく、とても美味でした。味付けは添加物を使用せず、砂糖と塩だけと知り安心しました。
原料の豆は、収穫時期によって違いがあるため煮る時間の調整をしていますが、どうしても仕上がりに多少の違いは出てしまうそうです。
北海道の豆の生産は減少していますが、東都生協の商品には全て国産原料を使用しているそうです。原材料の話、調達の苦労話など現場の声を聞くことにより、メーカーへの理解が深まりました。
食品添加物学習会&Let'sおにぎらず
食の安全について学習した後で「おにぎらず」作り
最初に食品添加物について学びました
配付された資料
東都生協では科学的見地に基づいた商品の安全基準を設け、計画的に衛生検査を実施しているため商品は安全なこと、法律を理解した上で情報を正しく選ぶことの大切さを学びました。
参加者からは「東都生協商品への安心感が高まった」「添加物について客観的に学ぶことができて良かった」などのほか、「1時間の講義では...。もっと聞きたい」という声も。
主催者は「食の安全を求める組合員が多いからこそ、東都生協が選ばれている」と納得したそうです。
おにぎらず作りでは、作り方を教わった後、「わたしのこだわり」商品を中心にそろえた具材で各自、自由に作って試食。
簡単にできておいしく、さまざまな商品の紹介もあって好評でした。
普段聞けない苦労話も...産直産地との調理交流会
新世代チャレンジプロジェクト産地・(農)房総食料センター、㈱野菜くらぶ、㈲山梨フルーツラインと交流
産地の取り組みや農産物について学びました
料理9点の豪華試食会
第1地域委員会は2017年2月21日、新世代チャレンジプロジェクトで応援中の(農)房総食料センター、㈱野菜くらぶ、㈲山梨フルーツラインを招き、「野菜・果物を知って産地ともっと仲良くなろう 調理交流会」を開催。
それぞれの取り組みや農産物について学んだ後、各産地農産物を使って産地の方と一緒に調理。「長ねぎのみたらし風」「糖しぼり大根カナッペ」など7品に主催者が調理した2品を加え、豪華な試食交流会となりました。
参加者からは「春の砂嵐に見舞われたり、産地は大変。野菜が欠品の時には今日の話を思い出したい」といった生産者を応援する感想が続出。
主催者は「前年度もコラボした3団体の皆さまから普段聞けない話を聞けて感動! 産地お薦めの調理も紹介できた」と大変喜んでいました。
天然酵母パン作りに挑戦
第5地域委員会がホシノ天然酵母を使用した「パン作り教室」を開催
自分たちで作ったパンで試食会

丸パン、にんじんパン
2017年2月20日、第5地域委員会は、ホシノ天然酵母を使用し、たまごやバターを使わない「パン作り教室」を開催しました。
講師の高橋恵美子さんからパン作りの流れについて説明を聞いた後、それぞれの班に分かれてパン作りをしました。
今回のメニューは、丸パン、にんじんパンです。パンのこね、分割、成形の過程の合間には酵母や小麦粉についても学習しました。
参加者からは、「パン作りは初めてでしたが、自分で作るパンはおいしい」「小麦粉も外国産と国産の違いが分かり良かった」など、好評でした。
主催者は「申し込みが多くて、天然酵母のパン作りに興味のある人が多いことが分かりました。参加者もとても意欲的に楽しんで参加されていたようでした」と話していました。
「浜の母さん 海の幸の料理教室」を開催
料理教室を通して「枝幸魚つきの森」運動への理解を深めました
右端が枝幸漁協女性部部長上野さん |
「バラちらし寿司」「秋鮭の三平汁」 |
まず、枝幸「魚つきの森」運動や加工工場について紹介。東都生協と枝幸漁協、北海道漁連が協定を結んで今年で10年。
植樹活動や交流などを通して生命の源である川と海を守り、漁場・資源管理型漁業によって生産される水産物を利用して豊かな食生活を推進する「枝幸魚つきの森」の取り組みが広がっています。
産地の北海道・枝幸町には毎年、東都生協の組合員が訪れ、植樹や鮭の稚魚やほたて稚貝の放流活動に参加しています。
放たれた鮭はベーリング海を2周し、4年で母川に回帰しますが、海の環境変化によって戻る鮭が減り、秋鮭の漁獲量は10年前の半分以下になっている現状が産地の枝幸漁協から報告されました。
同産地では朝水揚げされた鮭を昼には製品にしているので鮮度抜群であること、毛がにはメスと8㎝以下のものは漁獲せず、量を決めて大事に獲ることをルールとし、きちんと資源管理していることなどを学習しました。
その後は「枝幸の浜の母さん」こと枝幸漁協・女性部の皆さまと一緒に料理講習と試食。「北海道の話と、試食にひかれ参加した」という男性参加者も一緒に楽しく調理。
普段の漁の様子や地元での食べ方の話しで盛り上がった試食では、「とにかくおいしい」「冷凍秋鮭はアルミホイルをかぶせて焼くとしっとりおいしくできるなど、今後役立つ知識が得られた」と大好評でした。
「魚つきの森」マークの商品を組合員が利用することが、良質な水産物を普及させ、産地を元気にし、豊かな海を次世代に残すことにつながります。
組合員からは、「産地を応援していきたい」との声が上がり、料理教室を通して枝幸「魚つきの森」運動を進める理解が広がりました。
「浜の母さん、海の幸 料理教室」を開催
産直産地・枝幸漁協の森を守り、海を育て自然と共生する取り組みについて学習・交流
最初に、枝幸漁協の佐藤部長より、枝幸町の地形や自然、漁業、「魚つきの森」の取り組みなどについて説明。
枝幸町の紹介DVDも視聴し、持参していただいた「流氷」や、流氷の天使といわれる「クリオネ」の生きた実物も見ることができ、遠い枝幸を少し身近に感じられました。
参加者からは、「山を育てることで漁業を育て"みんなを幸せに"との取り組みには、あらためて第一次産業こそ生きる源と知りました」「枝幸の場所を勘違いしていました。養殖の方法も思っていたのと違い、新しい発見がいっぱいです」との声が聞かれました。
枝幸漁協女性部の皆さま
現地の自然やくらし、漁業の様子などを学習
熱く語る枝幸漁協の佐藤部長
各テーブルごとに枝幸漁協の女性部の方が講師として入り、浜の母さんの味や調理を教わりました。都会の私たち用に塩分を控えめにしていただきましたが、枝幸は漁師町なので、本場では塩分がもっと濃いとのことでした。
メニューは、枝幸の海の幸をたっぷり使った、バラちらし寿司・秋鮭の三平汁・秋鮭のバター焼・ほたてカレー風味の4種類。特に今年は毛がにの提供もあり、参加者は思わずにっこり。
お料理の一番人気は、塩鮭と白菜、にんじん、大根、ねぎ、豆腐と具だくさんの三平汁でした。
各テーブルで女性部の皆さまが直接指導
味を確かめながら料理
盛り付けには各テーブルの個性が
出来上がった料理をテーブルに並べ、参加者と枝幸漁協の女性部、北海道漁連の方々、東都生協の役職員が一緒に会食。枝幸の様子や暮らし、漁のこと、お料理のことなどを聞きながら交流しました。
参加者からは「鮭のバター焼きにしょうゆとみりんのタレをかけるのが参考になりました。」「新しいメニュー(ほたてカレー味)、素材を生かした三平汁など「海の幸」が本当においしかった。指導してくださった女性部の方の枝幸の話も楽しかった」などの感想が出されました。
盛り付けにもこだわりが
メニューは4種類
会食懇談、いろいろな方と話せました
千葉北部酪農農業協同組合を交流訪問(第6地域委員会)
「八千代牛乳」の味が生乳に近い訳
市販牛乳との比較実験 |
清潔な牛舎 |
子どもも大勢参加しました |
千葉北部酪農農業協同組合の信川氏、藤崎牧場の藤崎氏から同農協が生産する「八千代牛乳」や藤崎牧場の特徴、酪農の現状について教えていただきました。市販の牛乳と八千代牛乳の違いが分かる実験も行いました。
東都生協組合員から贈られた搾乳用の「もーもータオル」の活用や、清潔な牛舎を維持・管理する取り組みにより「八千代牛乳」生産者の原乳は細菌数が少ないことことについて説明を受けました。
市販の牛乳と比べ「八千代牛乳」は、低温で、しかも短時間で殺菌する高温短時間殺菌法(75度15秒、HTST法)を採用。「八千代牛乳」は生乳に近い、さらっとした癖のない味になるそうです。
今回の企画は、牧場見学や乳搾り体験を通して、千葉北部酪農農業協同組合との産地直結を実感し、利用につなげることが目的です。牛乳の消費が減り厳しい環境の中、手間やコストがかかるにも関わらず安全な牛乳を作り続ける酪農家の存在に、参加者一同感銘を受けました。
藤崎牧場は、藤崎さんが学生の時から持っていた「酪農をやりたい!」という夢を追いかけ、1頭の牛からスタートしました。しかし、後継者がいないため、あと数年で終わりになります。とても残念ですが、藤崎さんは「飼料や環境にこだわり作っている安全・安心な八千代牛乳の存在を広めてほしい」と語ります。
主催した第6地域委員会は「八千代牛乳を利用し紹介し、応援していくことが今の私たちにできることだと思います。第6地域委員会でも企画などを通し広く伝えていきたいと思います」と話していました。
おいしくてヘルシー、みんな大満足
東都生協の食材を使用して8品目を調理・試食
作り方も分かり参考になりました |
いずれも有機野菜・雑穀を使用 |
毎年試食会を開催して毎回異なるメニューを作ってきましたが、今回はれんこんステーキ、おからのポテサラ風、手巻き寿司、キャベツとひじきの重ね煮、ミニ玄米ハンバーグ、かぼちゃのサモサ、おからと豆腐の濃厚ガトーショコラなど8品目。
いずれも有機野菜と雑穀を使用し、ヘルシーでおいしい料理が出来上がりました。
参加者は「ヘルシー料理の作り方が大変参考になった」「家でも早速作りたい」と満足そうでした。
委員長の松本桂子さんは、「今年もヘルシー料理を皆さんに満足していただきうれしい。各家庭に戻ってぜひ実践してほしい」と語っていました。
組合員も職員も、若手生産者を応援
有機質資材「米の精」を活用した農畜産業についても学びました
「米の精」の取り組みを説明 |
肥料や飼料として活用が広がる「米の精」 |
東洋ライス㈱は、金芽ロウカット玄米と、BG無洗米製法から出る肌ぬかを粒状の有機肥料に製品化した「米の精」を紹介しました。
また、(農)多古町旬の味産直センターからは、肥料に「米の精」を使って甘さの強いさつまいも「べにはるか」を栽培していること、千葉北部酪農農業協同組合は牛の飼料に「米の精」を配合していることなどを説明。
産地・組合員・職員が共にテーブルを囲み交流しました。
「供給に携わる職員も産地に入って手伝うことで農を知り、組合員も買い支えるだけでなく産地の現状を知り、産地参入型で3者の力が集まる生協であってほしい」と、生産者は力説。
"親父の次に頑張る新世代"を応援したくなる企画でした。


