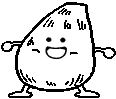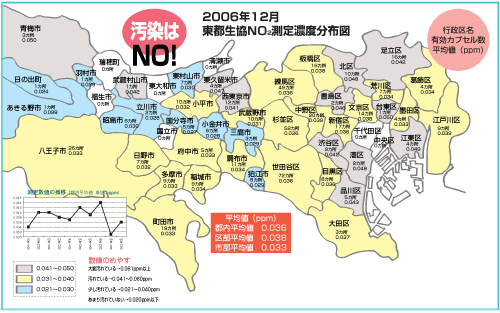すべてのカテゴリ
電気を消してスローな夜を「100万人のキャンドルナイト2006冬至」
電気を消し、ろうそくの灯りだけで過ごす静かな環境活動
東都生協では、2006年12月22日(冬至の日)に、環境活動の一環として「キャンドルナイト」への参加を呼び掛けました。
「100万人のキャンドルナイト」は、アメリカでエネルギー政策に抗議することから始まった自主停電の運動で、徐々に賛同する団体を増やして世界に広がっています。
◆取り組みに参加した組合員からの声
--------------------------------
キャンドルナイトの時、時間を見て電気を全部消しました。小学1年生だった孫はすぐカーテンを開けて近所を見回していました。真っ暗になると思ったらしいです。「みんなの家は電気がついている」と、とてもがっかりしていました。
来年はもっと変化のあることを期待しています。
(立川市・Tさん)
--------------------------------
「100万人のキャンドルナイト」に初参加。朝から「ろうそく」の準備。山形の和ろうそく、クリスマスのろうそくなど4本。玄関・リビング・ダイニングに火をともし、燭台で洗面所へ移動。キャンドルの下で本を読んで、ガラス越しの光の影に感動したり、帰宅した家族と明かりの下で食事。でも「あと10分ね!」などと言い出し、とうとう午後10時10分で終了。後日窓を拭くとすすで黒くなっていました! 時々またやろうかなと思った一晩でした。
(小平市・Sさん)
--------------------------------
◆取り組みに参加した職員からの声
--------------------------------
今年は家族で話し合い、クリスマスツリーは飾りのみ、電球は付けないことにしました。当日は、ろうそくの明かりで食事をしました。事前に買ったろうそくは、きっと電気代より高いのでは? でもなかなか良い感じで満足でした。
このろうそくで来年も実施したいと思います。
(組織運営部・W職員)
--------------------------------
真心をつないで
世界平和、核兵器廃絶への願いを熱く語り合いました
平和を願う心で一つになりました |
2006年11月29日から12月8日にかけて、都内5会場で平和委員会主催の(社)東友会(東京都原爆被害者協議会)との交流会が開かれ、延べ135人が参加しました。
今年で19回目を迎える交流会では、参加者一人ひとりが胸に秘めた思い、世界平和、核兵器廃絶への願いを熱く語りました。また、組合員が編んだモチーフをつないだひざ掛け112枚やニットの小物を、各会場で東友会に贈呈しました。
12月4日の国分寺労政会館では、(社)東友会事務局の村田未知子さんから「戦後61年を迎えた今でも、原爆による放射能の後遺症で被爆者は身体も心の傷も癒えず、戦後の保障の問題も未解決です。解決に向けて草の根運動を続けていきたい」との話がありました。
国分寺国分会の会長・西野稔さんからは、自身の被爆体験を踏まえ、経験を語る上の困難や、戦争のない現在だからこそ語り継ぎ検証していくことの重要性を話しました。
有志によるギター伴奏で「遠い世界に」などを歌い、緊張気味の参加者の表情も和らぎました。
「セモラ」は自立の強い味方
米ぬか100%の台所用石けん「セモラ」を製造する福祉工場エバーグリーンを見学
「セモラは、 |
メンバー全員、どの工程も |
2006年12月6日、福祉委員会主催で福祉工場エバーグリーンを見学しました。参加者はおとな6人、子ども1人。
エバーグリーンでは、精神障害がある方々への就労支援としてねり状米ぬか石けん「セモラ」を製造しています。
この日は前日までに仕込んだ石けんの充填作業日でした。できたての「セモラ」はまるでみそのような色と柔らかさで釜からにゅるにゅると出てきます。
それを工場のメンバーが、容器に1つ分ずつ入れて、計量、押して成形、ナンバリング、包装を行います。
「セモラは、よく泡立てて使ってください」と小さな工場ですが、一定時間ごとに作業者全員の手をアルコール消毒するなど、食品工場の品質管理を取り入れています。
また、仕込みごとにサンプルを保管し、組合員から品質に関するお申し出があった際は、即座に状況を確認できるようにしています。容器は焼却できる素材を使って環境に配慮しています。
メンバー一人ひとりは、障害を抱えながらも地域で自立して生活することを目指しています。「セモラ」を通しての東都生協組合員との交流は、とても励みになるとのことでした。
参加者からは、よく泡立てて使うとより洗浄力が出ることを再認識した、という声が多く聞かれました。
食と農通信 「これが 旬。 里いも!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年11月-(2)号より
|
里いもの皮をむくと手がかゆくなる人は、表皮の泥汚れを洗い落とした後、完全に乾かしてからむくか、塩を付けながらむきましょう。
料理例 ★里いものでんがく(4人分)
1. 里いも(8個)は皮をむき縦半分に切り、2〜3分ゆで、もみ洗いをしてぬめりを取る。
2. だし汁2カップ・みりん大さじ1・しょうゆ小さじ1・塩少々を鍋に入れ、(1)を10〜15分煮含める。
3. (2)が煮えたら水分をよく切り、金網でこんがり焼く。
4. 赤みそ大さじ7・酒大さじ2・みりん大さじ3・砂糖大さじ3とだし汁を合わせて火にかけ、とろりとするまで煮つめる(田楽みそ)。
5. (4)の田楽みそを焼けたいもに塗る。
12月2回企画「里いも」
108 400g前後
109 700g前後 徳用
ぜひご注文ください!
2006年12月東都生協NO₂測定濃度分布図
機関誌 『東都生協だより』 2007年3月号より
2006年11月30日(木)午後6時〜12月1日(金)午後6時の24時間、簡易カプセルでNO₂測定を行いました。その結果を報告します。
東都生協は1988年から二酸化窒素(NO₂)測定に取り組み、測定結果を「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供しています。この連絡会では生協のほか、さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定の積み重ねが大きな運動を支えています。
測定日時:2006年11月30日(木)午後6時〜12月1日(金)午後6時
配布数:901個
回収数:548個
有効カプセル数:490個
回収率:60.8%
※環境省が定めたNO₂の基準値は「0.04〜0.06ppmのゾーン、またはそれ以下であること」とされています。
お問い合わせ:東都生協組織運営部
TEL 03-5374-4756
(月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時)
東京の農業の実情を学びました
東京の農林業の振興を支える意義を学習
お茶の葉は、蒸し方によって |
2006年9月11日、東都生協の食と農委員会主催により、西立川にある(公財)東京都農林水産振興財団 東京都農林総合研究センターを見学しました。参加者は16人でした。
まず、生産技術科の木曽雅昭さんから、センターの概要説明がありました。新品種の育成や病害虫の総合的防除、食の安全・安心を確保するための技術開発、地域資源を利用した食品開発など、都民に役立つ試験研究が行われています。
その後、東京の農業の現状、特徴と役割、課題などと、それに対するセンターの役割や課題を学習し、センターの中を見学しました。
東京の農家は、ほとんど直接販売などの市場外流通であること、消費地に近いことから若い生産者が出てきていること、そんな人たちを支援し、環境に負荷を与えない農業技術開発に努めていることなど、最も私たちに近い東京の農業を知る良い機会になりました。
テロとの戦いは果てしなき世界戦争への道
機関誌 『東都生協だより』 2007年3月号より
参加者は人権の大切さを実感 |
2006年11月25日、平和委員会主催で千代田区神保町区民館にて寺中誠さん(アムネスティ・インターナショナル日本事務局長)を招き、「世界の戦争と人権」をテーマに学習会が開催されました。(参加者:10人)
「テロとの戦い」の実態は、お互いの敵をテロリストと呼び、誰に対する戦争かが分からないまま、勝ち負けのつかない戦争が果てしなく続くということ。
米軍拷問マニュアルに基づいた拷問と虐待が世界中で行われていること。イラク戦争のような情報戦が現代の戦争の特徴で、都市部への攻撃は子どもと女性の多くが被害者となり、またアフリカなどの紛争地域では10代の子ども兵士が何十万人もいて、過酷な訓練と行軍により精神を破壊していくことなどを学びました。
日本でも、入管法改正や共謀罪など人権に関わる問題があります。人権の大切さを意識し、日本と世界の人権の侵害に対して声を出すことが大事だと感じた学習会でした。
子どもの権利条約に関するワークショップを開催
1989年国連総会で採択された子どもの権利条約の4原則を学ぶ
子どもの権利を学びました |
「子どもの権利条約」という名前を聞いたことはありますか? 正式な名称は「児童の権利に関する条約」といい、子ども(18歳未満の児童)に保障されるべき権利を定めたもので、1989年11月国連総会にて採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しています。
この条約で定める権利は、(1)生きる権利(治療を受けるなど)(2)育つ権利(3)守られる権利(4)参加する権利--―に大別されます。2006年11月23日、東都生協の平和委員会は公益財団法人 日本ユニセフ協会の林田佳子さんを講師に、子どもの権利条約についてのワークショップを開催。5世帯12人の参加者とともに「子どもの権利条約」の条文が1つずつ書かれたカードを使いながら、子どもの権利について学びました。
小学校低学年の子どもにとっては難しい内容も含んでいましたが、「一番大切だと思う権利を5つ選んでください」という問いには、自分で考えながら「休み・遊ぶ権利」「搾取・虐待からの保護」などの権利を選んでいました。
子どもだけでなく、おとなも「権利」について再認識する機会となりました。
自分の気持ちに気付こう
子どもの虐待防止活動を考えるネットワーク事務局長の箱崎幸恵氏を講師に学習会
「そのときの自分の気持ちは?」 |
自分の気持ちに気付くには、 |
2006年11月10日、東都生協の福祉委員会が主催し、子育て支援企画「しつけ? 虐待? そのときの自分の気持ちに気付こう!」をさんぼんすぎセンターで開催しました。東都生協の組合員14人が参加。
講師は児童虐待問題のフリーランス・ライター、子どもの虐待防止活動を考えるネットワーク事務局長の箱崎幸恵さんです。
なぜ虐待をしてしまうのか? しつけと虐待はどう違うのか? をテーマに話が進みます。
参加者がそれぞれ「そのときの自分の気持ち」を紙に書いて発表し、それぞれの思いを分かち合い、言葉にして心をラクにしていくという参加型の学習会でした。「自分を愛するには、セルフ・エスティーム(自己信頼)を築くことが大事であり、人は自分が信頼されていると感じるとき、他者を信頼でき、信頼は連鎖する。暴力の連鎖を断ち、信頼の連鎖をつくりましょう」と結びました。
交流会では箱崎さんを囲んで悩みを話しながら、毎日の生活で言葉のキャッチボールをすることの大切さを実感しました。