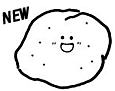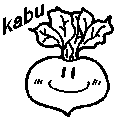すべてのカテゴリ
保育の基本を確認
機関誌 『東都生協だより』 2006年6月号より
預かる子どもが安全・安心に |
日頃の工夫や悩みを話し合い |
「保育ママ研修・交流会」が2006年4月~5月の期間に4回開催され、2006年度の保育ママとして登録されました。
4月5日(東京都消費生活総合センター)、19日(多摩消費生活センター)の保育ママ研修・交流会では、59人の保育ママが登録しました。
研修では、まず保育ママ制度が「助け合い活動」であること、一番大切なことは「子どもの安全」であるということを確認し合いました。
交流会では、「主催者も忙しいとは思うが、保育の様子にも気を配ってほしい」などの意見が出ました。
また、「保育ママ学習・交流会」で習った折り紙を保育ママの仲間から教えてもらったなど、ママ同士の和も広がっていました。
組合員同士の助け合い活動
機関誌 『東都生協だより』 2006年5月号より
「助け合いは思いやりの |
2006年3月9日、東都生協くらしの助け合いの会「ほっとはんど」の説明交流会が武蔵野公会堂で開催され、組合員16人が参加。
登録の手続方法や、研修でルールを学んでから活動をすることなど、コーディネーターからの説明を受けました。
活動は、産後の援助が増えていること、高齢者からは、かぼちゃを切ったり、季節の衣類の出し入れするのを手伝ってほしいなどの力仕事の依頼があるなどの体験談が語られました。
参加者からは「今は元気なので、できることはお手伝いしたいと思って登録しました」などの声が聞かれました。
東都生協 親子ヒロシマの旅
機関誌 『東都生協だより』 2006年6月号より
原爆死没者慰霊碑の前で |
2006年4月2日〜3日、4組の組合員親子と事務局の10人で平和募金企画「東都生協 親子ヒロシマの旅」を行いました。
1日目は平和記念公園にある平和記念資料館・原爆供養塔・韓国人原爆犠牲者慰霊碑などを見学。
原爆死没者慰霊碑・原爆の子の像・平和の観音像へは組合員より寄せられた千羽鶴を供え、亡くなられた人々や世界の平和を参加者全員で祈りました。
夕方は被爆者の方と交流会を行い「ここで感じたことを少しでも多くの人に伝えてください」「歴史を学ぶのでなく、歴史から学ぶのです」などの言葉に重みを感じました。
2日目は広島大本営跡や袋町小学校などを見学。袋町小学校は当時では珍しい鉄筋の小学校で、原爆に遭っても形が残り、家族と離ればなれになった人々が伝言を残しに小学校に集まったそうです。その時の壁に書いた伝言が保存されています。戦争が終わって61年目を迎え、時代がどのように変わっても心静かに平和を願う気持ちは変わりません。一日も早く戦争がなくなり、平和な世の中になることを願いながら帰路につきました。
食と農通信 「これが旬。新じゃがいも!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年3月-(2)号より
|
ビタミン、ミネラル豊富な 調理例 ★ ポテトグラタン
1. じゃがいも(600g)は3mm厚さの輪切りにして、水にさらして塩茹でする。
2. フライパンで牛ひき肉(160g)とみじん切りの玉ねぎ(1/2個)を炒めて、塩、こしょう(各少々)で味をつける。
3. グラタン皿(4枚)にバターを塗って、(1)のじゃがいもを並べ、温めた牛乳(1カップ)を注ぎ、(2)とチーズ(適量)を順番にのせ、200度のオーブンで20~25分焼く。
食と農通信 「これが旬。かぶ!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年3月-(1)号より
|
小かぶ
関ヶ原を境に東日本で多く生産されている。
冬は甘みが増すので炊き合わせや煮物に、春先は柔らかくなるので、酢漬けやぬか漬けに最適。
聖護院かぶ (大かぶ)
西日本で多く生産される。大きいものは4kgにもなる。
千枚漬けやかぶら煮などの煮物に用いられる。(煮くずれしにくい)
酸茎菜 (すぐきな)
根の部分は紡錘形、漬物の酸茎になる。
小かぶ料理法
春先は葉も実もやわらかくなるので漬物に、また葉はちりめんじゃこや桜エビ、ベーコンなど、うまみが出るものと炒め煮にするとおいしい。
伝えます! 子どもに平和を
機関誌 『東都生協だより』 2006年6月号より
ゴールでは7つのクイズに答えて、 |
2006年3月31日、平和委員会は「平和の大切さを親子で考えましょう! 多摩動物公園見学会」を開催しました。
大人10人・子ども15人が参加し、クイズラリーの用紙をもらってスタート。
「レッサーパンダのおなかは何色?」「マレーバクの模様はどれ?」などのクイズに答えてから動物の慰霊碑の前に集合しました。
「ぞうれっしゃがやってきた」の絵本の読み聞かせの後、平和委員の永尾寿孝さんから戦争の体験談を聞きました。「親子で動物をよく観察でき、平和の大切さが分かって良かった」などの感想がありました。
61年前の証人
機関誌 『東都生協だより』 2006年6月号より
夢違え地蔵尊で参加者へ説明を行う |
2006年3月25日、平和委員会主催の「下町戦跡碑めぐり」が、組合員21人が参加して開催されました。
一行はJR両国駅に集合し、東京都慰霊堂、台東区の東京大空襲追悼碑、弥勒寺、堅川地蔵尊、焼夷弾で焼けた榎、菊川橋夢違え地蔵尊、八百霊地蔵、東京空襲戦災資料センターなどの下町に残る東京大空襲の戦跡や施設を見学。
61年前に東京で起きた歴史の真実を知りました。
参加者は2時間の空襲で10万人以上の方が亡くなられた戦争の悲惨さをあらためて痛感しました。
どうする? 「リユースびん回収率65%」!
機関誌 『東都生協だより』 2006年5月号より
坂井職員から作業工程 |
環境委員会は2006年3月15日、参加者8人でリサイクル洗びんセンターと石川酒造㈱を訪問しました。
「ここは東都生協ときょうされんが作ったリユースびんを洗う工場であり、障害者の働く施設です。リユースびんは洗って繰り返し使うのでCO₂排出量が少なく、地球温暖化防止にも役立っています。ここ何年か東都生協でのリユースびんの回収率が下がっていて、働く人たちの仕事が減っています。リユースびんの良さを見直して利用し、東都生協に返してほしい」と、リサイクル洗びんセンターの坂井俊次氏から工場の案内とともにお話を伺いました。
リサイクル洗びんセンターを利用している石川酒造㈱の北川賢志氏からは、東京の酒造メーカーが統一びんにし、リサイクル洗びんセンターで洗ってもらうという構想を聞き、参加者は「早く実現すればうれしい。まずは、リユースびんの回収率100%になるように伝えていきたい」と話していました。
子どもの上手な預け方No.6 子どもと親が共に成長できる子育てを!
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年3月-(3)号より
|
いつも一緒にいると、親も子も煮詰まってしまうことがありますね。子どもは、親に元気がないと、なかなか幸せにはなれないものです。
子どもと時間を共有できる時期は、子育て中はとても長く感じますが、子どもは常に変化していきます。親にその変化を楽しむ余裕があると良いのですが、現実には難しいことが多いようです。
大切な子育て時間を充実させるために、第三者との関係を作ってお互いにリフレッシュする時間を無理なく持ってはどうでしょうか。
今はさまざまな預け方がありますが、そのとき大切なことは、子どもと親、自分たちにとって無理のない預け方を見つけることです。
核兵器のない平和で公正な世界のために
機関誌 『東都生協だより』 2006年4月号より
久保山さんの墓前で |
3・1ビキニデー集会に東都生協から4人が参加しました。
この集会は1954年にアメリカがビキニ環礁で行った核実験により第五福竜丸が被爆し、久保山愛吉さんをはじめとした
乗組員が亡くなったことを忘れまいと、毎年行われています。
当日は久保山さんのお墓へ向けて行進した後、屋内で集会が開かれ、参加者一同平和の大切さを感じながら、久保山さんが残した「原水爆の被害者はわたしを最後にしてほしい」の言葉をかみしめました。