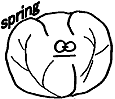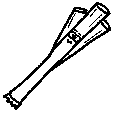すべてのカテゴリ
子どもの上手な預け方No.5 「子育て広場」など公共施設を利用するとき
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年3月-(2)号より
|
多くの自治体が、親子一緒に過ごす場として、保健所や児童館などで「子育て広場」を開設しています。
行けば同じ年頃の子どもを持つ母親同士、話は尽きないと思います。そこで起こるのが、おかあさんが話に夢中になりすぎて子どもから目を離してしまうこと。もちろん常勤のスタッフはいますが、人数は限られています。子育て広場では、子どもの安全は親が責任を持つのが基本的なルールです。
また回数を重ねるとグループが固定し、他のお母さんを寄せつけない雰囲気が出てくる、というのもよくある話です。子育て広場を大事にするためにも、新しい親子を孤立させないように、先輩は少し気にしてほしいものです。
食と農通信 「これが旬。春キャベツ!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年2月-(2)号より
|
●調理例 コールスローサラダ
1. 春キャベツ(1/2個)の芯を切り落とし、葉はザク切りする。ボールに入れて塩をふり、手でもんで水分を出し、半分くらいの量になったら水分を搾り取る。
2. 玉ねぎ(1個)は薄くスライスして水にさらしておき、ハム(5枚)はキャベツと同じに切る。
3. (1)(2)を合わせたものに、ノンオイルマヨネーズ(1/4カップ)を混ぜて、塩・こしょうで味を調えて出来上がり。
親は「お金の先生」になろう
機関誌 『東都生協だより』 2006年4月号より
「子ども自身で考えることが |
2006年2月14日、東京都消費生活総合センター(飯田橋)にて、ファイナンシャルプランナーの明石久美氏を講師に迎え、くらし委員会主催「子どもの金銭教育学習会」が開催されました。参加者は35人。
子どもに教えるための心構え、お小遣いの与え方・金額の決め方、知らないとだまされるさまざまな危険性などについて学びました。
お金の使い方や役割をまずは親がよく理解し、バランスよく子どもに教えていくことが大切だそうです。
お小遣いは計算ができ、お金の価値が分かるようになってからでも遅くはなく、与え方は定額制、労働制、手当制(基本+お手伝い手当など)といろいろあるとか。
「親が積極的に金銭教育をして、身近な『お金の先生』になってあげてください。子どもには『財産』より『生きるチカラ』を残してほしい」と明石さん。若いお母さんを中心に幅広い年代からの参加者は皆、真剣に聞き入っていました。
きょうされんの皆さんと交流しました
機関誌 『東都生協だより』 2006年3月号より
作業所商品の「借り物競争」 |
かわいい商品が多く迷います |
2006年1月20日と2月6日の2日間「きょうされん東京支部と東都生協との交流会」が開催されました。
東都生協は21人、きょうされん東京支部は23団体85人が参加し、組合員と共同作業所のメンバーが直に触れ合い、和やかに交流できました。
きょうされんは、共同作業所や授産施設が加盟し障害者福祉の向上のための活動に取り組んでいる団体です。東都生協では1991年から、署名や作業所の自主商品の販売などを通して、障害者福祉の向上のために提携活動に取り組んできました。
この交流会では、現在取り組み中の第29次国会請願署名についての説明があり、「応益負担導入についての見直し」という大きな目標を掲げながら参加者全員で国会請願署名の成功を確認し合いました。
各作業所の活動内容紹介や自主商品のアピールがあり、参加した人たちは商品を手に取りながら、それぞれの商品への思い・工夫などをメンバーや職員から聞くことができる良い機会となりました。
作業所と地域の人たちとの場として設けた交流会ではありましたが、地域の組合員の参加が少なかったことは残念でした。今後はより多くの組合員がメンバーと交流できるように考えていきます。
子どもの上手な預け方No.4 仕事を持っているお母さんたちへ
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年3月-(1)号より
|
仕事と家庭を持ち忙しいお母さん。そんな毎日の中で、子どもたちにとってお母さんといる時間はとても大切なひとときです。
小さいうちに、お母さんから伝えてほしいことの一番は「楽しく食事をすること」です。そして食べる時には手を洗い、
食前食後のごあいさつ、食事の時にはテレビを消してなどです。
配膳などの食事の準備を手伝わせることは親にとって、かえって大変なものですが、子どもたちには大きな財産になります。
「カバさんのお口は?」というと、大きく口を開けてくれます。嫌いな物を口に入れ「あれ、どこに入ったかな? たぬきさんのお腹になっちゃった。」と楽しく話しながら好き嫌いなく食べさせましょう。
最後は水かお茶で口をきれいにし「ごちそうさま。おいしかったね」。
子どもの上手な預け方No.3 幼稚園や保育園の場合
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年2月-(2)号より
|
―― 子どもを預ける時に心掛けたいことをシリーズでお届けしています ――
ほとんどの子どもにとって最初の親子分離の時なので、大切に準備して進めてあげたいですよね。先生とのコミュニケーションももちろんですが、親子のコミュニケーションが大切です。
1.朝はゆとりを持って、子どものペースを守ってあげる
2.子どもの体調をよく知っておく
3.帰宅後、親子で向き合うひとときを持つ
大人は今までの人生経験から、いろいろなことを理解し納得して行動することができますが、子どもたちにとっては全てが初めて、未知の世界なのです。
子どもが安心して行動できる基となる親子関係ができると、自然と他者との関わり方が、親子そろって見えてくるのではないでしょうか。
慣れれば優しい生ごみリサイクル
機関誌 『東都生協だより』 2006年3月号より
庭がなくても、 |
2006年1月13日、環境委員会主催で生ごみの有効利用を広く進めるために「生ごみリサイクル教室」がさんぼんすぎセンターで開かれました。
講師は「NPOたい肥化協会」の会田節子氏と浅井民雄氏。ビデオも交え、プランターやダンボールを使うなど、いろいろな事例でのぼかし肥を使った堆肥の作り方を教えていただきました。
13人の参加者は熱心に聞き、講習会が終ってからも講師の周りには個人的に質問する人の輪ができました。
食と農通信 「これが旬。長ねぎ!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2005年12月号より
|
長ねぎは、ビタミン類は少ない一方、新陳代謝を高め、疲労回復に効果的な働きをする硫化アリルという成分を含んでいます。ビタミンB1の吸収を助け、その働きを高めるので、B1を含む食材(豚もも・ごま・など)と一緒に食べると良いでしょう。
また、鼻詰まりや頭痛を抑制し、体を温める効果もあるといわれています。風邪気味かなと思ったら、刻んだ長ねぎとしょうが+みそ適量に熱湯をかけた汁を試してみてください。
●調理例 ねぎみそ (4人分)
1. かたゆで卵(1個)を作り、黄身だけ取り出してつぶし、みそ(30g)に混ぜる。
2. 長ねぎ(1本)は白い部分をみじん切りにする。またかつおぶし(1/3カップ)を手でよくもんで粉にする。
3. (1)(2)をみりん(大さじ1)で混ぜてお皿に薄く塗りつける。
4. 焼き網を熱し、(3)のお皿を伏せてのせ、表面に焼き色がつく位に焼く。ごはんにのせてできあがり。
「次の世代へ伝える食 今私たちにできること」
管理栄養士・安藤節子氏を講師に、食育での食事の重要性について学習
「おやつの与え方にも気を付けて!」 |
2005年10月26日、食と農委員会は食育に関する学習会を東京都消費生活総合センターで開催しました。講師は管理栄養士の安藤節子さん。組合員22人が参加しました。
◆食事とは何か「現代は、情報が氾濫し、情報に振り回されて自分を根無し草にしている」「調理済みの加工食品があふれ、見て・聞いて・触って・匂って・味わうという五感を上手に使って感じるプロセスが奪われている」と安藤さんは指摘。
「食事の持つ意味は、一緒に作って食べること、会話をすることという生活行為」と話しました。
◆五感豊かに脳育て赤ちゃんは、生まれてくると欲求を訴えます。食欲もその一つです。子どもの成長段階に合わせて、五感を上手に使って一緒に作るプロセスを経験させると脳も育ちます。
好き嫌いが出始めたときには、大人がおいしそうに食べて見せたり、子どもが嫌いなものを食べたときに褒めてあげることで、子どもは食べることを心地良いと感じるようになります。
食べることを強制するのではなく、食べたいという意欲が自主的・自発的に生まれ、それを育てる環境づくりを心掛けましょうということでした。
◆食育とは季節の物が巡り巡ってくること、それが旬で、私たちは生き物が一番元気なときに、その命を頂きます。
「素材を食べることを大事にし、いろいろなものを子どもと共に調理して食べること、会話のある楽しい食卓をともにすることが何よりも大切」安藤さんは強調。
若いお母さんからも実生活に則した質問があり、充実した学習会となりました。
明かりを消して「100万人のキャンドルナイト2005冬至」
夏至と冬至の午後8時〜10時の2時間、照明を消しロウソクを灯して過ごすスローライフ運動を進めています
東都生協では、環境を大切にする、さまざまな活動を進めています。2005年は6月21日(夏至の日)に続き、12月22日(冬至の日)に環境活動の一環として「キャンドルナイト」に取り組みました。「キャンドルナイト」は、アメリカでのエネルギー政策に抗議する自主停電の運動から始まりました。夜8時から10時の2時間、明かりを消した暮らしを呼び掛けています。
◆取り組みに参加した組合員からの声
--------------------------------
今回も、ろうそくの火をつけて食事をしました。
電気の有り難さを(便利で快適な生活を送れるので)つくづく感じました。実は、うちでは、キャンドルナイトを始めてから夕食の時の、落ちつく感じがとても気に入って、時々、やっています。
電気の有り難みを考える良い機会でもあり、無駄な電気を使わないように気を付けるようにもなりました。
これからも「キャンドルの光で夕食」を続けていこうと思っています。
(調布市 Tさん)
12月のキャンドルナイトには、アロマのろうそくなどたくさん用意しておいて楽しみました。それ以来、夜、茶わん洗いする時などは、あまり明るくなくても良いので、ろうそくを並べて、洗ったりして楽しむようになりました。
(目黒区 Tさん)
外が明るいので(他の家の光ですが)、電気が無くても過ごせました。他の人も地球のことを考えながら過ごしていると思うと、つながっているみたいでちょっと楽しい(でも、外が明るいということは、周りの人はやってない‥?!)。
子どもがもう少し大きくなったらキャンドルをともし、語り合って過ごしてみたいなぁ、と思いました。
(世田谷区 Kさん)
◆参加した職員からの声
--------------------------------
家の明かりを全て消して、8階から外を見て、どんなに街が明るいか見てみました。予想以上に外は明るく、無駄と思われる明かりがキラキラしていました。
防犯上のこともあると思うので、明かりの使い方を家族と話し合いました。
(足立センター M職員)
--------------------------------