すべてのカテゴリ
3.1ビキニデー
組合員活動情報紙 『ワォ』 2005年4月号より
2005年2月28日~3月1日の日程で日本生協連と静岡県生協連が開催した「3.1ビキニデー」に東都生協から組合員3人が参加しました。
2月28日の「虹のひろば」では、さまざまなセッションが開催され、その中でも、ピースボート・野平さんの「日本・中国・韓国の市民による共通の歴史教科書作り」への取り組み報告は、特に参加者の印象に残ったようです。
3月1日には、1954年の米国による太平洋・ビキニ環礁での水爆実験で被ばくし、半年後に死亡したマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員、焼津市の久保山愛吉さんの菩提寺まで約1,800人で行進しました。
その後、被災51周年3.1ビキニデー集会では、生協が取り組む平和の活動をアピールしました。
この1954年3月1日に被災した第五福竜丸が夢の島(江東区)に保存されているのをご存知ですか。
毎年、「お花見平和のつどい」を行っています。今年も4月2日に開催されます。
きょうされん東京支部との交流会を終えて
機関誌 『東都生協だより』 2005年5月号より
|
|
|
きょうされん東京支部と東都生協との交流会をさんぼんすぎセンター(2005年1月27日)、府中市ふれあい会館(同年1月28日)、昭島あいぽっく(同年2月17日)の3会場で開催。
延べ参加人数は共同作業所からは112人、東都生協組合員からは63人となりました。会場では各作業所の紹介、自主商品の展示や販売と自主商品の製作実演など和やかに交流が行われました。
製作実演は事前に何度も練習を重ねていたそうです。
当日は大勢の人の前で発表する真剣な表情を見て、参加者は心から応援したいと思ったようでした。
各作業所は地域とのコミュニケーションを持つことが重要と考え、これからも地域に根差した交流や関わりをつくっていきたいと発表していました。
当日参加した組合員と作業所で地域単位の交流について話し合っていたところもありました。
今後、東都生協としてもブロックや支部活動の中で作業所などの自主商品の紹介を行い、少しでもメンバーの成果を形にしていきたいと考えています.
きょうされん「第28次国会請願署名と募金」にご協力いただき、ありがとうございました。
期間:2005年2月1回~4回
署名:5,898筆(4月14日現在)
募金:380,127円(4月14日現在)
組合員の皆さまからお寄せいただいた署名は6月に国会へ提出し、共同作業所をはじめとした成人期障害者の施設充実や障害のある人も安心して地域で暮らせるような、具体的な手立てを求めます。
募金は署名用紙の印刷代やきょうされん資金として活用されます。
日本の近現代史についての学習会を開催
組合員活動情報紙 『ワォ』 2005年4月号より
|
東都生協は2005年2月5日・12日の両日、明治大学文学部・山田朗教授を講師に招き、近現代史についての学習会を開催しました。
どちらの学習会とも参加者は、メモを取りながら熱心に聞き入りました。以下、学習会の概要をご紹介します。
第1回―膨張主義の系譜と植民地支配の特徴―
日本は、明治維新直後からロシアの南下を非常に恐れ、対外膨張を志向する。これは、「主権線」(国境線)を守るためにその外側に「利益線」を確保するという当時の考え方。
日本の植民地支配の特徴として、
- 皇民化教育の徹底
- 労働力の確保(強制連行、強制労働)
- 軍事力の補充(植民地にも徴兵制を導入)
- 物的資源の収奪(食糧、資源)
第2回―現代に残された課題―
サンフランシスコ対日講和条約(1951.9.8調印)によって戦後処理が行われた。
この講和会議はアメリカ主導で行われ、ソ連は署名を拒否、中国・台湾・韓国・北朝鮮は戦勝国ではないという理由で除外。日本のアジアに対する占領・支配の処理としては、きわめて不十分なものであった。
- 戦争賠償は総額で1兆円と少ない(ドイツの8兆円、日本国内への旧軍人への補償40兆円とは対照的)
- 直接の戦争被害者にわたるような処理がなされていない
- ODAの形でアジア諸国に供与されたものは、東南アジアへ進出した日本企業を経て日本に還流する構造となっていた。
このため、1990年代以降、50件以上の戦後補償を求める裁判が提訴されている。例えば、
- 強制連行・強制労働問題(虐待・賃金未払いなど)
- 従軍慰安婦問題
- 軍隊への食糧・物資・施設提供による問題(住民が餓死・病死)
- 日本軍の軍票(代用貨幣)が未処理
- 強奪された私有財産(文化財)問題
食と農通信 これが旬
組合員活動情報紙 『ワォ』 2005年1月号より
春の七草の筆頭野菜として親しまれてきた"せり"の香りの元となる成分には、保温効果・発汗作用があるため風邪予防や冷え症に良いとされています。
また、健胃効果があるので、お節料理を食べ過ぎた後の小正月には、せりを使った料理はいかが!
「簡単レシピ」
<せりのおかゆ>
(1)ご飯に水を加えおかゆを作る。
(2)粗く刻んだせりを散らし、しょうゆを少したらす。
(3)熱々をかき混ぜて食べる。
※おかゆは消化が良い上、体を温める働きがあります。せりの保温作用がますますアップします。ゆずの皮を散らすと香りもアップ。
<せり湯>
(1)せりを刻み、茶碗に入れる。
(2)砂糖・かつお節少々を加え、熱湯を注ぐ。
(3)好みでおろししょうがを加えてもよい。
暖かい贈り物ありがとう
機関誌 『東都生協だより』 2005年3月号より
「東友会と交流し、被爆体験を聞きました。」でご報告した東友会(東京都原爆被害者団体協議会=東京在住の被爆者の会)との交流会で、当日参加された東友会の皆さんからお礼状(11団体14枚)をいただきましたので、その一部をご紹介します。
--------------------------------------
「通院の行き来に早速使わせていただいております、見知らぬ方より時間のかかる高価な編み物を頂き、ありがとうございます。」
--------------------------------------
「皆さまの心暖かいお気持ちの手編み膝掛けを頂き本当に感謝しております。厚くお礼申し上げます。本年被爆60年に当たり、あの惨劇を想い浮かべるとき、ヒロシマで無念の最後を遂げた家族たちを忘れることができません。」
--------------------------------------
「この編み物を贈る訪問活動が、一人一人の被爆者たちに「生きる力」を与えてくださり、被爆者が独りではないと、地区の会に結集させる力をいただきました。本当にありがとうございました。」
第3章 私たちのためのマネー講座「架空請求について」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2004年12月号より
皆さんの中に身に覚えのない請求書が届いた...という経験はありませんか?!
近頃、利用した記憶のないサイトの使用料の請求や、債券回収通知が届くといったいわゆる架空請求にまつわるトラブルが急増しています。
あたかも、正式な通知のように見せかけ、請求金額も大半が10万円以下といかにもありそうな金額が特徴。手口も増々巧妙化してきています。
もし、こんな請求が来たら身に覚えがない場合は、連絡せず、無視しましょう。
証拠は保管し、悪質な請求を受けた場合は、警察に届けましょう。
架空請求は何らかの名簿を入手した悪質業者がアトランダムかつ大量に送っているものと考えられているので、皆さん、個人情報の管理は慎重に行ってください。
食と農通信 これが旬
組合員活動情報紙 『ワォ』 2004年12月号より
大根の根(白い部分)は、ビタミンCが豊富で、澱粉の消化を促すジアスターゼや、焼魚に含まれる発がん性物質を分解したり蛋白質や脂肪の消化を助けるオキシターゼも多く含まれています。
焼魚や天ぷらに「大根おろし」は理にかなった生活の知恵といえるでしょう。
また、葉の部分は緑黄色野菜の仲間で、カロチンやビタミンB2・ビタミンCの他、ミネラルも含んでいます。
「大根豆知識」古代エジプトのピラミッド建設記録に、奴隷に支給した大根の費用が記録されています。日本には奈良時代に伝えられ、室町時代に一般市民に幅広く普及しました。
<民間療法>葉を陰干しして乾燥させて、お風呂に入れると身体が温まり、冷え症・神経痛・腰痛・肩こりに効果があるといわれています。
12月3・4回企画(予定)の三浦大根は、煮込んでも表面が凹みません。
「おでん」や「ふろふき大根」など、身も心も温まる冬ならではの料理に最適な1品です。
声明文「イラクへの自衛隊派遣延長に反対し中止を求めます」を提出しました
東都生協は、イラクへの自衛隊派遣延長に反対しその中止を求める矢野洋子理事長代行の...
東都生協は、イラクへの自衛隊派遣延長に反対しその中止を求める矢野洋子理事長代行の声明文を、2004年12月16日に首相官邸に送付しました。
「家計から見た税」学習会報告
機関誌『東都生協だより』2005年3月号より
東都生協・くらし委員会は2004年12月13日、日本生活協同組合連合会・組合員活動部の中野理恵子氏を講師に迎え、生協での家計活動について2003年度「全国生計費調査」結果から「家計簿から見えるくらしの今」というテーマでお話いただきました。
「全国生計費調査」は、全国の生協の組合員からモニターを募り、日本生協連「家計簿」に記帳いただいた同一世帯の毎月の家計収支を元にして集計されています。
2004年度のモニターは6生協合計1,894人で、東都生協からも34人が登録しました。
2003年度の結果から見ると、
- 収入に占める社会保険料(健康保険・介護保険・年金・雇用保険)の割合は 9.54%(年間平均:704,560円)
- 年間の消費税額は平均170,501円、収入に占める割合は2.31%
- 公的負担(税金+社会保険料)が収入に占める割合は18.20%・年間約134万円 ――となっています。
中野氏は「生協の家計活動のデータは、個人のくらしの羅針盤であるとともに、社会的な発言のバックボーン」だとして「社会に対し発言していこう」と提起しました。
参加者はさまざまな生活スタイルについて互いに学び合い、大きなテーマについても考えさせることになった学習会でした。
【資料】税・社会保険料調べ
(全国生計費調査――家計簿モニターより)
2004年12月東都生協NO₂測定結果のご報告
機関誌 『東都生協だより』 2005年3月号より
2004年12月2日(木)午後6時~12月3日(金)午後6時の24時間、
簡易カプセルでNO₂測定を行いました。その結果をご報告します。
東都生協は1988年から二酸化窒素(NO₂)測定に取り組み、測定結果を「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供しています。この連絡会では生協の他、さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定の積み重ねが大きな運動を支えています。
測定日時:2004年12月2日(木)午後6時〜12月3日(金)午後6時
配付数:1033個 回収数:719個 有効カプセル数:598個 回収率:69.6%
※登録測定数とは定点測定のことで、数年間にわたり同じ場所を測定することです。
※環境省が定めたNO₂の基準値は「0.04~0.06ppmのゾーン、またはそれ以下であること」
とされています。
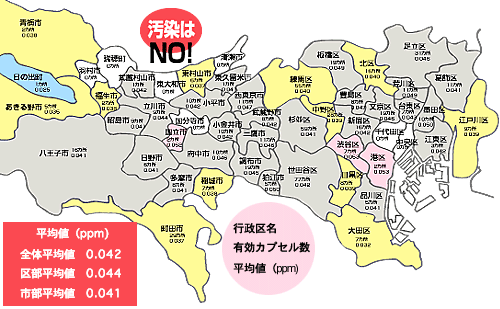
▲地図をクリックすると拡大します
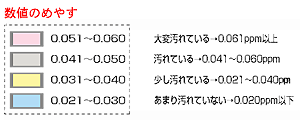
測定日時:2004年12月2日(木)午後6時〜12月3日(金)午後6時
配付数:1,033個 回収数:719個 有効カプセル数:598個 回収率:69.6%
※登録測定数とは定点測定のことで、数年間にわたり同じ場所を測定することです。
※環境省が定めたNO₂の基準値は「0.04~0.06ppmのゾーン、またはそれ以下であること」
とされています。




