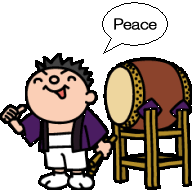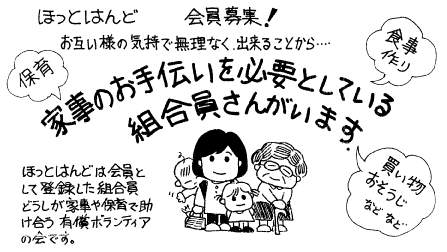すべてのカテゴリ
あなたも「電気ダイエット」に挑戦してみませんか!
組合員活動情報紙 『ワォ』 2007年3月-(2)号より
|
東京電力から届く「電気ご使用量のお知らせ」には昨年同月の使用量が載っています。CO₂の削減とともに電気代も安くなり一石二鳥。今年はどれだけ減らせたか、増えたのはなぜか、家族と一緒に考えてみませんか!
地球温暖化の原因のCO₂を減らそうと11月の電気使用量削減にチャレンジした「電気ダイエットコンクール」には49人の応募があり、38人から報告がありました。前年同月と比べ、減った人と増えた人の割合は半々でした。抽選で15人には「ダイエットしたで賞」その他の人には「参加賞」を贈りました。
*家族の協力で177kWhも削減できた
*体力をつけたり、もう一枚着るなどして暖房を減らした
*パソコンの使用量が増加傾向で悩んでいる
*夫や子どもが無関心で協力してくれず頭が痛い
*子どもが生まれたなど、増減にはさまざまな理由がありました。
参加者からは「どんなところで無駄がでるのか分った」「これからも家族を巻き込んで楽しくやっていきたい」との感想がありました。
![]()
待機電力をこまめにカット
電気製品を使用していないときに、タイマーなどのために消費される電力が"待機電力"。ビデオデッキ、オーディオコンポ、テレビ、電子レンジなどが代表的です。そしてその合計は、家庭の電力消費のなんと10%にも。
ここまでいくと「少しくらい」とも言っていられない数字です。その対策は、使っていないときに電源プラグをコンセントから抜くこと。少し面倒ですが、まずは使用頻度の低いものからやってみましょう。スイッチ付きコンセントの活用なども便利です。

電気製品の主電源を切って待機電力を90%減らせば
↓
1年間の節約金額約6,000円
1カ月だと約500円
出典/環境省 環のくらし
食と農通信 「これが旬。絹さや」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2007年2月-(2)号より
|
今年は暖冬傾向で、青果物の作柄がとても不安定になっているようです。企画の変更などあらかじめご了承ください。
料理例 ★ 絹さやのピーナッツあえ1. 絹さや(100g)は筋を取り、塩を加えた熱湯でゆで、冷水にひたし水気を切る。
2. ささみ(2本)は筋を取り、耐熱容器に入れて酒と塩をふり、ラップをしてレンジで3〜4分加熱し粗熱がとれたら食べやすく裂く。
3. ピーナッツバター大さじ1と1/2、砂糖大さじ1/2、しょう油大さじ2/3であえ、衣を作り、絹さやとささみをあえる。
2006年度の平和募金のご報告
平和な世界を次世代に引き継いでいくために
2006 親子ヒロシマの旅 |
|
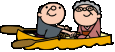
2006年度は、組合員の皆さまより 4,514,113円 もの募金をお寄せいただきました。
ご協力ありがとうございました。
2005年度より2,957,899円が繰り越され、2006年度募金と合わせて、収入合計は7,472,012円となりました。
お預かりした募金を活用した主な活動と支出金額をご報告します。残金6,075,463円は、2007年度に繰り越させていただきます。
2006年度活動報告(支出合計 1,396,549円)
◇親子ヒロシマの旅 (262,844円)
2006年4月2日(日)〜 4月3日(月) 参加9人(うち、子ども4人)
◇沖縄戦跡・基地巡り(293,600円)
2006年10月24日(火)〜 10月27日(金) 参加6人
◇松代大本営地下壕見学会 (79,170円)
2006年7月27日(木) 参加13人(うち、子ども2人)
◇ピースアクション2006 ヒロシマ平和代表団 (307,510円)
2006年8月5日(土)〜 8月7日(月) 参加4人(うち、子ども1人)
◇ピースアクション2006 ナガサキ平和代表団 (353,425円)
2006年8月7日(月)〜 8月9日(水) 参加6人(うち、子ども1人)
◇東京都原爆被爆者団体協議会(東友会)への支援 (100,000円)
1月新春の集い
◎ 2007年度 平和募金企画の予定
・親子ヒロシマの旅 実施済み 2007年3月26日(月)〜 3月27日(火)
・沖縄戦跡・基地巡り 実施済み 2007年3月27日(火)〜 3月29日(木)
・お花見平和のつどい&東京大空襲・戦災資料センターツアー 2007年4月7日(土)実施済み
・松代大本営地下壕見学会
・ヒロシマ平和代表団 8月
・ナガサキ平和代表団 8月
・都内企画(親子平和企画) 10月
・東友会への支援 1月
・3・1ビキニデーへの参加 3月
・戦争体験文集編纂
など
31人で鮭3本を料理!!
千倉町南部漁協販売㈱を講師に「お魚料理教室」
堀さん(右から2人目)に教わって、 |
食と農・東小委員会主催の「お魚料理教室」が、2007年11月29日、新宿消費生活センターで開かれました。
講師は千倉町南部漁協販売㈱の堀 優子氏。参加者は調理台に分かれて大きな鮭と格闘。炊きこみご飯やあら汁、けんちん焼きなどを作りました。
「魚1本を扱うのは初めてなのですごく新鮮」「来年は1本で供給されているものを買いたい」など。若いお母さんも多く、「とても良かった」「ぜひ家で作ってみたい」と大好評でした。
保育ママの活動が始まります
お子さんを保育する組合員同士の助け合いの活動
子どもの安全が第一 |
作って遊べる折り紙講習 |
「2007年度保育ママ研修・登録会」は2月から3月にかけて3カ所で開催され、2007年度の保育ママに139人が登録しました。
さんぼんすぎセンターでは2007年2月27日に開催。保育ママ委員会から、保育ママ制度は組合員同士の助け合い活動であることや、保育中の注意などの説明がありました。
今年度は研修に重点をおき応急手当の実習など、今後の保育ママの活動に役立つことを行いました。
交流会では「泣く子の対応」をテーマに意見交換を行いました。
「だっこして外の景色を見せる」などの体験談が出され「保育ママも、託すママも時間と心に余裕を持つことが大事」という言葉にみんな納得でした。
ありがとうの心で助け合い
組合員相互の自主的な家事援助活動
会員登録は6ケタコードで |
「東都生協くらしの助け合いの会 ほっとはんど」説明会が2007年2月14日に多摩消費生活センターで、2月26日は文京シビックセンターで開催され、会員12人と未会員10人が参加しました。
組合員同士の助け合いの会であること、有償の家事援助であることの説明の後、懇談に移りました。
「初めて活動に入った時はこれでいいのかと不安に思うこともあったが、大変喜んでいただき、よかった」「○曜日の午前とか定期的な活動もあるが、お互いの都合で次はいつとその都度決めて活動している」などの体験談、保育園の送り迎えが楽しいとの話、70歳で保育や家事援助をしている会員の話も披露され、主催者から「お互いさまの気持ちで、できるときにできることをやってみませんか」との呼び掛けがありました。
参加者からは「経験談を伺い、不安が解消されました」「援助できることがあれば、時間の合うところで参加したい」などの声がありほっとはんどの活動を知らせ、広げる機会となりました。
食と農通信 「これが旬。せり!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2007年1月-(1)号より
|
カリウムを多く含むので、常食すると高血圧の予防にも。
料理例 ★せりのいそべ巻き
1. せりはよく洗い塩ひとつまみを入れた熱湯で軽くゆで水に取り、手早く水気を切る。
2. のりを4つ切りにし、せりを乗せて巻き、半分に切って盛りつける。
3. だし汁で薄めたしょうゆを添える。
料理例 ★せりのご飯
飯が炊き上がったらせりを手早く上にまぶしてふたをする。せりの香りが釜の中いっぱいになったら盛りつける。
2月1回企画「せり(熊本県産)」ぜひご注文ください!
たくさんの笑顔と会話が!!
交流を通じて福祉の現状や取り組みを学びました
商品を間に楽しい交流 |
2月2日さんぼんすぎセンター |
福祉委員会主催の「東都生協ときょうされん東京支部との交流会」が都内2カ所で開催され、延102人の人が参加しました。
2007年1月26日、府中市ふれあい会館では開会あいさつの後、4テーブルに分かれて各共同作業所が製作している商品を当てる「箱の中は何だろうな」ゲームでスタート。
4人の解答者から出る正解や迷解答のたびに大きな拍手が湧きました。ゲームが終わって作業所が作っている商品の説明や試食などをしながら和気あいあいと交流。
会のさなかには、日々の作業で作った商品をテーブルに並べて即席の模擬店が開店し、大きな呼び声や、商品を持ち、参加者の中を歩く売り子さんも出て、楽しいひとときでした。
健康な身体づくり
東京西部保健生協から講師を招き学習
手軽に運動不足を解消 |
健康であり続けるために |
2007年1月19日、くらし委員会主催の「骨密度測定とメタボリックシンドロームについての学習会」が開かれました。講師は東京西部保健生協常務理事の吉岡尚志さんで、参加者は19人。まず超音波で1人ずつ骨密度を測定するところからスタート。
メタボリックシンドロームは腹囲が男85cm・女90cmを超えたら注意が必要とのこと。余分な内臓脂肪は食べる量を減らし、運動すれば減らせるので、1日1万歩を目指して毎日歩き続けることが大切と話されました。
健康な生活を維持するには骨量と筋力に注意すること。転倒予防に効果のある「荒川ころばん体操」が紹介され、全員でビデオを見ながら、体操をしました。
噂の安部さんが食品添加物を語る
「食品の裏側」の著者・安部司さんが講演
添加物を混ぜるだけの |
2006年10月17日、渋谷区立商工会館で、「食品の裏側」の著者である安部司さんを招き、仕入委員会と食と農委員会共催で学習会が開かれました。参加者は252人。
「添加物の神様」といわれる安部さんが、食品添加物とは何か、何のために使われているのか、食品添加物がまん延している現状とそれに対して私たちが何を選んでいけばいいのかを、実験を交えながら警告を込めて話されました。
私たちは、食品を選ぶ基準に「安全・安心」を一番に挙げますが、食品添加物が一向に減らないのは、実際は「安さ、簡単、便利、美しさ、味が濃い」を求めている私たち消費者がいる現状があるから。
この5つの基準で選ぶのであれば「無添加」はありえない。たとえば売れ筋のコンビニのサンドイッチやおにぎり。
裏を返して食品表示を見れば、聞いたことのないような物がたくさん書かれています。その一つひとつが何であるか、その安全性がどうかを知ることよりも、聞いたことがないものが書いてあるときは、「変だな」と思い、買うのをやめればよいのです。
買う場合は、食品添加物が使われていることを「知って」それでも食べるという判断を自らがすればよい。自分で選ぶ力を付けることが大切、というお話でした。
東都生協からは、「設立以来、不必要な添加物を使わない」との原則に基づいて商品の取り扱い基準を定めていることを商品部から説明。「食と農委員会からも食のあり方を見直す食育活動に力を入れていく」との報告がありました。
私たちへの「食の警告」とともに、「賢い消費者になってほしい」というメッセージが込められた講演でした。