すべてのカテゴリ
安全でおいしい水はどうやって
朝霞浄水場(埼玉県)を見学し、水の大切さを学びました
「あそこに見えるのが荒川の取水口です」 |
2007年6月27日、環境委員会主催の「夏休み親子水道ふれあい教室」が、埼玉県にある朝霞浄水場(東京都水道局が管理)で行われました。
参加した大人13人、子ども14人は5段階の浄水法について、実験を見ながら学んだ後、実際に水がきれいになっていく過程を見学しました。
「家の中でいちばん水を使うのはどこでしょう?」「...」「トイレです」という答えにちょっとビックリ。
「汚れた水が飲める水になるまでとても手間がかかることが分かったので、ムダにはできないと思った」という感想が子どもたちから聞かれました。
フェアトレード 〜買うことによる国際協力〜
適正価格で継続的な取引を通じ、途上国の生産者のくらしを支える
講師の話に熱心に耳を傾けていました |
2007年6月14日、渋谷区立商工会館で長坂寿久さん(拓殖大学国際学部教授)を講師に、平和委員会主催でフェアトレード学習会が行われました。
フェアトレードは、途上国の人々が工場や共同組合を作って、自立した民主的運営ができるように支援するNGO運動からはじまりました。
具体的には、環境に配慮し、強制的児童労働などがないように人権に対応し、さらに地域の伝統や資源を活用して継続性のある生産活動ができるように支援して、生産物を公正な値段で買い取って、人々が生活できるようにする活動です。
IFATという国際組織がフェアトレード基準を作り、FLOというラベル認証制度が作られています。
欧州では、コーヒー、紅茶などの食品を中心に貿易量が増えていますが、日本では認知度が低く、取り扱い量も少ないのが現状です。
私たち消費者がフェアトレード商品を活用し、途上国の自立支援、開発協力意識を高めていくことの大切さを学びました。
2007年6月東都生協NO₂測定結果
東都生協組合員によるの二酸化窒素(NO₂)測定活動
東都生協では、2007年5月31日(木)午後6時~6月1日(金)午後6時の24時間、簡易カプセルで二酸化窒素(NO₂)測定を行いました。その結果をご報告します。
東都生協では、組合員が空気中のNO₂測定活動に取り組んでいます。年に2回、同じ場所で測定して空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどを目的としています。
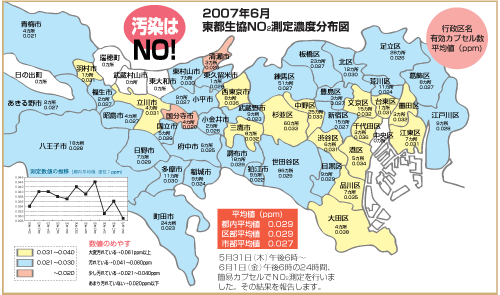
▲地図をクリックするとPDFが開きます。
■二酸化窒素(NO₂)測定概要
測定日時:2007年5月31日(木)午後6時~6月1日(金)午後6時
配付数:885個
回収数:594個
有効カプセル数:566個
回収率:67.1%
※環境省が定めたNO₂の基準値は「0.04〜0.06ppmのゾーン、またはそれ以下であること」とされています。
人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。
東都生協は1988年からNO₂測定に取り組み、測定結果を「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供しています。この連絡会では生協のほか、さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定の積み重ねが大きな運動を支えています。
お問い合わせ:東都生協 組織運営部
TEL 03-5374-4756
(月曜日〜金曜日・午前9時〜午後5時)
東京から平和をアピール
核兵器廃絶と戦争のない平和な世界を目指して
行進をしながら沿道の人に |
2007年5月10日、核兵器廃絶と戦争のない平和な世界を目指して「2007ピースアクション in TOKYO & ピースパレード」が行われ、東都生協をはじめ各生協などの団体が参加しました。
午前中は東京ウイメンズプラザ(渋谷)で「2007ピースアクション in TOKYO」が開催されました。歌手横井久美子さんによるピースコンサートの他、参加団体リレートーク、今年亡くなられた伊藤一長長崎市長への黙祷などが行われました。
東都生協からはグループ「麦藁帽子」による朗読劇や、福永喜美代理事が平和の活動を報告しました。最後に核兵器廃絶に向けたアピール案の朗読が行われ、大きな拍手で採択されました。
午後からは、沿道の人たちに平和のメッセージが入った花の種を配りながらのパレードが行われました。各自思い思いのアピールをしながら参加。暑い中での行進でしたが、終点の宮下公園までの約40分間の道のりを、元気よく歩きました。
核兵器の恐ろしさを改めて認識させられたのと同時に、平和アピールの大切さを痛感したピースアクションでした。
米粉を使って楽しい食卓
機関誌 『東都生協だより』 2007年4月号より
レシピを見ながら講師の手元に注目 |
2007年1月31日、国産の米粉を利用してほしいと、食と農西小委員会主催の「米粉でびっくりクッキング」が、さんぼんすぎセンターで開かれました。
講師は料理インストラクターの吉田文子さん。委員を含む25人が参加していちご大福やクリームスープなど、ふだん使う小麦粉を米粉に替えたりして4種類の料理を作りました。
「米粉がずっと身近になりました。いろいろな料理に使えるのにびっくり」など思いがけない米粉の使い方にびっくりした感想が聞かれました。
東京で平和を大切に守り続ける
世界平和と核兵器廃絶への願い込めた平和募金企画
東都生協も第五福竜丸の |
2007年4月7日新木場駅に11人が集合、まず第五福竜丸展示館前広場で行われている「お花見平和のつどい・2007」に参加。第五福竜丸のエンジンをこの地に移送する運動をした各団体の報告を聞き、展示館内の見学をしました。
建造から60年たった第五福竜丸やさまざまな資料を目の当たりにし、原水爆の惨禍を学びました。
その後東京大空襲・戦災資料センターに移動。米国資料の公開による東京大空襲の実態のNHK番組ビデオを見て、米国が空襲を行った経過を生々しく知ることができました。
説明員の山本唯人さんからは、この戦災資料センターは民間の募金で運営管理されていて、館内に展示されている東京大空襲の資料は市民からの寄贈で集まった貴重なものと説明を受けました。建設のための募金活動には東都生協も協力しました。
次に横網町公園の東京都慰霊堂を見学しました。ここは関東大震災の時に避難した人々が焼死した場所で、震災犠牲者の霊を追悼しています。その後東京大空襲で亡くなられた方も慰霊堂裏の納骨堂に納められました。平和委員の永尾寿孝さんに慰霊堂や東京大空襲の話を聞き、平和を願う一日でした。
オキナワで平和を考える
二度と戦争の悲劇を繰り返さないために
樹木の葉っぱに覆われた |
ガイドの説明に熱心に |
2007年3月27日〜29日、日本生協連主催の沖縄戦跡・基地巡りが開催され、東都生協からは「沖縄を知ろう」コースに4人、「親子で沖縄を学ぶ」コースに1組2人が参加。
1日目は、事前学習として沖縄の生協の方から平和活動・戦争体験談などを聞き、夜は琉球舞踊を見学しながら他生協の人たちと交流しました。
2日目は、戦時中は病院や住民の隠れ場所になった「ガマ(壕)」や「平和祈念資料館」「ひめゆりの塔」などの戦跡を見て回りました。
3日目は、嘉手納町の83%を占める嘉手納基地を「安保の見える丘」から見学しました。
戦争の悲惨さを知るだけでなく、戦争の起こった歴史的背景を学び、二度と戦争の悲劇を繰り返さないために私たちがどうすればいいのかを深く考える機会になりました。
親子で考える「地球の抱える問題」
開発途上国の現状を知り、私たちにできることを考える
ボランティア隊員から |
外国の学校の制服を展示 |
2007年3月29日、平和委員会企画で「JICA地球ひろば見学会」が行われました。
参加者25人は渋谷区にあるJICA(ジャイカ:独立行政法人 国際協力機構)の施設「地球ひろば」を、4つのグループに分かれて見学。
国際ボランティアに参加した人の体験談を聞いたり、貧困に苦しんでいる国の現状の説明などを聞きました。
春休み中だったこともあって子どもも多数参加。「世界の中で、学校に行きたくても行けない子がいるなんてかわいそう」という参加した子どもの感想が印象的でした。
ヒロシマで平和への思いを新たに
親子で平和について考える平和募金企画
渡邉美代子さんより |
春休みに親子で平和について考えてみようと、2007年3月26日〜27日の1泊2日で「2007ピースアクション『親子ヒロシマの旅』」が行われ、7組14人の親子が参加しました。
初日は原爆ドームや、平和記念公園にある広島平和記念資料館・韓国人原爆犠牲者慰霊碑などを平和ガイドの説明を受けながら見学。原爆の子の像へは組合員から寄せられた千羽鶴を供えました。
夜は被爆された方から体験談を伺い、地獄を生き延びた方々の、平和を祈る気持ちの強さを肌で感じた交流会となりました。
翌日は広島市の南にある比治山の陸軍墓地などを訪れました。山頂にある(財)放射線影響研究所の施設を外から眺めた際、「元はアメリカが設置した施設。原爆病の調査が目的だったため、被爆者の治療には一切関わらなかった」というガイドの言葉が非常に印象的でした。
被爆の実相を学び受け継いでいくことの大切さを実感した旅でした。
あなた! 便利なもの使い続けて大丈夫?
防虫剤や洗剤、医薬品などの化学物質との付き合い方
講師の環境カウンセラー |
2007年3月13日、環境委員会主催で化学物質との付き合い方に関する学習会が開かれ、30人が参加。
私たちは防虫剤や洗剤、医薬品などの化学物質によって、便利に暮らすことができています。
「化学物質を全て否定することは難しいので、情報を正しく理解し、メリット・デメリットは何なのかを考えることが大切」とのこと。
参加者からは「化学物質と上手に付き合うためにも選ぶ目を持ちたい。今日はその第一歩になった」との感想がありました。











