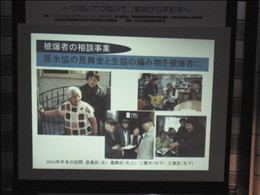すべてのカテゴリ
原材料と製造にこだわるユニオンソース㈱を視察訪問
素材の良さを生かし、不要な添加物を一切排除した安全・安心な商品作りを確認
ソースの歴史や独自の製法を解説 |
窓から見える自家挽き香辛料室 |
おいしさを守るこだわりの製法図 |
ユニオンソース㈱は、ソース・ケチャップ・マヨネーズ・ドレッシングなどのメーカーで、2012年から、本社を日光工場に移しています。
工場は食品工場にふさわしく、清潔な環境です。同社が扱う香辛料(セージ、タイム、ローレル、シナモン、黒こしょう、ナツメグ、クローブ)の説明を受け、その種類の多さと、試行錯誤をしながら配合にこだわっていることに驚きました。
香辛料の粉砕室では、ソースの個性に合わせて調合している様子や、製造直前に自家挽きしていることが確認できました。同社で製造する「東都無着色ソース」は、でんぷん、増粘剤を一切使用していません。またカラメル色素などの着色料も使用しないので、トマトを中心とした野菜・果物本来の色が出ています。
マヨネーズは安全な産直たまごを全卵使用し、ケチャップの原材料も国産完熟トマト100%。マヨネーズ、ケチャップとも化学調味料不使用、非遺伝子組換え原料を追求した、添加物のない、安全・安心な商品です。
メーカーが組合員の声に応え、これだけ原材料にこだわり、製造にもこだわっていることに対し、東都生協の組合員として、買い支え、伝えていくことが重要な課題だと感じました。
2014年度も組合員が参加した商品づくりを推進
全ての組合員に商品活動への参加・参画を呼び掛けています
2014年度も、東都生協の組合員による「新商品おしゃべり会」「アレルギー対応について学ぶ会」と、組合員や役職員による「商品委員会」がスタートしました。
「新商品おしゃべり会」は、毎月、新商品や開発途中の商品について組合員が原材料や製造方法を確かめて試食し、包材や調理法までを評価して改善意見などを出し合い、商品委員会につなげる活動です。今年度は、江戸川会場、大田会場、調布会場、町田会場、城西会場として5つの配送センターを拠点に開催しています。
「アレルギー対応について学ぶ会」は、本人または家族に食物アレルギーのある組合員が気軽に集い、情報交換や食物アレルギーに考慮した商品について意見交換を行う場。立川会場(多摩消費生活センター)と飯田橋会場(東京都消費生活総合センター)で隔月開催をしています。
「商品委員会」は、商品事業が組合員の声に応え、基本方針・政策に沿って行われているかを評価・提言する役割を担います。毎月の委員会では、業務組織で提案した商品について、新商品おしゃべり会・商品モニターなどから届いた声を考慮しながら確認します。
商品委員会委員は、地域での商品活動を推進し、社会情勢の変化や最新の科学的知見などを受け、見直し・再評価が必要な東都生協の商品の考え方・基準について提言も行います。
この他に組合員なら誰でも参加できる「視察訪問企画」があります。組合員が自ら取引産地・メーカーを訪問し、商品について安全・安心を確かめ、産直の取り組みなどについて理解を深めます。視察訪問企画は、組合員に配付している組合員活動情報紙「ワォ」で募集します。参加者は視察後、良かったこと、気になったことなどの報告書を提出し、商品委員会で確認します。
さらに「商品モニター」「ひとこえ生協」「おすすめコメント」からの意見も商品事業に生かしています。組合員の皆さまも、ぜひできる活動ご参加ください。
ラフターヨガ(笑いヨガ)で元気になろう!
東都人材バンク講師によるラフターヨガ(笑いヨガ)&ぷちカフェ♪を開催
徐々に「大笑い」できるように |
日本に紹介されてまだ7~8年のラフターヨガは、普通のヨガと違って、老若男女、誰でもどこでもできるヨガです。
おとなになるとなかなか自分から「大笑い」をする機会もなくなるので、最初はみんな、照れながら笑っていましたが、坂戸先生の指導の下、本当に「大笑い」ができるようになっていきました。
ハードな動きではないのですが、体も温まり、凝っていた体も柔らかくなり、楽しくなる「ラフターヨガ」、皆さんにもお勧めです。
雨の収穫体験もまた楽し!?
産直産地・三浦半島EM研究会を訪問。農薬や化学肥料をできるだけ使用しない栽培の様子を見学。
雨に見舞われながらも収穫 |
EM栽培についての説明をうける組合員 |
温暖な三浦半島とはうらはらな冷たい雨が降る中、「イイジマ農園」のビニールハウスでEM栽培についての説明を聞きました。
「EM」とは「Effective(有用な)・Microorganisms(微生物群)」の略語です。同研究会は、EMと米ぬかなどの有機物を使い、農薬・化学肥料を減らした野菜作りを実践しています。
お目当てのキャベツ・にんじん・大根は雑草と共生しながら、健康な土壌ですくすくと育っていました。
にんじん収穫のころから激しい雨に見舞われてしまいましたが、ビニールハウス内で雨宿りする人、雨にもめげず大根を抜く人、雨の農園を美しいと眺める人...。それぞれに見学と収穫体験を楽しみました。
試食品はあっという間に空!
エム・シーシー食品㈱学習交流会
講師の岩本さんと参加者 |
ズラリと並んだ試食品 |
この日は、パスタ3種類、ピザ3種類、カレー2種類、ジェノベーゼソースを使ったスープ1種類を試食。「全部温かい状態で食べてほしい」という岩本さんの心遣いから、スープができてからパスタをゆで、ソースを温め、ピザを焼く、という手順で調理を行いました。
「試食品の量が少々多いのでは」との声もありましたが、あっという間にお皿は空...。「ソースはどれも家庭ではなかなか出せない味で、おいしかった」「グリーンカレーは辛すぎるかと思ったが、クリーミーでおいしかった」など、参加者に大好評の試食会になりました。
子どもたちに安全な食を届けるために
JAやさと交流訪問
工場を見学 |
畑の生き物に子どもたちは大喜び |
有機農法でふかふかの畑に感動して「供給で届く野菜を見るたびに生産者の皆さんを思い出します」「子どもは東都生協の産直野菜で育てたい!」などの声も聞かれました。
また、子どもたちは、てんとう虫や気の早いカエルを見つけて大喜びで、たくさんの生物が暮らす畑を実感したようです。
「ふたば」では「子どもたちの安全な食」をテーマに、今後も学習会・産地訪問を通じて子どもたちと食について勉強していきたいと思っています。
東都生協の食の未来づくり運動の姿勢が次の世代へしっかり受け継がれていくことを、肌で感じた産地交流訪問でした。
(農)大矢野有機農産物供給センターを視察訪問
―視察訪問 第5弾―
「不知火」の品種や病気を説明 |
センター独自のボカシ肥料 |
1日目は、東都生協組合員が生産者支援のために出資する「土づくり基金」を利用した、「ボカシ肥料工場」を視察。同産地では、有機発酵肥料の「ボカシ肥料」を自家製造しています。
ボカシ肥料の材料の配合は作物によってさまざまですが、魚粉・米ぬかなどを3カ月切り返しをして混ぜ、年3回、共同作業で同産地の必要量・約140tを自給しています。
次に視察したのは、かんきつと葉付き玉ねぎ畑。同産地・鬼塚理事長からは、栽培理念・基準のほか、かんきつ選果時に行う糖酸度検査などについて説明を受けました。
2日目は、せり・しょうが貯蔵庫、にんじん畑を視察。地域が広いため出荷場まで40分以上もかかる所があったり、イノシシによる被害があるなど、生産上のご苦労も伺いました。
生産者の皆さまは真剣に作物と向き合い、品質向上や安定供給に努めているのに、気候の影響に左右され、規格外で出荷不可となる作物が想像以上に多いことにも、参加者は驚かされました。
お話を聞き、参加者から「規格外商品を東都生協で取り扱ったら?」という意見も出ましたが、生産者からは見栄えが悪いだけでクレームになることもあるので、扱いが難しいとのことでした。
さらに、生産者の高齢化で後継者不足問題を抱えているという現実もあります。参加者にとって、日々努力している生産者の思いを忘れず、今後も感謝をもって食べていきたいと感じられた視察訪問となりました。
2014ピースアクション in TOKYO&ピースパレード報告
核兵器の廃絶と戦争のない平和な世界を目指して、みんなで平和な東京を築こう
「語り継ぐ」で朗読をする |
(一社)東友会より東都生協の膝掛け贈呈 |
先頭の街宣車より渡貫理事がマイクで |
ピースパレードの様子 |
当日は7生協と2団体から244人の参加があり、東都生協からは組合員・役職員など23人が参加しました。
オーボエ演奏によるオープニング・コンサートからはじまり、「みんなで築く平和な東京」を語り継ぐでは、東都生協を含め3生協が朗読を行いました。
参加団体リレートークでは大学生協から「自分たちは戦争体験を直接聞くことができる最後の世代」「大学で学ぶためには平和でなければいけない」と、平和への願いを込めた活動が報告されました。
(一社)東友会からは、東都生協から同団体への膝掛け贈呈について紹介しました。55周年事業として被爆者と被爆二世の実態調査を行っていることが報告されました。
広島市長・長崎市長からもメッセージをいただき、核兵器廃絶への決意を新たにしました。
その後、神宮通り公園までピースパレードを行いました。昨年は雨天のためパレードは中止となりましたが、今年は晴天に恵まれ沿道の人たちに「花の種」を配りながら平和をアピールしました。
もしもの時に慌てないために
お葬式と終活について事前に学び、準備と心構えを
もしもの時に慌てないために役立つ知恵を |
社会福祉法人東京福祉会と東都生協保障・生活文化事業部の職員を講師に、にじえ葬の仕組み、エンディングノートの書き方、相続税など、もしもの時に役立つ知恵を学びました。
東都生協の葬祭事業「にじえ」には、「悲しみを乗り越え希望の虹に出会うまでお手伝いする」という思いが込められています。
葬儀経験者からの経験談「急なことでよく分からないうちに終わった」「予算をオーバーした」「スタッフから心付けを要求された」「地元の葬儀社で細かい気配りがあった」なども参考になり、事前の学びと心構えの大切さを実感した学習会でした。
雪の中から出てきたものは......
(農)茨城県西産直センターを訪問
おいしい野菜を持って記念撮影 |
貴重なにんじんの品種「WN101」 |
現地では一面の真っ白な雪と、ピリリと肌をさすような風に迎えられました。
当日の収穫は、霜が降りたこの時期一番おいしい葉物野菜(ター菜、ほうれん草)と、この時期にしか味わえない貴重な品種「WN101」のにんじん。
夏の暑さでにんじんの芽が育たず種をまき直したり、この寒さで収穫が遅れたりと、自然相手の仕事は本当に大変です。私たちの食卓に食べ物が届けられることに感謝しなくてはと痛感しました。
参加者は「前日から私たちのために雪かきをして農場の整備をしてくれた産地の皆さん、本当にありがとう。今日の出会いを大切にまた会いましょう」とバスの中から手を振り、筑波山を後にしました。