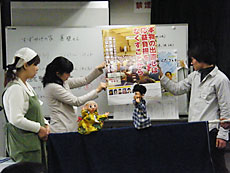福祉
理解し合うことが大切 ~きょうされんとの交流会~
共同作業所との交流を通して福祉政策の現状を知り、理解を深める
東都生協・池田組合員常任理事より |
きょうされん東京支部・財政事業委員 |
作業所のリレートーク |
会場では共同作業所商品も販売 |
東都人材バンクの登録講師 |
みんなでベリーダンス |
2009年12月10日、共同作業所の方たちとの交流を通して福祉政策の現状を知り、理解を深めることを目的に「きょうされんと東都生協との交流会」(小平市 ルネこだいら)を開催しました。きょうされんより9作業所32人、東都生協より38人が参加しました。
参加した9つの作業所から、事業・活動の様子をリレートークで紹介。東都生協の商品案内をセットしている作業所利用者からは、組合員の手元に届くチラシに乱れたものがないようにと、一生懸命セットしている普段の作業の様子が語られました。
参加した組合員からは、「作業所の方々が、東都生協のチラシがこんな一生懸命にセットされているなんて知らなかった。これからは、もっと大切に商品案内を見ます」などの声が出されました。
この他に、きょうされんとの協同事業としてリユースびんの洗浄を行う「リサイクル洗びんセンター」(昭島市)や、社会福祉法人ときわ会との協同事業で米ぬか石けんを製造する「福祉工場エバーグリーン」などからの報告もありました。
また、きょうされん東京支部より、障害者自立支援法の廃止と新法制定を求める「きょうされん第33次国会請願署名」の協力呼び掛けがあり、当日会場で20筆集まりました。
「声の商品案内」を届け続けて20年
声の商品案内を届ける「リーディングサービス」利用者との懇談会
「やまびこの会」に感謝状を贈呈 |
オペラ歌手の天野さんが歌声を披露 |
昼食を食べながら楽しく交流 |
参加者全員で記念撮影 |
参加したのはサービス利用者と付き添いのガイドヘルパー(※)、そして商品案内の読み上げ、録音、発送作業を永年ボランティアで担っている「視覚障害者と協同するボランティアの会(通称「やまびこの会」)」のメンバーら57人と盲導犬2頭。
まず東都生協の中村副理事長が「やまびこの会」の活動に敬意を表して、感謝状を贈呈しました。
「やまびこの会」の中には、発足当時から20年間継続して活動しているメンバーも。東都生協のリーディングサービスを長い間支えていただいています。
続いて、ご自身がリーディングサービス利用者でオペラ歌手の天野亨さんのミニコンサート。天野さんの歌声に一同引き込まれ、聞き入ります。コンサートの締めくくりは天野さんの歌唱指導の下、参加者全員で「ふるさと」を合唱。
昼食をはさんで、懇談を行いました。
2009年から、CDによる声の商品案内「デイジー」の取り組みも開始した東都生協のリーディングサービス。利用者からは「リーディングサービスをはじめてから、注文数が増えた」「CDになってから、今まで以上に便利になった」などの意見が出されました。
全国の生協の中でも、草分け的な活動を続けてきた東都生協のリーディングサービス。利用者にとってなくてはならない活動であることを再認識できた懇談会となりました。
(※)ガイドヘルパー
視覚障害者の外出の補助を行う、移動介護従事者
体験しながら楽しく交流
福祉を取り巻く現状や共同作業所への理解を深める取り組み
これからも交流会を大切にしたい |
いつも作業所で作製している押し花はがき、藍染タオル、ビーズアクセサリーなどの作り方を教えてもらいながらの交流は、各テーブルで楽しく話が弾み、笑顔いっぱいの時間になりました。
その後は、お茶とクッキーで作品のできばえや作業所の生活などを話題に歓談、みなさんの作品の販売もあり、盛りだくさんの交流会になりました。
参加した組合員からは、「作業体験がよかった」「子どもと一緒に参加したいので、ぜひ夏休みに開催してほしい」などの声が寄せられ、きょうされん団体からの参加者からは、「もっと交流したかった」ととても名残惜しそうでした。
皆さんの善意でサイクロンシェルターが完成しました
「バングラデシュ・ミャンマーサイクロン募金」のご報告
svaの木村万里子さんより |
SVAの関尚士事務局長に |
バングラデシュ |
孤児院の前で |
2008年5月に東都生協で取り組んだ「バングラデシュ・ミャンマー(ビルマ)サイクロン募金」に寄せられた募金額は1,480万円超に達し、バングラデシュ、ミャンマーのそれぞれ復興支援・緊急支援に充てられました。
2009年1月30日、今回の募金を寄託した社団法人シャンティ国際ボランティア会(SVA)の緊急支援担当・木村万里子さんが東都生協本部を来訪し、当組合・竺原(じくはら)常務理事に対して東都生協「バングラデシュ被災地復興支援活動完了報告」を行い、13ページにわたる「報告書」が手渡されました。
ご協力いただいた皆さまに感謝を申し上げますとともに、詳細をご報告いたします。
サイクロン募金報告
組合員の募金総額1,489万円余りが
被災者支援に役立てられてきました
2008年5月3日夜からミャンマー(ビルマ)南部を襲ったサイクロンは、死者22,980人・行方不明42,100人(2008年5月7日、国営テレビ=時事)、約100万人が家を失う(国連担当官=毎日)大惨事をもたらしました。
その前年2007年11月15日にバングラデシュ南部を襲ったサイクロンでは、約3,400人が命を落とし、約150万世帯の家を奪いました。半年を経た今も、人々の心に傷を残しています。
東都生協は2008年5月12日(月)から全組合員に被災状況を伝え緊急募金を呼び掛けるチラシを配付しました。緊急募金チラシでは、東都生協組合員に以下の内容をお知らせしました。
- 東都生協は、社団法人 シャンティ国際ボランティア会(SVA、本部・新宿区)と提携し、お預かりする募金は、現地の住民組織、非政府組織などの協力を得て、直接、被災地の救援・復興に役立てる。
- バングラデシュでは子どもたちのための教室やサイクロン避難用施設建設のために。ミャンマー(ビルマ)では現地組織との関係を確保した上で、被災住民本位の支援を構築するために募金を活用する。
- 2つの被災地への募金の配分は生協とSVAとで協議して行う
短期間に14,892,662円の募金が寄せられました
2008年7月12日、東都生協・宗村弘子副理事長は新宿区大京町の同会本部を訪れ、募金全額を同会に贈呈。両団体で協議した結果、
バングラデシュ・サイクロン被災者復興支援として595万5,625円、ミャンマー(ビルマ)・サイクロン被災者緊急支援として893万3,417円をそれぞれ配分することを確認しました。
以下、すでに完了したバングラデシュ・サイクロン被災者復興支援事業と、支援継続中のミャンマー(ビルマ)被災者緊急支援の中間状況について、報告します。
バングラデシュで鉄筋2階建てのサイクロンシェルター4棟が完成
東都生協・組合員からの募金595万円余が地域を活性化
2009年1月30日、同会の緊急支援担当・木村万里子さんが東都生協を訪問し、東都生協・竺原俊明(じくはらとしあき)常務理事に「バングラデシュ・サイクロン『シドル』被災地復興支援活動活動完了報告書」を手渡しました。
バングラデシュでは、今後おそらく何度も再来するであろうサイクロンの被害に備え、本格的なシェルターの建設に募金全額が役立てられました。サイクロンや津波が発生した場合は、近隣住民は、鉄筋コンクリート2階建てのシェルターの2階に避難することができるようになりました。2階には牛などの家畜も避難できます。
シェルターは、同会の支援でこれまでに4棟建設されました。このうちの1棟は、バングラデシュ南部のボルグナサダル郡に位置し、ベンガル湾を河口とするブリシャワル川沿いの地域であるケオラブニア地区に、東都生協・東京南部生協と他の日本の3団体の計5団体からの募金で建設されました。
シェルターの日常運営は、男女の地域住民で構成する運営委員会によってなされ、地域の集会所・コミュニティセンターとして機能しています。

ミャンマー(ビルマ)
組合員からお寄せいただいた募金は、被災3日後から緊急物資を直接届ける活動の原資として役立ちました
一方、ミャンマー(ビルマ)でのサイクロン被害に対しては、直後に各国からの支援協力が表明されたのに対して、同国側がこうした支援を警戒して、一時は膠着(こうちゃく)状態となり、その間にも多数の犠牲者が生じるという事態となりました。
同会はかねてからタイに現地事務所を設けていたこともあり、被災直後からミャンマー(ビルマ)国内のボランティア諸団体と連絡を取り、独自のルートを開発して、5月6日から水(ボトル入り)、浄水剤、米、毛布、薬(下痢止めなど)のほか、小屋を建てるためのブルーシートなどの建材を被災者に直接届けるという活動を精力的に展開し、5月末までに42,000人に届けることができました。
その後も活動は拡大して展開し、7月までに87か村で配付活動を行い、延べ182,000人に救援物資が届けられました。7月からは稲作農家への「種籾」の配付や、共同で利用するトラクターの支援、漁村への船や魚網を届けました。
①食料品(飲料水、米、豆、じゃがいも、玉ねぎ、油):46,400人分②衣服と靴:11,600人分
③家屋修繕や避難小屋の建設資材:8,665世帯分
④遺体処理、塩害環境整備資材:43か村分
⑤救急衛生セット:26,900セット
⑥トラクター:16台(約80家族分)
⑦移動医療チームの展開費用:毎週平均10チーム
⑧離散家族支援:103人の交通費など
農漁村の生活再建と孤児院建設、保育施設
これまでにサイクロン被災の子どもたちを応援する復興支援活動として、孤児院2棟が建設され、男児70人、女児31人が利用しています。さらに保育施設の修繕・建て直しに取り組み、これまで34棟が再建され、女児421人、男児440人が利用しています。

同会では、これまで各国の子どもたちに絵本を贈るボランティア活動を展開してきました。日本の絵本の日本語の箇所を当該国の言葉に直したシールを貼り、現地の子どもたちに読んでもらうという取り組みです。国内の絵本作家や出版者の了解を得て、ボランティアが2,000円の実費を負担しながら、現地の言葉に翻訳したシール貼りを行います。(詳細はここをクリックしてください)
ミャンマー(ビルマ)の子どもたちに絵本を贈るボランティアを、同会は募集しています。東都生協の組合員は実費2,000円が昨年の募金から拠出されます。
【参考】
社団法人シャンティ国際ボランティア会・ミャンマー支援活動(外部サイトにリンクします)
【お問い合わせ先】
社団法人 シャンティ国際ボランティア会 東京事務所 03-5360-1233(緊急救援担当:白鳥、薄木)
東都生協 03-6859-4680
これって「障害者税」!?
障害福祉についての制度拡充を求めるきょうされんの国会請願署名・募金運動について学習
署名や募金の意義・必要性 |
講師の磯部光孝さんの |
2009年1月9日渋谷区商工会館にて、きょうされん第32次国会請願署名と募金運動について学習会を開催しました。講師は、きょうされん東京支部副会長の磯部光孝さん。
ここ数年、社会保障関連予算は毎年度2,200億円ずつ減額されています。こうした中で 2006年に施行された障害者自立支援法は「応益負担」という形で障害のある人々に新たな負担を強いるもので、利用料の滞納や、利用者の施設からの退所などを生み、多くの事業所も運営面で困難に直面しているというのが現状です。
きょうされんが、障害者権利条約の水準に沿った国内法の見直しを求め、障害のある人が地域で安心してくらしていくことができるように運動していることを、この学習会で学びました。
参加者は、少しでも手伝えるように、署名と募金の協力をし、国へは続けて訴えていく必要を実感しました。
親子になること
親と子のあり方を学ぶ子育て支援学習会
当日は男性の参加者もいました |
2008年11月4日、東都生協は東京都消費生活センターで子育て支援学習会を開催し、25人の組合員が参加しました。「親子になること」をテーマに評論家・芹沢俊介さんを迎え、親と子のあり方について学びました。
子どもときちんと向き合い「おかあさん?」「なあに?」こんな会話を続けることが第一歩とのこと。
参加者はそれぞれに子どもとの関係を思い起こし、これからの指針を見つけ出そうと「親子のきずなの大切さ」、子どもの「受け止められたい欲求」など講師の言葉を懸命に聴いていました。
「このような機会をもっと多くの方々に知ってほしい」「子育てがより楽しいものになる気がします」と参加者から感想がありました。
食物アレルギーと保育
機関誌 『東都生協だより』 2008年11月号より
じっくりと聞きました |
2008年9月11日、保育ママ委員会は、アレルギーのある子どもも安全に預かることができるようにと、保育ママを対象に「アレルギーについての学習会」を開きました。
講師の東都生協アレルギー相談室の武内澄子さんからの「食物アレルギーって何?」にはじまり、症状やアレルゲン、新しいタイプの食物アレルギーや表示の見方、代替食についてなど、丁寧な説明がありました。
保育に当たっての注意では、保育時の発症事例やアレルギー事故防止対策についての話があり、26 人の参加者は真剣に聞き入りました。
「アレルギーの子どもを預かったときの室内の掃除はどうしたらいちばん効率が良い?」などの質問も出されました。
「講師の知識の豊富さに感動」「事例を挙げて説明してくださったのでとても分かりやすく、良かった」「アレルギーの危険さ、深さについて再認識しました」などの感想が聞かれ、有意義な学習会となりました。
心を開く聴き方、話し方
日本メンタルヘルス協会・丸山弥生さんを講師に学習
講師の話に興味津々 |
活発に意見交換 |
2008年3月6日、さんぼんすぎセンターで、東都生協くらしの助け合いの会「ほっとはんど」が学習&懇談会「心を開く聴き方、話し方」を開催しました。講師は日本メンタルヘルス協会の丸山弥生さん。
60人の参加者で会場はいっぱい。心理テストで自分の「親心、大人心、子ども心」度を知り、なるほどと感心。
「本当のプラス思考とは、プラスもマイナスもきちんと見て、どちらを選択したら自分も周りの人も幸せかと考えること」「差し出された手をありがとうと受け止めることが謙虚さです」などの話を実例たっぷりに聞き、笑ったり頷いたり。3時間があっという間でした。
ステキな商品はいかがでしょう?
共同作業所の方々との交流を通して福祉政策の現状への理解を深めました
演じられた人形劇は |
2008年2月29日、東都生協はさんぼんすぎセンターにてきょうされん東京支部との交流会を開催しました。8 団体と組合員合計40人が参加。
この交流会は、共同作業所の方々との交流を通して福祉政策の現状への理解を深めることを目的に、毎年開催しています。
「年に一度のこの交流会を楽しみにしていました」というあいさつからスタート。お弁当を食べながらの交流が行われました。
「こんな製品が欲しいという要望はありますか?」「販路拡大のためのアイディアにインターネットを使ってみたい」など、積極的な活動に結び付けるための情報交換が活発に行われました。
それぞれの作業所で作られたクッキー、しおり、おもちゃ、手芸品など自慢の品々が会場いっぱいに並び、笑顔がいっぱいの販売が始まると、作業所のメンバーは手に手に商品を持って売り込みを開始。
ビデオを使ったきょうされんPRタイムでは「味は保証済みです!!」と胸をはってアピール。人形劇や署名の呼び掛けなども行われ、にぎやかな一日となりました。
自分を知って子育てに生かす 福祉委員会連続講座
子育ては、親も子も自己信頼を築くための道のり
同じ立場の人たちと意見交流をしました |
「自分の気持ちに気付いて子育てをラクにしよう!」をテーマに、福祉委員会では、講師にフリーライターの箱崎幸恵さんを迎え、2007年10月9日と11月13日に連続講座を開催し、子育て真っ最中のお母さんが延べ27人参加しました。
まず、幼い頃の自分を思い出し、紙皿にその頃の感情を一番示す顔の表情をクレヨンやマジックで描きました。笑顔、泣いている顔、不安な顔とさまざまな顔が描かれ、そのころの気持ちを参加者一人ひとりが発表し合いました。
感情は自分の行動の動機付けになり、自分の行動パターンを知ることにより、客観的に自分を見つめ直すことになることを学び、それによって自分の陥りやすい感情と行動パターンについて書き出しました。
子育て中はいろいろな気持ちが湧いてきます。子どもへの愛しさや喜びだけではなく、不安やイライラも。そんなとき、子どもを通して自分の子どもの頃と向き合うことになり、親自身も自分が大切な存在であると気付き、落ち着きを取り戻します。子育ては、親も子も自己信頼を築くための道のりであることを学びました。
参加者同士が思いを分かち合ったことで、さらに元気が出て、あらためて子どもと向き合うことができるようになった講座でした。