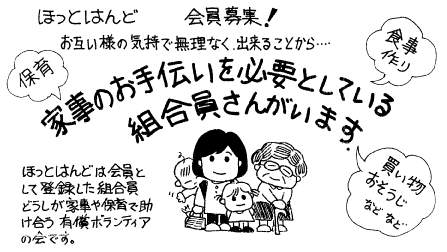福祉
東都生協の活動の1つです
組合員が共同作業所でボランティアを体験
朝のミーティングは |
手際よく袋詰め |
2007年8月21日、きょうされん福祉作業所のボランティア体験が三鷹ひまわり第三作業所で行われました。
参加者は朝礼の後、作業所のメンバーと一緒にクッキーやケーキづくりを体験しました。
この日は納期が迫っていて、厨房 では売れ筋のクラッカーとクッキーが次から次へと鉄板に並べられていました。
同時進行でオレンジケーキの準備も。
「学校の卒論のテーマに東都生協を取り上げたんです。生協の活動の広がりを体験したくて今回は参加しました」という参加者の1人はお 母さんが組合員だという「東都生協第 2世代」。
クッキーの焼き上がる香りのする中で、黙々と仕事をするメンバーと一緒に袋詰めをしながら、作業所の活動を知る良い体験になりました。
保育ママの活動が始まります
お子さんを保育する組合員同士の助け合いの活動
子どもの安全が第一 |
作って遊べる折り紙講習 |
「2007年度保育ママ研修・登録会」は2月から3月にかけて3カ所で開催され、2007年度の保育ママに139人が登録しました。
さんぼんすぎセンターでは2007年2月27日に開催。保育ママ委員会から、保育ママ制度は組合員同士の助け合い活動であることや、保育中の注意などの説明がありました。
今年度は研修に重点をおき応急手当の実習など、今後の保育ママの活動に役立つことを行いました。
交流会では「泣く子の対応」をテーマに意見交換を行いました。
「だっこして外の景色を見せる」などの体験談が出され「保育ママも、託すママも時間と心に余裕を持つことが大事」という言葉にみんな納得でした。
ありがとうの心で助け合い
組合員相互の自主的な家事援助活動
会員登録は6ケタコードで |
「東都生協くらしの助け合いの会 ほっとはんど」説明会が2007年2月14日に多摩消費生活センターで、2月26日は文京シビックセンターで開催され、会員12人と未会員10人が参加しました。
組合員同士の助け合いの会であること、有償の家事援助であることの説明の後、懇談に移りました。
「初めて活動に入った時はこれでいいのかと不安に思うこともあったが、大変喜んでいただき、よかった」「○曜日の午前とか定期的な活動もあるが、お互いの都合で次はいつとその都度決めて活動している」などの体験談、保育園の送り迎えが楽しいとの話、70歳で保育や家事援助をしている会員の話も披露され、主催者から「お互いさまの気持ちで、できるときにできることをやってみませんか」との呼び掛けがありました。
参加者からは「経験談を伺い、不安が解消されました」「援助できることがあれば、時間の合うところで参加したい」などの声がありほっとはんどの活動を知らせ、広げる機会となりました。
たくさんの笑顔と会話が!!
交流を通じて福祉の現状や取り組みを学びました
商品を間に楽しい交流 |
2月2日さんぼんすぎセンター |
福祉委員会主催の「東都生協ときょうされん東京支部との交流会」が都内2カ所で開催され、延102人の人が参加しました。
2007年1月26日、府中市ふれあい会館では開会あいさつの後、4テーブルに分かれて各共同作業所が製作している商品を当てる「箱の中は何だろうな」ゲームでスタート。
4人の解答者から出る正解や迷解答のたびに大きな拍手が湧きました。ゲームが終わって作業所が作っている商品の説明や試食などをしながら和気あいあいと交流。
会のさなかには、日々の作業で作った商品をテーブルに並べて即席の模擬店が開店し、大きな呼び声や、商品を持ち、参加者の中を歩く売り子さんも出て、楽しいひとときでした。
「セモラ」は自立の強い味方
米ぬか100%の台所用石けん「セモラ」を製造する福祉工場エバーグリーンを見学
「セモラは、 |
メンバー全員、どの工程も |
2006年12月6日、福祉委員会主催で福祉工場エバーグリーンを見学しました。参加者はおとな6人、子ども1人。
エバーグリーンでは、精神障害がある方々への就労支援としてねり状米ぬか石けん「セモラ」を製造しています。
この日は前日までに仕込んだ石けんの充填作業日でした。できたての「セモラ」はまるでみそのような色と柔らかさで釜からにゅるにゅると出てきます。
それを工場のメンバーが、容器に1つ分ずつ入れて、計量、押して成形、ナンバリング、包装を行います。
「セモラは、よく泡立てて使ってください」と小さな工場ですが、一定時間ごとに作業者全員の手をアルコール消毒するなど、食品工場の品質管理を取り入れています。
また、仕込みごとにサンプルを保管し、組合員から品質に関するお申し出があった際は、即座に状況を確認できるようにしています。容器は焼却できる素材を使って環境に配慮しています。
メンバー一人ひとりは、障害を抱えながらも地域で自立して生活することを目指しています。「セモラ」を通しての東都生協組合員との交流は、とても励みになるとのことでした。
参加者からは、よく泡立てて使うとより洗浄力が出ることを再認識した、という声が多く聞かれました。
自分の気持ちに気付こう
子どもの虐待防止活動を考えるネットワーク事務局長の箱崎幸恵氏を講師に学習会
「そのときの自分の気持ちは?」 |
自分の気持ちに気付くには、 |
2006年11月10日、東都生協の福祉委員会が主催し、子育て支援企画「しつけ? 虐待? そのときの自分の気持ちに気付こう!」をさんぼんすぎセンターで開催しました。東都生協の組合員14人が参加。
講師は児童虐待問題のフリーランス・ライター、子どもの虐待防止活動を考えるネットワーク事務局長の箱崎幸恵さんです。
なぜ虐待をしてしまうのか? しつけと虐待はどう違うのか? をテーマに話が進みます。
参加者がそれぞれ「そのときの自分の気持ち」を紙に書いて発表し、それぞれの思いを分かち合い、言葉にして心をラクにしていくという参加型の学習会でした。「自分を愛するには、セルフ・エスティーム(自己信頼)を築くことが大事であり、人は自分が信頼されていると感じるとき、他者を信頼でき、信頼は連鎖する。暴力の連鎖を断ち、信頼の連鎖をつくりましょう」と結びました。
交流会では箱崎さんを囲んで悩みを話しながら、毎日の生活で言葉のキャッチボールをすることの大切さを実感しました。
子育て、支援しま〜す
機関誌 『東都生協だより』 2006年9月号より
私の好きなものを |
音楽に合わせて |
親子のスキンシップと母親同士の情報交換を目的とした福祉委員会主催の「やってみよう! 親子ヨガとおやつ作り」がさんぼんすぎセンターで2006年7月31日に開かれました。
この企画には、抽選で選ばれた組合員13組が参加。講師は東都人材バンクの根橋明子さん。ゆったりと音楽に合わせて、猫のポーズのおかあさんの背中に乗ったり、足の間をくぐったりと親子の息もぴったり。すっかりリラックスしました。
後半は調理室で子どもたちがおやつ作り。コップにアイスクリームを入れて、バナナ、グミなどをトッピングしてパフェの出来上がり。「保育があったので、1歳児を預け、上の子と参加できて楽しかった」など、親子で楽しんだひとときでした。
情勢学習会 〜できることから始めてみませんか?〜
機関誌 『東都生協だより』 2006年8月号より
|
東都生協は2006年6月1日、日本生協連の松村陽子さん講師に招き、福祉活動に関する学習会を開催しました。組合員9人が参加しました。
松村さんはまず、助け合いの会の活動が社会福祉などへ移行し、事業化されてきた現状が話されました。
福祉を巡る状況の変化の中で、地域の中でのくらしの助け合いが不可欠になっており、生協でできる福祉・助け合い活動・子育て支援を、ますます発展させていくためにどうしたらいいかを、さまざまな生協の取り組みを事例に出しながら話されました。
後半は、「ふくしdeまちづくり」というテーマで、ワークショップを行いました。
自分が望むまちの将来像をみんなで出し合い、そうなるためにどうしたらいいかを考え、話し合うことで、自分たちができることのヒントが見えてきたように思えました。
新年度の活動スタート
機関誌 『東都生協だより』 2006年6月号より
質疑応答が活発に行われました |
2006年4月22日、さんぼんすぎセンターにて東都生協くらしの助け合いの会 ほっとはんどの第8回総会が、会員36人の出席の下で開催されました。
安西幸子代表幹事より2005年度活動報告・決算、2006年度の活動計画・予算、2006年度の幹事の選出について提案があり、全ての議案が賛成多数で可決されました。
質疑応答の際、会員から「ぜひ広報を充実させて『助け合いの会』を広めていってほしい」との積極的な声が出されました。
よりよい助け合い活動を目指して2006年度がスタートしました。