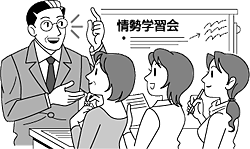福祉
専門委員会主催の情勢学習会を開催しました
福祉を巡る情勢と、他生協の子育て支援活動について学習
|
2005年度の各専門委員会の活動に先立って、世界や日本の情勢(状況)を学習し、委員会の重点テーマと課題を確認するために、5つの専門委員会がそれぞれ情勢学習会を行いました。
福祉委員会
2005年6月7日、東京都消費生活総合センターで福祉情勢学習会が開催されました。参加者は8人。
福祉を巡る情勢と、他生協の「子育て支援」について、日本生協連の二村睦子職員と松村陽子職員から学びました。
初めに、二村職員より他生協の「子育てひろば」の活動の紹介がありました。「子育てひろば」とは、0歳から3歳までの親子が集まる場所で、現代版「井戸端会議」などを行える自由なスペース。プログラムは最低限ですが、スタッフがいて、予約なしでふらっと気軽に利用できます。生協の施設・保険・人材がベースになって全国40生協で実施しています。
少子化の影響で、初めて抱く赤ちゃんが自分の子どもという人が多くなっているのが現状で、親・家庭・地域の子育て能力が低下している中、全ての子育て家庭で支援を必要としています。
その後、松村職員から介護保険制度、全国生協の福祉助け合い活動の取り組みについての話がありました。福祉委員会の活動のヒントとなる学習会でした。
2005年度保育ママ登録・研修交流会
組合員活動への参加時に子どもを預けられる組合員同士の助け合い活動「保育ママ制度」
保育ママ制度の大切さ再確認 |
保育ママとの楽しいひととき! |
2005年度の保育ママ登録・研修交流会が2005年3月31日から5月10日にかけて5カ所で行われ、152 人の保育ママ登録がありました。
各会場では福祉委員から、保育ママが組合員同士の助け合いの制度であること、保育時の注意、報告書の書き方などの説明があり、その後、いくつかのテーブルに分かれて、体験談や今後に向けての意見交換などを行いました。
実際の保育の現場では、主催者側が企画などの準備に追われ、保育ママとのコミュニケーションが不足になりがちだったり、また、保育ママからの声の集約手順が分かりづらいとの声もありました。
福祉委員会は、当日の意見を受け止め、保育ママ制度の相互理解を深めていきます。
東都生協くらしの助け合いの会
ほっとはんど2005年度活動スタート
機関誌 『東都生協だより』 2005年6月号より
活動計画を提案する |
選出された2005年度の幹事 |
2005年4月23日、さんぼんすぎセンターで東都生協くらしの助け合いの会 ほっとはんど第7回総会が開催されました。
活動のまとめと、2005年度の活動計画・予算、幹事の選出などが可決され、2005年度の活動がスタートしました。
提案説明の後、「新任幹事が多いので、予算を有効に使って手厚い研修をしてほしい」との要望が出されました。
また、援助する会員と援助を受ける会員との地域的なバラつきがあって、「待っていても活動に結びつかないこともある」「何かのときに助けてほしいから登録しているが、今は急がないので活動はなし」など、いろいろな実態が話し合われました。
今年度の幹事の2人からは、次のような抱負が寄せられました。
石綿美津江幹事
「未熟者ですが、よろしくお願いします」
鈴木知子幹事
「くらしを支え合う、自主的な家事援助活動がより充実し広がるように、皆さんと協力して取り組んでいきたいと思っています」
きょうされん東京支部との交流会を終えて
機関誌 『東都生協だより』 2005年5月号より
|
|
|
きょうされん東京支部と東都生協との交流会をさんぼんすぎセンター(2005年1月27日)、府中市ふれあい会館(同年1月28日)、昭島あいぽっく(同年2月17日)の3会場で開催。
延べ参加人数は共同作業所からは112人、東都生協組合員からは63人となりました。会場では各作業所の紹介、自主商品の展示や販売と自主商品の製作実演など和やかに交流が行われました。
製作実演は事前に何度も練習を重ねていたそうです。
当日は大勢の人の前で発表する真剣な表情を見て、参加者は心から応援したいと思ったようでした。
各作業所は地域とのコミュニケーションを持つことが重要と考え、これからも地域に根差した交流や関わりをつくっていきたいと発表していました。
当日参加した組合員と作業所で地域単位の交流について話し合っていたところもありました。
今後、東都生協としてもブロックや支部活動の中で作業所などの自主商品の紹介を行い、少しでもメンバーの成果を形にしていきたいと考えています.
きょうされん「第28次国会請願署名と募金」にご協力いただき、ありがとうございました。
期間:2005年2月1回~4回
署名:5,898筆(4月14日現在)
募金:380,127円(4月14日現在)
組合員の皆さまからお寄せいただいた署名は6月に国会へ提出し、共同作業所をはじめとした成人期障害者の施設充実や障害のある人も安心して地域で暮らせるような、具体的な手立てを求めます。
募金は署名用紙の印刷代やきょうされん資金として活用されます。
利用しています 声の商品案内 ―第4回リーディングサービス利用者懇談会」開催―
機関誌 『東都生協だより』 2005年1月号より
利用者からさまざまな |
盲導犬も参加 |
東都生協は2004年11月3日、さんぼんすぎセンターで組織運営部主催のリーディングサービス(声の商品案内)を利用している視覚障害者と「声の商品」を作成している音訳スタッフとの懇談会を開催。ガイドヘルパーや東都生協の役職員など37人が参加しました。
今回は商品の利用普及と調理方法の説明を兼ねて冷凍食品の試食会も行われ、その準備は音訳スタッフの皆さんが頑張りました。
利用者からは「食べたことがないものが食べられて良かった」「試食してみないとわからないのでいい機会だった」など商品について、テープについてなど活発に意見交換が行われ、充実した懇談会となりました。
秋の保育ママ学習交流会を開催
機関誌 『東都生協だより』 2004年12月号より
|
|
|
今秋、東都生協の福祉委員会では、保育ママの活動に役立つことや子育て支援の講演会などを3会場で開催し、延べ72人の組合員が参加しました。
2004年9月24日のテーマは「お母さんだけががんばらない子育て」
講演の内容評論家の芹沢俊介氏を講師に2004年9月24日、新宿農協会館で開催。組合員30人が参加しました。
短い時間の中で、子どもが他者を求め近づく行動「愛着行動」を中心に映画「A.I.」を例に挙げ、分かりやすくお話をしていただきました。
親は子どもの「愛着行動」の受け止め手である「愛着人物」となる必要があります。
子どもを受け止める関係「愛着関係」がきちんとできる前に「しつけ・教育」をしてしまうと、母親の前でのみ「良い子」となってしまうなどの影響があります。
芹沢氏は、子どもの受け止め手である「お母さん」たちを受け止められない、社会の問題などにも言及しました。
2004年9月28日のテーマは「おもちゃを通しての子育て」
芸術教育研究所室長・中野貴美江氏を講師に2004年9月28日、武蔵野公会堂にて開催。18人の組合員が参加しました。
1つのおもちゃでも遊び方を変えると違う遊びができることや、自分で動かす遊びの重要性などを学びました。
参加者からは、
「おもちゃについての考えを変えることができました」
「温かみのあるおもちゃに触れることで心が豊かになることを教えられました」
などの声が寄せられました。
一般社団法人 日本折紙協会・中野光枝氏を講師に東京都生協連会館で開催。組合員24人が参加しました。
折り紙の基本である縦、横の見分け方や山、谷、段、かぶせ折りについて学びました。実際に折り紙で母子猿、パンダ、サンタクロースなどを全員で折りました。