すべてのカテゴリ
「千葉のこめ豚」飼料用米栽培産直交流会を開催しました!
千葉のこめ豚に与えるえさに配合する飼料用米の栽培体験しました!
2010年に「千葉のこめ豚飼料用米栽培産直交流会」として、千葉のこめ豚に与える餌に配合する飼料用米の栽培体験に東都生協組合員とその家族、延べ50人が参加しました。産直産地・JAかとり、㈱コープミート千葉のご協力の下、田植えを2010年5月8日、稲刈りを同年9月26日に行いました。
この企画を通して、飼料用米を作ることが耕作放棄地・休耕田の活用につながること、飼料用米を配合した餌で育てた産直肉「千葉のこめ豚」の消費が環境保全型・資源循環型農業への転換と食料自給率向上につながることについて理解を深めました。
<田植え> 開会式 |
 作業前に記念撮影「頑張るぞぉ」 |
 生産者の方から田植えの説明 |
 田植えの様子① |
 田植えの様子② |
 田植えの様子③ |
 田植え機の操作実演「早いねぇ」 |
 ちょっと田植え機の体験も... |
 「ちゃんと育ってね」 |
稲刈り
 「さぁ 稲刈り」「立派に育ちました」 |
 稲刈りの様子① |
 稲刈りの様子② |
 稲刈りの様子③ |
 稲刈りの様子④ |
 稲刈りの様子⑤ |
 稲刈りの様子⑥ |
 コンバイン作業を見学「やっぱり早い!」 |
<参加者の声(抜粋)>
「飼料米の将来性のお話を聞いて、飼料米の生産がとても多岐にわたる可能性を持ち、有効性を持っていることがよく分かりました。ぜひこれからもどんどん飼料米が国内で生産・消費されることを願っています。こんなにも農業と畜産が密接だなんて...実感しました。」
「田うえ 最初はどろの中に足を入れるのは気もちわるかったけれど入れてみたらいがいと気もちよくていっぱい田うえができたのが楽しかったです。コンバインでうえたのより列がばらばらだったのがおもしろかったです。いねかり かまはするどくけがをするかも?! と思っていましたがけがもなく楽しくできました。いねは太いのと細いのがあり、太い方は力がいりました。けれどたくさんかりとれたのでよかったと思いました。」(9歳)
「親子とも、初めての体験にわくわくドキドキしていました。体験してみると、思っていた以上に楽しく夢中になりました。私は翌日筋肉痛に悩まされました。たった1時間の体験でこれですから、農家の方、特に機械のないころの方々のご苦労は計り知れません。昼食ではおいしいバーベキューを用意していただいてありがとうございました。『千葉のこめ豚』のおいしさを実感しましたので、これからも購入して、食べる時にはこの体験のことを思い出し、食卓の話題にしたいと思います。」
「今回の企画への参加を終えて、飼料用米の目的や役割が少しだけ理解できました。実際に皆さまのお話を聞く中で、より消費者のことを考え、生産工程が組まれていることに感心させられました。私たちが作った飼料用米も有効かつ効率的な思考に少しでも役立てられたらうれしく思います。」
「今回参加したことで、注文の際にその商品の生産背景を想像するようになりました。どんなところで、どんな風に作られ、自分たちのところに届くのか。そんなことを考えながら選んでいくので、時間がかかってしまいます(苦笑)。ささやかではありますが応援しています。」
「産直えさ米たまご」の飼料用米 田植え&交流を開催しました!
飼料用米を給餌して生産した「産直えさ米たまご」の意義を確認
飼料用米を配合した餌で育てた「産直えさ米たまご」(現:ひたち野 穂の香卵)を生産するJA新ひたち野とその販売窓口・日本販売農業協同組合連合会の協力を得て、2010年5月22日(日)に9人の組合員とその家族が参加して田植えと交流を行いました
この体験と交流を通して、消費者と生産者が飼料用米ができるまでの一端を知り「産直えさ米たまご」の価値観を共有。日本の風土に合った米を鶏の餌として生かし、輸入飼料に頼らない畜産生産を実践する産直産地への支援者が増えました。
<飼料用米の田植え風景>
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 「産直えさ米たまご」の卵焼き |
 JAひたち野・島田さん |
 「産直えさ米たまご」生産者・小幡さん |
- 飼料米は日本の畜産のあるべき姿だと思います。食べ物がどのように作られ、守られていかなければならないのか、自分なりによく考え、また他の人にも伝えていきたいと思います
- 「2年生の娘に、田植えを体験させたいという思いだけで参加しましたが、それ以上の充実した一日を過ごすことができました。特に娘は田植えもさることながら、たまごのおいしさに感激しており「生協で注文してね!」と申しています
- 「田うえは、なえを5本ぐらいつまんでうえました。足がとくにどろどろになるけど、土がむにゅっとして、とてもきもちがよかったです。おひるごはんでは、一ばんおいしかった食べものは、たまごやきです。たまごのきみの色はえさによってかわることがわかって、ふしぎだなと思いました。もし、わたしが田んぼをもっていたらみんなでうえたいです(7歳)
- 「産直えさ米たまご」は何度か購入したことがありましたが、あまり詳しいことは知らずに食べていました。単に「休耕田の有効活用のために米を作って鶏に食べさせている」という認識でした。飼料を外国に頼っているというのは知ってはいたものの、改めてお話を伺って、ほとんど輸入に頼っているのは大問題だと危機感を感じました。小幡さんと島田さんのお話は分かりやすくて、大変勉強になりました。お二人の「産直えさ米たまご」に対する愛情と情熱が、こちらにも伝わってきましたよ
多様な活動交流会を開催しました!
東都生協は2011年2月23日に「多様な活動交流会 ~おしえて!あなたの楽しい活...
東都生協は2011年2月23日に「多様な活動交流会 ~おしえて!あなたの楽しい活動~」と題した交流会を文京シビックセンターで開催。
多様な活動を進めている団体の活動発表・紹介・交流の場、多様な団体とのネットワークや活動の広がりを考える場とすることを目的としています。
くらしのテーマ(くらし・福祉・平和・環境・食と農・商品)に基づき活動する専門委員会・支部テーマ別委員会・グループ・サークルなど39人が参加しました。今回は東都人材バンク講師と東都生協ワーカーズ・コープ連絡会からも参加しました。
 |  |
ライアーの演奏や紙芝居など6団体が発表
 |  |
 | 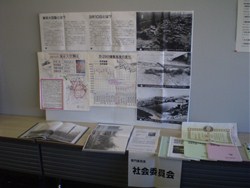 |
展示作品
テーブルに分かれ、「テーマ活動にたくさん参加してもらうために工夫していること」をテーマに意見交換や交流を行いました。
 |  |
いろいろなアイデアを出し合って交流
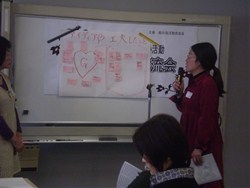 |  |
最後にグループ発表
短い時間でしたが、参加者からは
「普段委員会ではお会いできない方と会え活動を知ることができた」
「これからの活動のヒントになりそう」
「新しい出会いがあり楽しく交流できた」
「熱心な活動が伝わってきた」
「どうしたら参加者が増えるのかを話し合えた」
「企画を立てるときには常にアンテナを張り、タイムリーで興味関心なものなど重要なことを再認識できた」
「アイデアを出し合い今後の参考になった」
などの声がありました。
ブロックや支部とも連携を深めることで、今後テーマ活動をもっと広げていくきっかけとなったようです。
食の未来づくりフェスタを開催しました!
東都生協組合員、生産者など3800人参加の大盛況!
 |
 |
 |
展示・販売や交流を通じて、消費者と生産者が直接手をつなぐ産直(産地直結)の強みを存分に生かし、「食の未来」をさまざまな切り口で楽しく考える機会となりました。
今回の「フェスタ」は、東都生協が進める食の未来づくり運動の成果をみんなで確かめ、その思いを広げ「いのちをつなぐ大切な食」について考えようと東都生協が主催。東都生協産直生産者団体協議会・東都生協共生会との共催で、東京南部生協、東都生協住まいる会が協賛しました。展示・販売と交流を合体させたイベントとしては初めての取り組みとなります。
展示・販売エリアでは、100を超える東都生協の産直産地・メーカーが出展し、自慢の商品の試食や特別価格での販売を行いました。
中央ステージでは、第一線で活躍する尾前武シェフ、塩谷茂樹シェフによるクッキングショー、まぐろの解体ショーや、来場者の参加によるワインの銘柄当てなど、さまざま企画が繰り広げられました。
体験交流エリアでは、産直生産者の協力で野菜クイズや牛乳の実験、わら細工を体験し、北海道・枝幸漁協や宮城県漁協・表浜支所から参加した「浜のかあちゃん」に料理を教わったり、生産者と消費者がじっくり懇談。
消費者が直接、生産者と話をし、味わって、作り手のこだわりや商品の良さを実感し、利用し続けることで、地域農業を元気づけて日本の食料自給率向上につなげていこう、そして安全で安心な食を次世代へ受け継いでいこうとの思いを込めて開催した今回のフェスタ。さまざまな場面をご紹介します。
 |
 メーカーに話を聞いて、試飲して、でもやっぱり迷っちゃう~ |
 新鮮な野菜に生産者の笑顔付き、まさに産直! |
 化粧品を試したり、色を確認したりできました! |
 新燃岳噴火による農作物被害を訴え、支援を呼び掛けます |
■元気なステージ
ステージでは、楽しい企画が次々と...
 尾前シェフが、ほたて、寒ぶり料理のコツを伝授 |
 みかんの皮を一番長~くむけるのは誰? |
 まぐろ1本を見事に解体。試食も楽しみ! |
 |
 塩谷シェフ。チョコレート菓子の技を披露! |
■たのしい♪ 体験・交流エリア
「食の未来づくり運動」に関連したパネル展示、産地のビデオや産地の自慢レシピの紹介や試食、野菜当てクイズや大豆計量ゲーム、生産者とじっくり話せるコーナーなどワクワクが盛りだくさんのエリアでした。
 「魚つきの森」運動を一緒に進める枝幸漁協、 |
 玄米を棒でついて精米。違いが分かるかな? |
 生産者にわらじ作りも教わりました |
 「キッズクッキング」では、チョコバナナ・いちごにチャレンジ |
 生産者を囲んで交流。直接お話を聞くと産地がググッと身近に |
 職員有志などによるソーラン節で、元気にオープン♪ |
 牛さん、寅さん、狸さんは子どもたちと仲良しに |
 「○×クイズラリー」では会場内を回って産直クイズに挑戦 |
第4回消費力検定講座を開催しました!
賢い消費者になるために、みんなで消費者力アップ!
2011年1月14日、東都生協は東京都消費生活総合センター(飯田橋)で、第4回目の消費者力検定講座を開催し、組合員23人が参加しました。
東都生協で行う消費者力検定連続講座は2010年度で3年目になりますが、今回初めて検定後の振り返り講座となりました。
東都生協の受講者の消費者力検定結果の分析について解説いただき、今後の生かし方としてさまざまな啓発方法について学び、参加者は消費者学習は楽しさを実感することができました。
今回は、2010年11月に行った第7回消費者力検定(一般コース)結果と認定証を配付し、消費生活コンサルタントの広重美希氏を講師に、検定の傾向や東都生協受講者の消費者力を分析・解説をしていただきました。
全国平均と比較を行った後、正解率の低い問題を重点に、苦手な問題を振り返り。広重氏から「アンテナを立てていくことが大事」とアドバイスを受けました。
今後の生かし方として、消費者被害の現状を認識し、悪質な業者への対処方法と啓発方法について学習。
特に高齢者の消費者被害では、全国の消費生活センターに寄せられた契約当事者が70歳以上の件数は、2009年度は約12万件で相談全体の13%を占めています。
70歳以上のトラブル相談での販売方法や手口は、1位は訪問販売、2位は電話勧誘販売で、この2つが群を抜いて多くなっています。相談しないケースもよく見られることから、広重氏は「高齢者の周囲の人の見守りが必要」と強調しました。
悪質な業者への対処方法として広重氏は「自分の身は自分で守る意識が大切」として、必要のないものは「要りません」「必要ありません」とハッキリ断ることの重要性を指摘。断り文句としては「今忙しいから...」「主人に相談してから...」などは特に注意が必要だとしました。
 |
 |
断り方ゲームでの断りトークの様子
 |
 |
事例「消防署から来ました」「住宅用火災警報器設置キャンペーンに来ました」の寸劇
続いて、年代・特性に応じた啓発方法を紹介。ロールプレーイングで悪質な訪問販売の事例として「消防署の方から来ました~」についてシナリオを元に参加者で挑戦しました。
年代、特性に応じた啓発方法として以下のようなプログラムが準備されています。
- ゲーム/クイズ/うた/すごろく(金融)
- ロールプレーイング(寸劇)
- パンフレット/ビデオ
- 物作り(エコ料理・廃油石けん)/実演展示法
- 紙芝居/絵本
- 漫才/落語/コント
消費者トラブルについての啓発企画のポイントは「は身近な消費者問題にアンテナを張ること」。
「まず、身の周りで気になっていること、物、それに対する自分の思いを知ることが大切」だとして、参加者同士でアイデアを出し合って企画書を作成し、発表。消費者学習の楽しさを体験しました。
 |
グループごとに消費者の啓発企画を作成
※2010年8月から開始したオープン講座、連続検定講座には延べ175人の組合員が参加し、消費者力を養いました。
----------------------------------------
第3回消費者力検定講座を開催しました
賢い消費者になるために、みんなで消費者力UP!
----------------------------------------東都生協は2010年10月20日、東京都消費生活総合センター(飯田橋)にて第3回目の講座を開催し、組合員43人が参加。消費生活コンサルタントの広重美希氏を講師に、契約と悪質商法について学びました。
契約の原則的知識として、契約の種類、契約の成立、契約が無くなるときなどについて学習。
契約の例外的知識として、合意だけで成立しない契約、消費者契約法、特定商取引法など。特定商取引法の対象となる取引、クーリングオフ、その他救済方法についても学びました。
勧誘業者の勧誘員に勧められ契約した人の立場になって、見本を参考にクーリングオフのはがきを書いてみました。また、悪質商法クイズにもチャレンジしました。
悪質商法の種類
- キャッチセールス
- アポイントメントセールス
- SF商法(催眠商法・宣伝講習販売)
- 点検商法
- ネガティブオプション(送りつけ商法)
- 電話勧誘販売
- 内職商法
- マルチ商法
- 利殖商法
- 家庭教師派遣・学習教材
- 架空・不当請求
------------------------------------------
第2回消費者力検定講座を開催しました
賢い消費者になるために、みんなで消費者力UP!
------------------------------------------東都生協は2010年10月8日、東京都消費生活総合センター(飯田橋)で第2回講座を開催し、組合員31人が参加。
消費生活コンサルタントの西村のぶ子氏を講師に、ライフプラン・金融商品・家計の生活経済についてワークショップを行いました。
生活と家計管理、クレジットの利用、クレジットに関する法律、多重債務、貸金に関する法律、金融商品、金融商品に関する法律、相続、遺言、生命保険、損害保険、税金など生活経済全般と、豊かな生活や人生を実現するためのプランニングと合わせて消費者力を学びました。
金融商品については、生活設計に役立てるために、人生で起こりうるさまざまな出来事「ライフイベント」表を元にワークショップを行い、講師からアドバイスを受けました。
 |
 |
グループ対抗、金融関連の「○×クイズ」にチャレンジ
きょうされんと東都生協との交流会を開催しました!
交流を通して福祉政策の現状への理解を深めました
共同作業所の方々との交流を通して、福祉政策の現状への理解を深めることを目的に、東都生協はきょうされんとの交流会-楽しく!笑顔で!語り合おう!-を2011年1月21日、杉並公会堂で開催しました。きょうされんから28人、東都生協組合員51人が参加しました。
冒頭、きょうされん東京支部より「障害者権利条約」のお話や、国際ルールに沿った新法づくりを求める「きょうされん第34次国会請願署名」についての協力の呼び掛けがありました。障害のある当事者が法令などの制定過程に参加することの大切さや応益負担の問題点を学びました。
|
|
職員・通所者が、各作業所の活動や事業の様子をパワーポイントで紹介
|
続いて、きょうされん所属の共同作業所と東都生協組合員が8つのテーブルに分かれて交流。
同じテーブルの共同作業所が作った商品の良さを学んだ組合員からは、その商品について「エキスパートになります!」との意気込みが語られました。
交流した後は、各テーブルの組合員が、熱の入った作業所商品のアピールを行いました。
参加した組合員からは「作業所のことが理解できた」「私たちにできることや共同作業所と一緒にできることが少しでも増えるとよい」などの感想がありました。
東都生協はこれからも、障害のある方々の社会参加を進める全国組織「きょうされん」(旧称:共同作業所全国連絡会)と、共同購入事業や組合員活動などをさまざまな場で協同を進めます。
「上野公園親子スタディーツアー」を開催!
親子で平和の大切さをかみしめました
社会委員の説明を熱心に聞き入ります |
最初に、慰霊碑「哀しみの東京大空襲」前で、写真や資料を見ながら東京大空襲についての説明を受けます。
次に、上野東照宮の「広島・長崎の火」モニュメントに移動し、広島、長崎への原爆投下や被爆の悲惨さなどについての話や、絵本「原爆の火」の読み聞かせに聞き入ります。
上野動物園まで歩いた参加者は、園内の「動物慰霊碑」前で、人間以外の生き物も戦禍を被ってきたことを学び、絵本「かわいそうなぞう」を読み聞かせ。
お楽しみの動物園スタンプラリーでは、園内の動物をよく観察しながら親子で動物園をまわりました。
親子で平和の大切さをあらためてかみしめる一日となりました。
傾聴と話し方について学ぶ講習会を開催
心がつながるコミュニケーション PARTⅢ ~傾聴と話し方~
相手の話を聞く人・聞かない人を実演 |
2人1組みでロールプレイを行いました |
講師の小谷津光子さん |
今回の講習会は、組合員同士の自主的な家事援助活動に取り組む「東都生協くらしの助け合いの会ほっとはんど」と、保育の助け合い活動を運営する「保育ママ委員会」の共催によるものです。
講師のNPO法人P.L.A・小谷津光子氏から、まずコミュニケーションの基本は、心を込めて相手の気持ちを聞くという「傾聴」であることを説明。傾聴の3つの心構え(受容・共感的理解・純粋性)や、話をする人が望んでいることについて学びました。
その後、2人組になり、ロールプレイで「人の話を聞いていない人との会話」や、この反対の「人の話を聞いている人との会話」を実演。この学習会に参加した動機をテーマに、実際に会話を実習し、振り返りと話し合いをしました。
参加者からは
「今日の実習から、自分はまさに子どもの話を聞いていなかったことがわかった。これからは改善したい」
「次回、保育ママとして活動する時に、学んだことを生かしたい」
「子どもに共感したいが、ついつい上から押さえ付けてしまっていた。これからは『私はこう思うけれど』という範囲にとどめるようにしたい。」
などの声が出されました。
家事援助や保育の活動のみならず、家族や友人とのコミュニケーションにも役立つ学習会となりました。
東都生協では、子育て中の組合員が安心して活動に参加できるようにと、事前に登録した組合員による有償の助け合い活動として保育ママ制度を設けています。
また、組合員相互の自主的な家事援助活動として「東都生協くらしの助け合いの会 ほっとはんど」を運営し、組合員自身の手でくらしを支え合い、安心して住み続けられる地域づくりを目指した活動を進めています。
「Love & Peace音符と遊ぼう♪ Ⅱ」を開催
音楽やお話を通じて平和について考えました
ピアノ・チェロ・オーボエによる演奏 |
鎌倉幸子さんから平和の活動報告 |
「平和」についてのトークセッション |
東都生協は2010年11月20日、世田谷区の烏山区民会館ホールにて、「Love & Peace音符とあそぼう♪Ⅱ」を開催しました。
世界で起こっている現状に目を向け国際的な視野で平和を考えることを目的に「ピースコンサート」「平和の活動報告」「トークセッション」を行い、当日は107人の参加がありました。
開演は午後1時30分。キーボード奏者、アレンジャー、プロデューサーとして多方面で活躍されている井上鑑さんのピアノ、増本麻理さんのチェロ、tomocaさんのオーボエによるピースコンサートでは、多彩な楽曲が演奏され、平和を願いながら奏でられるアンサンブルの美しい音色に聴き入りました。
休憩をはさみ、社団法人シャンティ国際ボランティア会(SVA)国内事業課長の鎌倉幸子さんによる活動報告では、カンボジアの過去と現状について知ることができました。映像を交えた鎌倉さんからの報告は、ご自身の実際の体験も踏まえた、とても分かりやすいお話でした。
また、SVAが取り組んでいる「絵本を届ける運動」の報告もありました。これは子どもの図書がほとんど出版されていないカンボジア、ラオス、ミャンマーの難民キャンプ、アフガニスタンへ絵本を送る活動。
日本で出版されている絵本に翻訳文を印刷したシールを貼り付けるという気軽に参加できる国際協力です。東都生協でもこの活動に参加し、組合員の皆さんに協力していただき、今年は100冊の絵本を贈りました。
当日会場では「リサイクル・ブック・エイド」にも取り組みました。
家庭で不要になった本やCD・DVD・ゲームソフトを提供いただき、これをブックオフコーポレーション㈱の査定を経て、教育支援活動の資金としてSVAへ寄付し、アジアにおける図書館運営や図書館員の育成、絵本出版などに活用するという取り組みです。
一冊の本が、数千の子どもたちの学ぶ機会づくりにつながります。当日は計135点の本やCDなどが集まりました。
続いて行われたトークセッションでは、井上鑑さんと鎌倉幸子さんが「平和」についてトーク。
井上さんの「知らないことは罪ではないが、知らないまま無神経に突き進むのは罪」、鎌倉さんの「未来があると思えることが平和で、子どもたちの笑顔に未来はあると感じられた」との言葉を、参加者は印象深く受け止めました。
トークセッションを通じ、平和であるために「知ることの大切さ」をあらためて考えました。
最後にもう一度演奏があり、音楽の素晴らしさ、平和の大切さを再確認しつつ、この企画を締めくくりました。
「平和について考えるというのは日常ではなかなかできないことですが、音楽やお話を通じて世界を身近に感じることができました」との参加者の感想に表されるように、平和への思いを共有し、平和について考える企画になったようです。
世界にある現実を知り、考えること、関心を寄せること、各自が今できることを考え、実行していくことの大切さを感じる素敵な一日となりました。
新潟コシヒカリ(弥彦)の産地・弥彦村を訪問
産直産地・JA越後中央の位置する弥彦村に親しみを感じる1日となりました!
2010年11月11日に新潟コシヒカリ(弥彦)を生産するJA越後中央・弥彦営農センターが位置する弥彦村を、11人の東都生協組合員が訪問しました。
ちょうど紅葉が見ごろの弥彦村で米の低温倉庫見学や温泉、菊まつり、そして寺泊の魚の市場通りでの買い物などを楽しみ、弥彦村に親しみを感じる一日となりました。
■JA越後中央の低温倉庫
倉庫の奥まで積み上げられている新潟コシヒカリ |
現地に到着した一行は、JA越後中央の米を貯蔵する低温倉庫を見学しました。
9月に収穫された米(もみ)は、各生産者が乾燥し、もみすりをして玄米にします。同農協の倉庫に運ばれた玄米は、約1トン入りの大きな袋に詰められ、検査を受けた後、この低温倉庫に積み上がります。
低温倉庫には、玄米が入った袋(フレキシブルコンテナパック)が倉庫いっぱいに積み上がっていました。米の保管状況を初めて見る組合員が多く、整然と積み上げられている様子に圧倒され、品質管理がしっかりしていることに感心していました。
 左は説明をするJA越後中央弥彦営農センターの本間センター長 |
 |
 |
 |
 |
■寺泊の魚の市場通り
寺泊の魚市場通り(通称「魚のアメ横」)には、大型鮮魚店が軒を連ね、日本海の魚介類を中心とした海の幸が手ごろな値段で売られていました。
 |
米の消費量の低下、価格の下落、農家の高齢化など、米農家を巡る状況は厳しくなっていますが、こんなときだからこそ、生産者と消費者の関係を深めていくことが大切だといえます。
私たち消費者が今後も安心できる産直米を安定的に手に入れ続けるためには、消費地と生産地との距離を縮めていくことが必要。東都生協ではいろいろな形で産地との交流を行い、生産者の顔が見えるだけでなく、生産者にとっても消費者の顔が見える関係作りを進めています。
皆さまも産地・メーカー交流訪問に参加する機会があれば、ぜひご参加ください。










