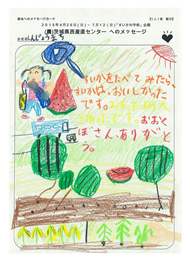すべてのカテゴリ
2015年東都生協 親子ヒロシマ平和代表団 報告
ヒロシマ被爆70年の歴史と復興への歩みを学び、平和の尊さを教えられました。
2015.08.24
カテゴリ 平和
広島城の石垣 原爆の熱線で一部黒く変色 |
組合員が折った千羽鶴を手向けます |
「被爆樹」の前で説明を聞きます |
東都生協ヒロシマ平和代表団 |
「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、広島県生協連・長崎県生協連・日本生協連が、被爆体験の継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として毎年開催。1978年のスタートから、東都生協も毎年代表を派遣しています。
例年、ヒロシマ平和代表団派遣は1泊2日で開催してきましたが、今年は戦後70年という節目の年であるということもあり、ヒロシマの実相についてもっと深く学ぶため、2泊3日の行程としました。
8月4日広島到着後、一行は「碑巡り 広島城周遊コース」に参加。
広島城内には、旧陸軍の第5師団や当時の広島大本営の建物、地下には「防空作戦室」や「通信室」といった軍事施設の戦争遺跡が現存。
普段は入ることのできない「防空作戦室」や「通信室」の内部を地元のガイドの説明を受けながら見学しました。
8月5日は「碑巡り 白神社・袋町小学校コース」、日本生活協同組合連合会主催「虹のひろば」に参加しました。「虹のひろば」は全国の生協の参加者が集う場です。
メインステージでは、被爆ヴァイオリンと被爆ピアノでの演奏から始まり、松井広島市長のあいさつの他、被爆者代表、高校生代表のリレーメッセージが行われました。
また、夜は東京の生協が集う交流会に参加し、被爆者の方の貴重な証言を伺いました。
被爆者の方が、原爆投下当日一緒にいた友人の表情や町の様子などを淡々と話されていました。淡々としたその語り口に、当時の状況が一層リアルに伝わり恐ろしさを感じました。
8月6日最終日は、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に参列しました。
また、東都生協の組合員が折った千羽鶴を平和公園に手向けました。
今年、被爆者の平均年齢は80歳を超えました。年々体験を語る方の人数は減少していきます。より多くの人が被爆地を訪れ、被爆の実相や被爆体験を聞き、継承していくことが大切になっています。
2015年東都生協 ナガサキ平和代表団 報告
長崎の鐘と町中のサイレンが鳴り響く中、原爆犠牲者の冥福を祈り黙祷を捧げました
2015.08.24
カテゴリ 平和
長崎爆心地碑。 |
組合員から託された |
田上富久 長崎市長 |
被爆者の証言を聴く |
「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、広島県生協連・長崎県生協連・日本生協連が、被爆体験の継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として毎年開催。1978年のスタートから、東都生協も毎年代表を派遣しています。
1日目は「被爆の証言と紙芝居」に参加。
1歳9カ月だった当時に被爆した男性からは、被災した当時の様子や、その後毎年8月9日になるとご両親が当時の状況を話してくれたことなど1時間にわたってお話しを聞きました。
その後、平和案内人(※)による紙芝居「平和を刻んだ少女 菅原耐子さん」を鑑賞。
爆心地から500mの場所にある城山小学校に建てられた少年平和像の台座に書かれた「平和」という文字を書いた当時6年生の少女(菅原耐子さん)の実際の出来事を1年かけて調べ、作られた紙芝居でした。
2日目の午前中は、原爆落下中心地碑~如己堂(にょこどう)・永井隆記念館~浦上天主堂を巡る「平和のまち歩き」に参加しました。平和案内人から、原子爆弾投下直後の人々や町の様子なども詳しく聞くことができ、爆風や熱線の威力を実感しました。
午後は、日本生活協同組合連合会主催の「虹のひろば」に参加。
オープニングは「波佐見町 鹿山雷神太鼓」による迫力満点の太鼓演舞で始まりました。
被爆者(山口仙二さん)の魂の軌跡を音楽と語りで紡いだ「ノーモア・ヒバクシャ」では歌手で俳優の上條恒彦さんの素敵な歌声と劇団TABIHAKUが織り成すハーモニーに会場中が感動をしました。
2015年NPT再検討会議に合わせニューヨークへ行かれた長崎原爆被災者協議会会長の谷口稜嘩(すみてる)さんと、ララコープ会長理事の水町初江さんのリレートーク、8月5日ピースアクションinヒロシマで行われた「子ども平和会議」のアピール文発表なども行われました。
最後に、平均年齢77歳という世界で唯一の被爆者合唱団 被爆者歌う会「ひまわり」による合唱を聴きました。
最後の曲「We never forget」では参加者も一緒に歌い会場が一つになりました。また、長崎市の田上富久市長からのあいさつもありました。今年は全国の生協から約900人の参加があり、平和への思いを一つにしました。
最終日は、長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に参列し、長崎の鐘と町中のサイレンが響く中、原爆犠牲者の冥福を祈り黙祷を捧げました。
実際に原爆の遺構を見たり、被爆証言を聴いたりすることで、原子爆弾の威力の大きさや、戦争に巻き込まれてしまった子どもたちの思いなどを肌で感じることができました。
今年、被爆者の平均年齢が初めて80歳を超え、被爆体験を語り継ぐことへの危機感が募ります。
まずは今回見聞きしたことを身近な人たちへ伝えていくこと、そしてたくさんの人がこうした企画に積極的に参加することが大切だという思いを参加者で共有しました。
※平和案内人:
平和案内人(ボランティアガイド)は、被爆者の高齢化が進む中、被爆の実相と平和の尊さを次世代に伝えていくために活動しています。主に長崎原爆資料館や国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、平和公園周辺の被爆建造物などを一緒に巡りながらガイドを行います。
出典:公益財団法人 長崎平和推進協会ホームページ
公益財団法人 長崎平和推進協会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
配送センターに太陽光発電設備を設置しました!
東都生協は再生可能エネルギーの普及・拡大を進めています
2015.08.11
カテゴリ 環境
国立センター(東京都国立市) |
屋上に設置した太陽光パネル |
モニターで発電状況が確認できます |
発電した電力は、配送センターで使用する電力の一部として使われます。また、災害時には非常用電源としても活用できます。
今回の設置により、太陽光発電設備が設置されている事業所は、八潮センター(埼玉県八潮市)と合わせて2カ所となりました。
年間発電量の合計は、約4万kWh (一般家庭の年間電力消費量換算で約9軒分に相当)となる見込みです。
CO₂削減効果は、年間16トン。森林面積で換算すると43,950㎡になります。この面積は、およそ東京ドーム1個分に相当します。
*CO₂排出係数 0.5045kg-CO₂/kWh (平成24年度太陽光発電協会)による算出
東都生協は、原子力発電に頼らない持続可能な社会づくりの実現に向けた取り組みとして、再生可能エネルギーの普及・拡大を進めています。
<設備概要>
設置場所:東都生協 国立センター(東京都 国立市)
発電容量:33kW
年間予測発電量:31,112kWh
稼働開始:2015年7月24日
おいしいすいかを作り続ける生産者は「かっこいい!」
(農)茨城県西産直センターにて、すいかの苗植えから管理、収穫までを体験
2015.07.23
カテゴリ 食と農
大きく育つように |
わらは「すいかのベッド」 |
収穫を親子で喜びます |
産地への感謝のメッセージ |
「すいかの学校」は、4月の苗植え、5月わら敷き、7月収穫の全3回。すいかの苗植えから、生育の管理、収穫までの一連の作業を通じて、農業に触れ、学ぶことを目的としています。
2015年度は14家族・42人が登録。果物作りの一連の作業が体験でき、生産者とも交流できる機会として、東都生協の農業体験企画の中でも人気があります。
第1回目(4月26日)はすいかの苗植えです。畑は、東都生協出荷用の畑の一角をお借りするという本格的なもの。まず、畑に肥料をまく土づくりから始めました。
すいかの苗は、土台を強くするために台木となる「夕顔」の苗に「すいか」の苗を接ぎ木したものを用います。生産者の大久保さんに、1カ月前から準備していただきました。みんな、大きく育くように願いながら畑に穴を掘ってすいかの苗を植え、土を掛けました。
第2回目(5月24日)は、日照や乾燥、汚れからすいかを守る「わら」を敷く作業。また、伸びた弦の先に咲いたすいかの雄花、雌花を合わせ、受粉させる作業も体験しました。この作業はとても重要な作業で、めったに体験できないものです。
第3回(7月12日)。苗を植えてから約3カ月、いよいよ立派に実を結んだすいかの収穫です。自分たちで植え、育てたすいかへの思いはまた格別なもの。「小玉すいか」といっても1玉が約3kgあり、子どもには重い物でしたが、皆、大事そうに収穫していました。
生産者の大久保さんが既に収穫し、冷やしておいていただいたすいかを、みんなで試食。暑い中、畑で食べるすいかのおいしさは忘れられないものとなりました。
参加者からは、
「すいかを家で、いざ切ってみたら、畑で見た時より一段と大きく感じた」
「受粉のために蜂がいたことも、子どもに興味深かったようだ。命の一端をリアルに感じた」
「自分たちで、苗を植え、わらを敷き、作業の流れを手伝わせていただけたので、作物に対しすごく愛着が湧いた」
「おいしい作物を作り続ける生産者はかっこいい! 生産者の笑顔がすてきだった!」
――などの感想が出されました。
東都生協は産地直結を実感し、商品のこだわりや食の大切さについて学び、次世代へつなげていく機会として、これからも農業体験企画を実施していきます。お楽しみに!
アレルギー表示の学習と試食会を開催!
4月より食品表示法が施行 ―― 分からないことはメーカーに確認を! ――
2015.07.09
カテゴリ 食と農
熱心に聴き入る参加者 |
アレルギーを考慮した商品を展示 |
第1部ではアレルギー表示について学習。
講師は東都生協アレルギー相談室の武内澄子氏です。2015年4月1日より新たに「食品表示法」が施行されたことを受け、新表示と旧表示の違いを学びました。
◆新「食品表示法」とは
これまで商品表示のルールは、JAS法・食品衛生法・健康増進法という目的の異なる3つの法律で定められていました。これらの表示義務を1つにまとめ、より安全でより分かりやすい表示になるように新しく「食品表示法」ができたのです。
新アレルギー表示の主な内容
・個別表示を原則とする
・表示面積の制約や原材料が多く、消費者に分かりにくくなる場合は、一括表示を認める
・繰り返しになるアレルゲンは省力してもよい
・特定原材料が使われていることが明らかに分かる「特定加工食品」と、名称から使われていることが予測できる「拡大表記」は廃止して、全て表示する
――このような内容で施行された「食品表示法」ですが、猶予期間が5年間あります。つまりこの5年間は、新表示と旧表示が混在するため、両方の知識が必要となります。
アレルギー表示のことなどで分からない場合は、メーカーへ聞き、確認することが大切です。
◆アレルギー表示品目 ※2015年6月時点
義務(7品目):卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに
推奨(20品目):いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉
表示対象食品:容器包装された加工食品と食品添加物
量:食品に含まれる総たんぱく質が数㎍/g以上の場合(1㎍=1gの100万分の1)
この順番は、2011年~2012年全国実態調査での発症数の多い順だそうです。
◆食育が大切 ~知識を得ることで命を守る~
子どもにアレルギーがあるからと、その食品を見せないでおくのは危険なことです。
なぜなら、食品が何からできているのかを学ぶことが、自分の身を守ることにつながるからです。例えば、バターは牛乳からでき、マヨネーズは卵からできる。そして卵は鶏から産まれる――こうしたことは、食育としても、とても大切なことです。
こうして、自分で判断できる子どもに育てることができます。
◆健康志向で注目されているごまが...
ごまは抗酸化作用で注目が高まり、想像できない商品に使用されています。例えば、カレールゥ・みそ汁・洋菓子・健康飲料などは、原材料にごまが多用されており、特に注意が必要です。なお、黒ごまより白ごまの方が、アレルギーを起こしやすいそうです。また、1歳・2歳児がいくらや生ものを食べるのは避けた方がよいようです。
>◆乳由来の食品添加物
・カゼインNa...牛乳に含まれるたんぱく質の一種です。乳化剤・安定剤として菓子類、パン類、乳製品類に広く使われます。口腔ケア商品にカゼインNaが含まれることがあるので、歯科医院でも確認が必要です。
・CPP(カゼインホスホペプチド)...カルシウム吸収促進剤
これらは「乳」由来だと判断することが必要です。
安心して食事を楽しむために、不明な点があったらメーカーへ確認しましょう。
第2部では、アレルギーを考慮した商品の試食と展示を行いました。共同購入の商品案内「さんぼんすぎ」で企画されている商品を実際に手に取り、パンやお菓を試食。「米粉のパンケーキ」「お米で作ったまあるいパン」「みちのくせんべい」「フレンズスイーツガトーショコラ」など、さまざまな東都生協商品が紹介されました。
参加者からは、
「食品表示についての法律が変わったことは知らなかったので、とても勉強になった」「アレルギーを考慮した商品はシンプルな原材料のものが多く、安心しておいしく食べられる」「試食では、アレルギーの有無にかかわらずおいしかった」「知識を身に付け『自分の身は自分で守る』子どもを育てる上で大切なことを再認識した」
――などの声が寄せられました。
2015年度も組合員参加による商品活動が開始
組合員の声に応え、商品政策や基本方針に沿った商品づくりを進めます
2015.07.06
活発な質疑が行われた |
商品ガイダンス資料 |
東都生協は2015年4月24日、商品活動に関わる組合員・地域コーディネーター・組合員理事を対象に「商品委員会ガイダンス」をさんぼんすぎセンターで行いました。
東都生協の商品委員会は、組合員の声に応える商品事業を進めるために商品活動全体を取りまとめ、商品事業が組合員の声に応え、商品政策や基本方針に沿って進められているかを評価・提言する役割を持ちます。
まず、商品部職員が「東都生協の商品政策」「組合員のくらしの変化に対応した商品の考え方・取り扱い基準」を資料に沿って説明。「東都ナチュラル」で有機牛乳を取り扱う経緯の話では、「従来のHTST(高温短時間殺菌)と有機牛乳のUHT(超高温短時間殺菌)との違いは?」など活発に質疑応答が行われました。
次に安全・品質管理部職員が「食品衛生の基礎知識(食の安全に関する近年の出来事や食料自給率、輸入食品の安全性、食品添加物、食中毒、寄生虫、異物混入など)」を説明しました。
中でも「農薬を使わないと収量は3割減になる」「魚介類の寄生虫は加熱・冷凍で死滅する。東都生協の魚介類は冷凍なので安全」というお話が印象的でした。「良い商品を取り扱っているので、自信を持って進めていただきたい」という結びの言葉にも納得でした。
参加者からは
「子どもがいるので商品をよく知りたかった。試食もできて大変勉強になった」「新商品おしゃべり会に登録したことで、東都生協の考え方や基準・検査体制・食品衛生の知識と幅広く学習できた」
――と好評。
東都生協は、一人でも多くの組合員が活動に参加して商品を知る機会を、今後も設けていきます。
㈱ルミエール訪問
有機農法で育てたブドウから最高品質のワインが生まれる
2015.07.06
カテゴリ 食と農
日本式ブドウ畑 |
いろいろなワインの試飲もしました |
ヨーロッパ式垣根栽培の畑と日本式のブドウ畑を見学しました。
2004年から自然農法を取り入れて栽培していますが、日中の気温は高くても、夜は25度以下になることでブドウの色ののりや糖度が上がるため、昨今の温暖化は深刻な問題なのだそうです。
ワインセラーの見学では、花崗岩を積み上げて作った国登録有形文化財の石蔵に見入り、ワインの試飲ではその深い味と香りに舌鼓。
参加者からは
「ブドウの実のなる前の畑に感動!」
「素晴らしい歴史のあるワイン蔵が見られて良かった」
――などの声が寄せられました。
本物のワインを作るために本物のブドウを育てる――最高品質へのこだわりと理念が受け継がれているメーカーに感慨を覚えた訪問となりました。
料理作りから広がる新たな仲間の輪
サポーター&総代の交流会
2015.07.06
カテゴリ 食と農
「三州三河みりん」を使って |
交流が活動の幅を広げるきっかけに |
総勢22人で「三州三河みりん」を使用した鶏肉のソテーみりんバルサミコソース、ライスサラダ、MIRINパンナコッタを調理。出来上がった料理をいただきながら交流をしました。
どの料理も美味! 特に"コクがあり、しつこくない「三州三河みりん」の甘味が洋風デザートに最適" と、パンナコッタが大好評でした。
交流会では、東都生協のことから各人の住んでいる地域のことまでいろいろと話が弾み、新しい仲間ができたり、総代に興味を持った人もいて、活動の幅を広げるきっかけになったよう...。
皆さんから、楽しかった、また企画してほしいとの声が上がっていました。
トイレットペーパーができるまで30時間!
~古紙再生の現場見学~
2015.07.06
カテゴリ 環境
牛乳パックを回収した原料 |
直径2mの原紙ロール |
みんなで資源回収の大切さを感じました |
ここでは牛乳パックなどの古紙からトイレットペーパーを1日65万個作っています。
30~40年前に牛乳パック回収ルートの確立に貢献した同社ですが、最近の古紙回収率は減少傾向にあり、再生する際の配合率を守れなくなってきているそうです。
工場内の直径2メートルもある原紙ロール、プリント版、トイレットペーパーが作られる様子に、参加した子どもたちも興味津々。
紙粉が舞い、大きな機械音の中で作業する姿を見て大変な現場であること、古紙再生には多くの工程が必要なことも確認できました。
参加者からは「リサイクルの現場は初めて。資源回収の大切さをあらためて感じた。皆さんに呼び掛けたい」などの声がありました。
商品委員会主催 放射能学習会 報告
~国産水産物について~
2015.07.06
カテゴリ 食と農
水産庁より招いた講師の方々 |
大勢の幅広い年齢の参加者 |
講師には水産庁漁政部加工流通課・課長補佐の岡野正明氏を招き、水産物の放射性物質調査について講演をしていただきました。
主な内容は、福島の原発事故から4年経て、食品を巡る環境はどうなっているかということ。特に、国産水産物などの放射性物質の調査結果や、安全性確保のための取り組みについて学びました。
参加者は幅広い年齢層で小さいお子さん連れの人も多く、それぞれに深い関心を持って参加していることがうかがえました。
今回の講演で水産物の放射性セシウムについては理解できたものの、参加者皆さんの不安が全て解消されたということではなかったようです。
アンケートでは「放射能学習会は今後も定期的に開催してほしい」「日本海を含め全国レベルの話も聞きたい」「健康被害について、放射性物質排出の方法、調理の際の工夫などを知りたい」といった意見・感想も多く聞かれました。
東都生協の安全・品質管理部では現在、1週間に約85検体を検査し、商品の供給時に2週間に1度のペースで検査結果報告を組合員に配付しています。また、東都生協のホームページでも残留放射能自主検査結果が検索できるシステムになっています。
今回、この情報があまり利用されていないことも分かりました。
参加者にとって放射性物質を巡る現状を知ることができた学習会になりました。