商品活動
(農)大矢野有機農産物供給センターを視察訪問
―視察訪問 第5弾―
「不知火」の品種や病気を説明 |
センター独自のボカシ肥料 |
1日目は、東都生協組合員が生産者支援のために出資する「土づくり基金」を利用した、「ボカシ肥料工場」を視察。同産地では、有機発酵肥料の「ボカシ肥料」を自家製造しています。
ボカシ肥料の材料の配合は作物によってさまざまですが、魚粉・米ぬかなどを3カ月切り返しをして混ぜ、年3回、共同作業で同産地の必要量・約140tを自給しています。
次に視察したのは、かんきつと葉付き玉ねぎ畑。同産地・鬼塚理事長からは、栽培理念・基準のほか、かんきつ選果時に行う糖酸度検査などについて説明を受けました。
2日目は、せり・しょうが貯蔵庫、にんじん畑を視察。地域が広いため出荷場まで40分以上もかかる所があったり、イノシシによる被害があるなど、生産上のご苦労も伺いました。
生産者の皆さまは真剣に作物と向き合い、品質向上や安定供給に努めているのに、気候の影響に左右され、規格外で出荷不可となる作物が想像以上に多いことにも、参加者は驚かされました。
お話を聞き、参加者から「規格外商品を東都生協で取り扱ったら?」という意見も出ましたが、生産者からは見栄えが悪いだけでクレームになることもあるので、扱いが難しいとのことでした。
さらに、生産者の高齢化で後継者不足問題を抱えているという現実もあります。参加者にとって、日々努力している生産者の思いを忘れず、今後も感謝をもって食べていきたいと感じられた視察訪問となりました。
「試して 伝えよう!」連絡会での利用促進商品と報告
連絡会での商品の試食・アンケートを通じて利用普及を推進
試食アンケートはその場で記入、回収 |
< 4月の利用促進商品 |
連絡会は月1回程度、ブロック委員会・とーと会・サークルなど地域内の活動団体が出席して開催する会議。今回の取り組みは、連絡会出席者が利用普及商品を試食し、各地域での利用普及を推進することが目的です。
昨年度は12回の連絡会にて、商品委員会で確認した商品のうち12品を試食・評価しました。地域によっては商品委員が商品普及活動の先頭になり、商品をPRしました。試食アンケートでは、毎回、評価以外に意見・感想・コメントが多数寄せられます。
その後、結果を集約、商品委員会で報告され、アンケートは商品部へ手渡されます。商品部では全てに目を通し、寄せられたお薦めコメントは、広報で使用することもあります。
商品の利用普及を進めるには、実際に試し、組合員同士で伝え合うことが必要不可欠。そのため、連絡会での試食は利用普及に直結する活動となっています。ただ、アンケート結果での「おいしい」は「利用したい」に簡単には結び付かないのも実状です。
東都生協はこれからも機会あるごとに、組合員の皆さまから直接声を聞き、組合員のニーズに合った商品を提案していきます。
組合員が信州ハム㈱を視察訪問
安全・安心、おいしさにこだわった丁寧な商品づくりを確認しました
メーカーの方から概要を聴き取り |
工場内の製造工程を確認 |
異物・変形などを丁寧に選別 |
2013年9月19日、東都生協は長野県上田市の千曲川のほとりにある信州ハム㈱の視察訪問を行いました。視察訪問企画では、東都生協商品の生産現場や関連する施設を視察します。目的は、東都生協との約束事や、約束を守るための仕組みとその運用実態、産地やメーカーの特徴的な取り組みなどを、組合員自らが確認することにあります。
創業71年の信州ハム㈱では、恵まれた自然の中で製品を丁寧に作り続けていることを確認。特に東都生協のための無塩せき商品の製造では、添加物・アレルゲン(小麦・卵・乳)・異物混入にも細心の注意を払われていました。無塩せきについての説明では、体に優しい商品作りへのこだわりを再認識させられました。
工場では、原料の出庫から完成品の箱詰めまでの流れを見学。細菌に汚染されないようにクリーンルームなどの入口は別々に設置、素爪ブラシ他もきちんと用意し、素手で肉の骨などをチェックするために15分ごとに消毒液で手を消毒することを義務付けています。また、製品工程の見学では、整形(骨・異物の除去)⇒無塩せき味付け⇒熟成⇒パック⇒熱処理⇒充てん⇒機械パック⇒金属探知機 の各工程で細かく異物・変形などのチェックを行い、手間を惜しまない姿勢が見られました。
「添化物の少ない商品から作っていくので、東都生協の商品は朝一番に作っている」とのこと。
参加者は、「清潔な工場で商品が作られているのが分かった」と安心した様子。また、「無塩せき商品の良さをあらためて認識することができた」「おいしいハム・ソーセージの試食に感謝です。いただいたレシピも参考にして孫たちに食べさせたい」などの感想が寄せられました。
年末年始に向けた試食会「冬の楽☆楽パーティー」開催
年末年始商品の利用普及に向け、組合員組織で試食会を開催
みんなで話し合いながら進行 |
味付けぽん酢と胡麻油で |
バラエティー豊かな試食品。 |
試食会開催をエントリーした団体には、事前に手軽に作れるパーティーレシピと開催手順の説明などが届きます。メニューが決まったら、食材の手配と準備をします。併せて、地域への広報から参加者のアンケート回収・報告まで、それぞれが主体となって進めます。
開催エントリーした青井ブロックでは、2013年10月14日に開催。会場の足立センターには、祝日にも関わらず13人が参加しました。
はじめに参加者でテーブルを囲み、試食商品の内容や調理方法、盛り付け、テーブルセッティングについて話し会った後、全員で調理。おしゃべりをしながら電子レンジでチンしたり、盛りつけをしたりと、楽しく作業が進み、バラエティーに富んだ試食品が出来上がりました。試食ではどれにしようか迷いながらも、お気に入りを見つけたようです。
「活動に参加するのは初めて」「勤めていて参加する時間が取れなかった」という参加者も、「試食会に参加して発見があった」「今後も利用していきたい」と好評でした。主催者は「皆さんに楽しんでいただき、意見も聞けて参考になりました」と、今後につながるヒントも多く、両者に有意義な機会となったようです。
「作ろう! みんなと同じ給食」― アレルギー対応について学ぶ会 ―
除去食は、見た目を"似せて作る"ことも必要!
揚げパンの生地は米粉 |
馬肉を使ったミートソース作り |
当日のメニュー:シュウマイ2種、 |
アレルギー対応について学ぶ会は2013年10月10日、さんぼんすぎセンター調理室にて調理講習会を開催。当日は、組合員、学ぶ会(飯田橋会場メンバー・立川会場メンバー)合わせて15人が参加し、アレルギー物質として食品に表示を義務付けられた特定原材料の7品目、卵・乳・えび・かに・そば・落花生・小麦―を除去した給食メニューに挑戦しました。
食物アレルギーがある子どもに対して、学校の対応はさまざまです。今回は小学校と幼稚園給食の献立表から、給食と同じようにお弁当を作るのは難しい、と思われる6品を決定。お弁当作りの参考になるように、みんなで作り方を検討・試作しながらレシピを練り上げました。
食材は、東都生協の「アレルギーを考慮した商品」と㈱鎌倉ハムクラウン商会の「ハム」「塩麹」などアレルゲン不使用商品の中からチョイスし、リーダーを講師に4つのテーブルに分かれてクッキング開始。各リーダーは、参加者の質問に答えながら手際よく調理し、学ぶ会のメンバーも自分たちで工夫した作り方を教え合いました。
給食そっくりに出来上がった「卵を使わない親子丼」「牛乳を使っていないプリン」などに、みんな感動! 実際に食べてみて、「単純にアレルゲンを除去していたが、"似せて作る"ことも必要だと分かった」など、参加者の感激の声はさらに大きくなりました。
今年からアレルギー対応について学ぶ会は2会場で開催され、両会場でメンバーの交流、組合員との交流が行われています。
「メーカーに聞く、アレルギー対応商品の秘密」
アレルギー対応について学ぶ会が、人に優しく環境に優しい石けん製品などを製造する太田油脂㈱を招き学習会開催
|
同社は愛知県岡崎市にあり、「なたね油」「エゴマ油(しそ油)」などを製造しています。アレルギー対応商品の開発は2006年11月に立ち上げ、2007年2月からMSシリーズの販売を開始しました。
同社では自社工場ではなく、約20社に商品の製造を依頼。規制が多いため、製造工場を探すのには大変苦労したそうです。さらに、自社工場ではないため製造から出荷まで細心の注意を払い、アレルギー検査も細かく実施し、少しでも分かりやすく正確な情報に基づく表示を心掛けています。
また、「アレルギーの子どもだけではなく、みんな一緒に食べられる商品作り」を目指しています。
【MSシリーズのコンセプト】
・香料・着色料・化学調味料を使わない
・表示対象25品目+ごま・米・じゃがいもを表示する
・製造ロットごとにアレルギー検査をしている。
・製造環境の情報を開示している。
【東都生協で扱っている商品】
「カリカリスティック(さつまいも味・かぼちゃ味・ポテト味)」
「おかかせんべい」
「サクッとコーンクッキー」
「こめせんべい」
「こめぽんせん」
固形せっけん作りも体験
合成界面活性剤を使わず、人と環境に優しい石けん作りに半世紀以上にわたって取り組む太陽油脂㈱を野毛ブロック(世田谷区)が交流訪問
固形せっけん作り |
太陽油脂㈱製品の展示 |
「油」には石油系と油脂とがありますが、同社では油脂を使用。合成界面活性剤は使わない、人と環境に優しい石けん作りを半世紀以上にわたって続けています。
続いて水酸化ナトリウムと油で固形せっけん作りを体験。汚れを落とす仕組みや、川に流れた後どうなるかなどを学び、石けんに関する知識を深めました。
その後、実際の固形せっけんや液体せっけんの工程と、食用油のパック詰めを見学しました。子どもたちは、見学している間に固形せっけんが出来上がっていて大喜び。
同社の徹底した省エネへの配慮と、太陽光発電を利用して機械を動かしていることにも、参加者は驚かされました。
参加者からは、
「汗の成分は酸から作られるので、水で下洗いしてから洗たくするとときれいになる、という話がとても参考になった」との声も聞かれました。
親子ともども、楽しい学習の場となりました。
「ぴっかりぴん」のふるさとでワイワイ交流会
JAやさと(茨城県石岡市)で視察・交流会
カエルつかまえたよ! |
賞品は同産地が生産するコシヒカリ |
参加者全員で |
行きのバス車中では、商品部・柳澤誠職員が「生き物がいる田んぼの大切さ」をクイズを交えて解説。到着後はJAやさとの生産者と田んぼへ向かいました。
体験田では、水草の下の生き物を探すコツを教わりながら早速採集。なかなか見つけられず、子どももおとなも無我夢中! 最終的にはアメリカザリガニ、メダカ、ゲンゴロウなどが集まり、みんなで観察しました。
生き物を田んぼに返した後のお昼のバーベキューには「ぴっかりぴん」の塩むすび、地元野菜やしゃも肉などが登場。おむすびは大好評で、3個も食べた子がいたほどです。
生産者との話も弾み、「食べて支えてもらっていると思って作っている」「いっぱい食べてください」との生産者の言葉に、「食べます!!」と参加者が答える場面も。
食後は「ぴっかりぴん」が当たるクイズや記念撮影の他、米低温倉庫と精米施設も視察し、最後はJAやさとの直売所へ...。
参加者は、「生産者が努力していること、田んぼが治水に一役買っていることが勉強でき、とても有益でした」「チラシを見るとき〝ここで作られたんだな〞と思いながら注文できます」etc.と感慨深げ。
子どももおとなも産直米の故郷を知り、たくさんのことを学びました。ご飯を食べるとき、きっとこの日のJAやさとを思い出すことでしょう。
JAやさと:
茨城県のほぼ中央に位置する自然豊かな産直産地。JAやさと農協管内の農業は、昔から養豚、酪農、養鶏などの畜産が盛んで、その家畜の有機物や落ち葉を堆肥にして、野菜や果物の多品目複合農業・環境保全型農業が行われてきました。東都生協とは地域ぐるみの総合的な産直「地域総合産直」を推進し、野菜・果物、産直たまご、コシヒカリ(ぴっかりぴん)、産直加工品の納豆などを生産しています。
「安全・安心」を「聞こう・知ろう」学習会
「東都生協の物なら安心して買えると再確認できた」
東都生協商品を試食しながら交流 |
初めに商品部・野地浩和部長が東都生協の歴史や理念、「食の未来づくり運動」や安全・安心を確保するための仕組みを紹介。また、東都生協の畜産物・農産物などの商品は、いつ・どこで・誰が・どのように作っているのかが「商品ガイド(仕様書)」と「eBASE(商品情報データベース)」で明確なことを説明しました。
次に安全・品質管理部の職員が、安全な商品を作るための科学的な方法を解説。東都生協いちおし商品である「河内晩柑」「東都惣菜屋さん白和え」「高原朝摘みトマトジュース」について、そのおいしさだけではなく、商品ができるまでの過程や思いなどを語りました。
後半はグループに分かれてイチ押し商品の試食を行い、商品部の職員も加わって懇談。「お弁当用に冷凍のまま入れられる商品が欲しい」「魚の切り身は2切れが使いやすい」などさまざまな意見交換ができました。
参加者からは「お薦めの声を職員からじかに聞け、熱意が伝わった。愛情を持って商品を見守っているのがよく分かった」「東都生協の物なら安心して買えると再確認できた」など商品政策が理解された学習会になりました。
2013年度「新商品おしゃべり会」活動
企画前の新商品を評価し、声を寄せ合う組合員による商品作りの活動
凍ったまま、すぐ炒められて便利 |
三陸産山かけめかぶ |
新商品おしゃべり会 |
初開催の会場となるため、登録メンバー紹介の後、理事が「新商品おしゃべり会」の運営や開催留意項目などを説明しました。また、調理・試食後には、商品部の職員から、商品の原材料や製造工程などの説明を受け、意見交換を行いました。
今回試食したのは水産部門の2品。1品目は産直産地・(農)房総食料センターのなすを使用した「いかと茄子のスタミナ炒め(みそ風味)」。 別添のみそ風味のたれを使い、フライパンで簡単調理できます。
メンバーからは「にんにくも入っていないし、『スタミナ炒め』のネーミングを変えるべき」「長く炒めてもいかが固くならなくておいしい」「結構ピリ辛。小さい子には食べさせられない」など、いろいろな意見が出ました。
なお、商品名は後日「いかと茄子の辛味噌炒め」に変更になりました!
2品目はたれと冷凍山いもが添付された「三陸産山かけめかぶ」。「日持ちするので、常備したい」「たれの袋は開け口が分かりやすかったので、山いもの袋も同様にしてほしい」などの意見が出ました。
大田センター会場は新しいメンバーが多かったにもかかわらず、大変活発な意見交換ができました。
メンバーの意見が商品名に反映されるなど、商品活動のやりがいも感じながら新年度の活動が始まりました。

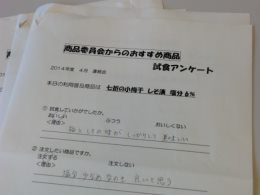
 >
>

















