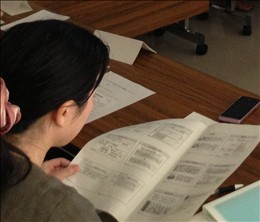商品活動
わたしのこだわり朝ごはん
組合員と㈲匝瑳ジーピーセンター、アイケイ食品㈱、茨城乳業㈱、信州ハム㈱、㈱ナガノトマトが試食&交流
大勢の参加者でメーカーの説明にも |
参加者から質問が相次ぎました |
試食・交流で組合員と生産者との |
産地・メーカーの方々との交流・試食を通して地域の組合員に商品への愛着を深めていただき、新しい参加者や活動地域などを増やすことが目的です。
この日、参加者はなんと56人! 交流の場では産地・メーカーの方々と心おきなく話をし、クイズなども行って大盛況。
参加団体からは「商品を知ってもらえる企画は、メーカー側としてうれしい」、参加者からは「各メーカーの生の声が聞けた」「食品の安全・安心への配慮についても強く認識できた」との感想が聞かれました。大変満足度の高い企画となりました。
また、今回は第1地域委員会が依頼した組合員活動のサポーター2人が、運営のお手伝いを担当しました。
サポート初体験の1人は、「主催者とともに準備から関わることができ、良い経験になりました。心地良い疲れと達成感...次にお声が掛かるのが楽しみ!」と前向きなコメント。サポーターは1人からでも組合員活動に参加できるシステムです。
登録すると、企画ごとに開催日当日のお手伝いをお願いしています。準備・片付けなどに携わるため、企画の流れが分かります。1年ごとの登録なので、活動したいと考えている皆さんに登録をお勧めします。
アレルギー対応♥おしゃれな米粉カフェ
米粉を使っておいしく楽しく、アレルギー対応メニューを考えました
焼きたてスコーン |
各班で調理開始 |
同じ悩みを共有できました |
本日のカフェメニュー完成 |
東都生協のアレルギー対応について学ぶ会は2014年11月6日、「アレルギー対応♥おしゃれな米粉カフェ」を開催。
参加者は家族やご自身がアレルギーがあるため、共通の話題ですぐに打ち解けました。
委員考案のレシピ「ケークサレ」「シフォンケーキ」「キッシュ」「スコーン」「ミートパン」「パフェ」の調理をしながら、日ごろ気を付けていることを話したり、アレルギー相談室の武内職員に尋ねたり、と和気あいあいでした。
「保育園の懇親会向けに、小さな子どもからおとなまで安心して食べられる差し入れを作りたい」「学校給食にどう対応したか、先輩に聞きたい」「アレルギーがあるが、かわいいおやつを作ってみたかった」と参加理由はさまざまですが、「コンソメの原料にアレルゲンがある場合は、うまみとコクを出すのに『塩麹』を使う」「生クリームの代替えに『豆乳グルト』を水切りし『油とグラニュー糖』でホイップする」など、調理の工夫を委員から伝授されました。
「同じ悩みを共有できてうれしい」「知恵を凝縮したレシピに幸せを感じた」「米粉の奥深さ、卵の代わりにかぼちゃパウダーでおいしく見せるという細かな愛情に感動」「7大アレルゲンを排除してもおしゃれなパーティーメニューになり、びっくり!」と、みんな大満足。
試食交流では地域での新しい仲間づくりのきっかけにつながる声もたくさんあり、アレルギーを持つ子が安心して暮らせる環境づくりへの期待がますます強くなりました。
「新商品おしゃべり会」町田会場報告
組合員が新登場前の商品を調理・試食し、評価する活動
実地で調理方法を確認 |
調理して商品の状態を確認 |
調理しやすさも重要なポイント |
今回提案されたのは、「さんまのつみれ汁」と「北海道産秋鮭のポテト焼き」。どちらも冷凍品の試食となりました。
「さんまのつみれ汁」は、つみれ材料としてはなじみのないさんまが原材料で、青魚特有の臭みが心配でしたが、「食べやすくスープも付いて利用しやすい」という意見にまとまりました。
「北海道産秋鮭のポテト焼き」は、揚げ立ては鮭の味が、冷めるとポテトの味が引き立つなど、時間差で味が楽しめます。またお弁当サイズで、冷めてもカリッとしている点も好評でした。「8切れ入りを4切れ入り、または4切れ2パックにはできないか?」との委員の声に、商品部職員からは「多様なニーズがあるので、これからの提案に生かしていきたい」とのコメントがありました。
夏休み中の開催でしたが、保育付きなので小さい子どもがいる委員も安心して出席できました。
(農)佐久産直センター視察訪問を実施しました
農薬・化学肥料に頼らない、冷涼な気候を生かしたおいしい作物作りを確認しました
園地の視察 |
質疑応答 |
産地の概要説明 |
選果場の視察 |
視察訪問企画は、東都生協の扱う商品について生産現場や関連する施設を視察することにより、東都生協との約束事、それを守るための仕組み、その仕組みの運用実態、産地・メーカーの特徴的な取り組みなどを組合員自らが確認するという目的で行っています。
現地では、最初に桜井さんの園地を視察。「ふじ」「あいかの香り」の説明を受け、栽培方法の確認をしました。
次に、(農)佐久産直センターにて産地の概要説明。今年の大雪での施設被害の報告や、りんごのひょう被害に対する支援へのお礼の後、殿様ねぎ・モロッコいんげん・りんご・プルーンの取り扱いについて説明を受けました。
続いて選果場を視察し、選果の仕方や箱詰め方法を確認しました。
その後、野元さん・関口さんの園地を視察。「紅玉」「ふじ」「シナノゴールド」の降ひょう被害について説明を受けました。
最後に直売所を訪問し、(農)佐久産直センターの商品を購入し帰途に就きました。
園地を2つ回ったことで予定よりも時間がかかってしまいましたが、参加者は熱心に生産者の話を聞いていました。
(農)佐久産直センターでは、今年2014年は6月16日、8月7日、9月11日に降ひょうの被害があり、りんご(紅玉)の生産量の4割が被害を受けました。東都生協での「つがる」「紅玉」のフルーツサポート支援企画に感謝の言葉がありました。
参加者からは、
「参加人数が少数だったのでまとまりがあり、楽しく視察ができました」
「産地に直接出かけて生産者の方々と直接交流ができることにこそ、産直の醍醐味があると確信しました」
「東都生協の安全を確認できました」
「ひょう害に対する支援企画をもっと実施すると良いと思いました」
などの感想がありました。
信州ハム㈱の視察訪問を実施しました
無塩せきハム・ソーセージを製造して40数年。おいしさと安全性を追求した商品作りを確認
会社の概要説明 |
工場施設の視察と質疑応答 |
工場内製造現場の視察 |
視察訪問お疲れさまでした |
視察訪問企画は、東都生協の扱う商品について生産現場や関連する施設を視察することにより、東都生協との約束事、それを守るための仕組み、その仕組みの運用実態、産地・メーカーの特徴的な取り組みなどを組合員自らが確認するのが目的です。
現地では、最初に同社の工場長が会社概要と取り組みを説明。
信州ハム㈱が、無塩せき(発色剤・亜硝酸ナトリウムを使用しない)、保存料不使用の商品を作り始め約40年であることや、東都生協向けハム・ソーセージには国産豚・南国元気鶏を使用していることなど、製品作りへのこだわりを確認しました。
昼食を兼ねた信州ハム㈱製造商品の試食およびプレゼンテーションでは、「わたしのこだわり東都ロースハム」ときのこのサラダ、「わたしのこだわり東都ベーコンスライス」のベーコン白菜鍋、「焼いておいしいソーセージ」を試食しました。
次に、見学ロビーより、工場内の製造現場を2班に分かれて視察。原材料の入荷から製造、箱詰め、出荷まで一貫した生産システム「Iライン」によって製品の安全性と品質保証にしっかり対応されていることなどを確認しました。
参加者からは、以下のような感想が寄せられました。
- 自然環境に恵まれた中で、商品1つ1つが愛情込めて丁寧に作られている様子が伝わり、ぜひとも今後もその姿勢を維持していただけたらと願っています
- 無塩せきハムのメーカーとして着実に成長している姿は頼もしかった。対応してくださった社員の皆さん全て人柄が良く、働きやすい良い会社なのだなと思いました
- 徹底した品質管理の元に、あのおいしさができていると感じました
- 工場見学、料理教室、幼児対象にランチパーティー他、イベント活動に積極的に取り組むなど、支援活動を通して社会貢献していることを知り、自信を持って製品を提供している一つの表れで好感を持てました。製品に対して購入意欲が高くなりました
- 「今回の企画に参加したことで、何が大切なのかを知り、食や日本の未来について考える良い機会となりました
(農)房総食料センター視察訪問を実施しました
安全でおいしい産直青果の生産に向けた、土づくりや栽培管理などの取り組みを確認
品目別栽培カードに関する説明 |
山田集荷場の視察 |
施設の視察と質疑応答 |
農地の視察と質疑応答 |
視察訪問企画は、東都生協の扱う商品について生産現場や関連する施設を視察することにより、東都生協との約束事、それを守るための仕組み、その仕組みの運用実態、産地・メーカーの特徴的な取り組みなどを組合員自らが確認するという目的で実施しています。
現地では、最初にDVDによる産地概要の視聴。続いて同産地の方よりプレゼンシートに沿って、産地の概要、栽培のこだわり、産地と消費者と生協職員の顔の見える関係づくり、農産加工品へのチャレンジ、若手生産者からベテランの"匠"生産者に至るまでの新しい販売チャレンジ、さまざまな交流活動などについて説明しました。
また、「品目別栽培カード」について、作付け計画、栽培品目、生産者栽培報告書、出荷予定割り振りなどについての説明もありました。
昼食後はバスで移動し、主に根菜類を取り扱っている山田集荷場と生産者の農地の視察を行い、質疑応答を行いました。
参加者は少人数でしたが、その分、視察訪問での産地の状況や概要説明に関してもじっくり聞き入ることができ、東都生協の職員を含め、産地との質疑応答を積極的に行い、産地についての知識を一層得ることができました。
産地と東都生協の産直のつながりや取り組みなどについての理解が深まった、密度の濃い視察訪問となりました。
参加者からは、
「産地を実際に訪れることによって、生産者がどのように栽培し出荷しているのかが目で見て実感できた。今後、商品案内書に掲載されれば、ぜひ購入したいと思う」
「(農)房総食料センター婦人部の方々による手作り料理での昼食のおもてなしが、とてもありがたく、とてもおいしかった」
「和やかに意見交換できるので質問がしやすい。今回も参加して東都生協の野菜は本当にこだわりがあり安全であることを再確認できてよかった」
「ある程度知っているつもりでも、現地に行かないと分からないこともあると思った。若い人が頑張っていることが分かって良かった」
などの感想が寄せられました。
「新商品おしゃべり会」 江戸川会場報告
毎月1〜2品の提案商品を組合員目線で調理・試食・評価し、改善意見を出す商品作りの活動
資料を基に活発な意見交換中 |
きゅうりが丸ごと1本入ってます |
今回の提案商品は、「本醸造醤油でじっくり漬けた国産きゅうりの一本漬け」と「いか揚げ」。2品ともあまり調理の必要がないため、評価し合う時間を多く取り、活発な意見交換が行われました。試食する商品の味、食感、成分についてそれぞれの意見があり、同じ商品でも味が「濃い」「薄い」という議論を行います。
この日のきゅうりの一本漬けも、「これだけ漬け込む必要があるのか」「1本といっても小さく感じる」「ポリポリの食感は良いが、味が濃い」と辛口の評価がある一方で、「市販はもっと味が濃く、添加物も多い」と市販品との違いを評価する意見もありました。
いか揚げについては、「これはいかというよりゲソ揚げでは?」「おいしい」「お酒に合いそう」といった意見が出ました。「ゲソが同じ長さだけど、長い触手の2本分はどこにあるの?」という質問には、一同大笑いでした。
評価が高い商品は、「商品案内に出るのが楽しみ、 もっと早く出してください」と要望するメンバーもいます。 毎回和気あいあいで、 笑い声の絶えない江戸川会場からの報告でした。
*新商品おしゃべり会
新商品に組合員の声を生かす商品づくりの活動。毎月、新商品・開発中の商品について原材料や製造方法を確かめて試食し、味や包材、調理法などを評価します。改善意見は商品部で受け止め、改善結果は商品活動を取りまとめる商品委員会へ報告されます。今年度は、江戸川会場、大田会場、調布会場、町田会場、城西会場で開催
アレルギー対応について学ぶ会「アレルギー表示と食品添加物」を学習
新メンバーも交え11月の米粉調理講習会について検討
11月に予定する米粉調理講習会 |
熱心に講義に聞き入ります |
事前に出し合ったレシピで試作品を作ってきたメンバーもいて、メニュー決めから大盛り上がり! 主食系のケークサレ、キッシュ、ミートパイ、デザート系のスコーン、パフェ、シフォンケーキの6品目について、3チームに分かれてメニューを絞ることになりました。
その後のミニ学習会では、安全・品質管理部の武内澄子職員が「アレルギー表示と食品添加物」について講義。
商品表示に関する法律から、表示されなかったために起きた事例や今後の表示改正について、食品添加物とアレルギーの関係など、40分という短い時間で盛りだくさんの内容となりました。
次回のミニ学習のテーマについては、「食品の酸化、油脂の度合いについて」に決定しましたが、メンバーから「災害時のアレルギー対応、備蓄について知りたい」「東日本大震災で実際どうだったのか...」など震災時の備えを知りたいとの声もありました。
最後に新商品の「ぱりまる カレー」を試食して会は終了しましたが、退室後も調理講習会のチームごとに早速打ち合わせをする熱心さでした。
「新商品おしゃべり会」調布会場報告
組合員が新商品を企画前に試食し、評価する活動「新商品おしゃべり会」を今年度は5会場で開催中
評価とお薦めコメントを記載します |
商品部職員から提案目的や商品の説明を受けて、組合員全員が質問・意見を出した後、「おいしいと感じたか」「注文したいか」の評価と、お薦めコメントを記入します。人によって嗜好はさまざまなため、提案商品の選択に担当職員が頭を悩ませることもあるそうです。
評価表は集計し、商品委員会に提出されます。また、商品評価には、原材料や製造工程などの商品仕様が記載された「商品ガイド」を参考にしますが、評価後に回収し、機密情報として管理されています。
今年度からは活動費の支給に代わり「わたしのこだわり」から毎月1品、利用促進商品が試食品として提供されています。試食品を提供した翌月には、前月の試食品についての感想や意見を集めます。
「食べたことのないものが試食できてうれしい」「すでに気に入って購入しているので、友人にプレゼントして試食してもらった」というメンバーもいて「わたしのこだわり」の利用普及にも役立っています。
2014年度も組合員が参加した商品づくりを推進
全ての組合員に商品活動への参加・参画を呼び掛けています
2014年度も、東都生協の組合員による「新商品おしゃべり会」「アレルギー対応について学ぶ会」と、組合員や役職員による「商品委員会」がスタートしました。
「新商品おしゃべり会」は、毎月、新商品や開発途中の商品について組合員が原材料や製造方法を確かめて試食し、包材や調理法までを評価して改善意見などを出し合い、商品委員会につなげる活動です。今年度は、江戸川会場、大田会場、調布会場、町田会場、城西会場として5つの配送センターを拠点に開催しています。
「アレルギー対応について学ぶ会」は、本人または家族に食物アレルギーのある組合員が気軽に集い、情報交換や食物アレルギーに考慮した商品について意見交換を行う場。立川会場(多摩消費生活センター)と飯田橋会場(東京都消費生活総合センター)で隔月開催をしています。
「商品委員会」は、商品事業が組合員の声に応え、基本方針・政策に沿って行われているかを評価・提言する役割を担います。毎月の委員会では、業務組織で提案した商品について、新商品おしゃべり会・商品モニターなどから届いた声を考慮しながら確認します。
商品委員会委員は、地域での商品活動を推進し、社会情勢の変化や最新の科学的知見などを受け、見直し・再評価が必要な東都生協の商品の考え方・基準について提言も行います。
この他に組合員なら誰でも参加できる「視察訪問企画」があります。組合員が自ら取引産地・メーカーを訪問し、商品について安全・安心を確かめ、産直の取り組みなどについて理解を深めます。視察訪問企画は、組合員に配付している組合員活動情報紙「ワォ」で募集します。参加者は視察後、良かったこと、気になったことなどの報告書を提出し、商品委員会で確認します。
さらに「商品モニター」「ひとこえ生協」「おすすめコメント」からの意見も商品事業に生かしています。組合員の皆さまも、ぜひできる活動ご参加ください。