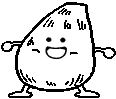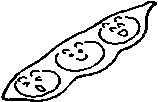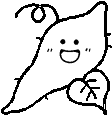食と農
噂の安部さんが食品添加物を語る
「食品の裏側」の著者・安部司さんが講演
添加物を混ぜるだけの |
2006年10月17日、渋谷区立商工会館で、「食品の裏側」の著者である安部司さんを招き、仕入委員会と食と農委員会共催で学習会が開かれました。参加者は252人。
「添加物の神様」といわれる安部さんが、食品添加物とは何か、何のために使われているのか、食品添加物がまん延している現状とそれに対して私たちが何を選んでいけばいいのかを、実験を交えながら警告を込めて話されました。
私たちは、食品を選ぶ基準に「安全・安心」を一番に挙げますが、食品添加物が一向に減らないのは、実際は「安さ、簡単、便利、美しさ、味が濃い」を求めている私たち消費者がいる現状があるから。
この5つの基準で選ぶのであれば「無添加」はありえない。たとえば売れ筋のコンビニのサンドイッチやおにぎり。
裏を返して食品表示を見れば、聞いたことのないような物がたくさん書かれています。その一つひとつが何であるか、その安全性がどうかを知ることよりも、聞いたことがないものが書いてあるときは、「変だな」と思い、買うのをやめればよいのです。
買う場合は、食品添加物が使われていることを「知って」それでも食べるという判断を自らがすればよい。自分で選ぶ力を付けることが大切、というお話でした。
東都生協からは、「設立以来、不必要な添加物を使わない」との原則に基づいて商品の取り扱い基準を定めていることを商品部から説明。「食と農委員会からも食のあり方を見直す食育活動に力を入れていく」との報告がありました。
私たちへの「食の警告」とともに、「賢い消費者になってほしい」というメッセージが込められた講演でした。
食と農通信 「これが 旬。 里いも!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年11月-(2)号より
|
里いもの皮をむくと手がかゆくなる人は、表皮の泥汚れを洗い落とした後、完全に乾かしてからむくか、塩を付けながらむきましょう。
料理例 ★里いものでんがく(4人分)
1. 里いも(8個)は皮をむき縦半分に切り、2〜3分ゆで、もみ洗いをしてぬめりを取る。
2. だし汁2カップ・みりん大さじ1・しょうゆ小さじ1・塩少々を鍋に入れ、(1)を10〜15分煮含める。
3. (2)が煮えたら水分をよく切り、金網でこんがり焼く。
4. 赤みそ大さじ7・酒大さじ2・みりん大さじ3・砂糖大さじ3とだし汁を合わせて火にかけ、とろりとするまで煮つめる(田楽みそ)。
5. (4)の田楽みそを焼けたいもに塗る。
12月2回企画「里いも」
108 400g前後
109 700g前後 徳用
ぜひご注文ください!
東京の農業の実情を学びました
東京の農林業の振興を支える意義を学習
お茶の葉は、蒸し方によって |
2006年9月11日、東都生協の食と農委員会主催により、西立川にある(公財)東京都農林水産振興財団 東京都農林総合研究センターを見学しました。参加者は16人でした。
まず、生産技術科の木曽雅昭さんから、センターの概要説明がありました。新品種の育成や病害虫の総合的防除、食の安全・安心を確保するための技術開発、地域資源を利用した食品開発など、都民に役立つ試験研究が行われています。
その後、東京の農業の現状、特徴と役割、課題などと、それに対するセンターの役割や課題を学習し、センターの中を見学しました。
東京の農家は、ほとんど直接販売などの市場外流通であること、消費地に近いことから若い生産者が出てきていること、そんな人たちを支援し、環境に負荷を与えない農業技術開発に努めていることなど、最も私たちに近い東京の農業を知る良い機会になりました。
食と農通信 「これが旬。丹波黒の枝豆」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年10月-(1)号より
|
枝豆は大豆を若い時期に収穫したもので、大豆と同じような栄養成分があり、大豆にはほとんど含まれないビタミンAやCが含まれます。
京都丹後・丹波地方で栽培されている正月用の黒豆を枝豆として収穫しました。
別名「ぶどう豆」と呼ばれる薄紫色(豆の表面の薄皮が薄紫色)の大粒の豆で、コクのある甘味が特長です。
料理例 ★枝豆のわさび粕漬け おいしい!
1. 枝豆を洗ってざるに上げ、実を出して布巾で水気を拭き、塩をまぶし手でこすりつけて5〜6分置く。
2. たっぷりの熱湯に入れ、少し歯ごたえの残る程度にゆでる。
3. わさび粕床(熟成粕200g、みりん30cc、砂糖30g、塩5g、練りわさび大さじ2)を練り合わせて作る。
4. (3)のわさび粕床に(2)の枝豆を混ぜる。
5. 熱湯で殺菌したびんに詰めて密閉し2〜3日置く。
粕ごと食べられる。(賞味期間は冷蔵庫保管で2カ月ぐらい)
食と農通信 「これが旬。柿!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年9月-(2)号より
|
料理例 ★柿と大根のなます
1. 大根(80g)は長さ6cmぐらいに千切り、柿は種を取り、薄いくし型に切る。
2. 大根、柿は別々に塩(少々)を振る。大根はしんなりしたら水気をきつく絞る。
3. 下漬け用の材料(酢:1/2カップ、だし汁:1/2カップ、砂糖:1/4カップ、塩小さじ1)を容器に入れて、「2」の大根を加えて4〜5時間漬ける。
4. 「3.」の汁をきつく絞り、柿と本漬用の材料(酢:1/3カップ、だし汁:1/2カップ、砂糖:大さじ3、塩小さじ1/2)を加えて好みの味になるまで漬け込んで出来上がり。
食と農通信 「これが旬。さつまいも!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年8月-(2)号より
|
料理例 ★ つまいもの茶きんしぼり 甘くておいしい!
1. さつまいも(400g)は皮をむき、2cmの厚さに輪切りにして水に漬ける。
2. 軟らかくゆでて、熱いうちにうらごしし、砂糖大さじ2とレーズン(20g)を加える。
3. ラップを用意し、(2)を丸めて上部をギュッと搾る。
9月1回企画「さつまいも」107
お薦め
ぜひご注文ください!
情勢学習会 〜食と農を巡る情勢について〜
食を農に近づけるために、今組合員にできることを考える
2006年6月9日、東都生協は宮村 光重氏(東都生協顧問 日本女子大学名誉教授)を講師に食と農を巡る情勢についての学習会を開催し、組合員11人が参加しました。
今の日本では、他の支出の必要から、食料支出を抑えようとし、安価なもの=輸入食料が増えているという家庭の実態があります。食べるものにお金をかけない世帯が増加し、少子高齢化もあって、食料消費そのものが下がっています。しかも、輸入食料は増加しているため、食料自給率はカロリーベースで40パーセントまで下がっています。
収入を確保できないため、農家では深刻な後継者不足が進んでいます。今の農業従事者は半数以上が65歳以上で、農家が減ると田畑が荒れていき、数年後日本の農業はなくなるかもしれません。
「今までは、農を食に近づけようとしていたが、それが逆に農と食の分離を生む結果になってしまった。これからは食を農に近づけることを考え、産地交流訪問をしたり調理の方法を考えたり、今私たちができることを考え、活動を広げていく必要がある」と話しました。
食と農通信 「これが旬。ルッコーラ!」
組合員活動情報紙 『ワォ』 2006年7月号より
|
料理例 ★ルッコーラとスモークサーモンのパスタ
1. ルッコーラ(80g)はざく切り、玉ねぎ(100g)は薄切り、ニンニクはみじん切りにする。
2. 鍋にお湯を沸かして塩ひとつまみを入れ、フェデリーニ(細めのスパゲッティ、140g)をほんの少し芯が残った状態のアルデンテにゆでる。
3. フライパンにオリーブ油(大さじ4)、ニンニク、半分に割った赤唐辛子(2本)を入れて火にかけ、香りが立ってきたら玉ねぎを加えてしんなりするまで炒める。
4. (3)にゆであがったフェデリーニとゆで汁(おたま1杯)を加えて混ぜ合わせ、塩・コショウで味を調える。火を止めてルッコーラと松の実(からいりしたもの、大さじ3杯)と混ぜ合わせる。
5. 皿にスモークサーモンを2枚敷き、(4)のパスタを盛りつける。
![]()
小松菜を育ててみませんか
機関誌 『東都生協だより』 2006年4月号より
小松菜の蒸しパン作り。 |
プロが作った小松菜に皆ビックリ |
食と農委員会では、食育を「食べ方」「知識」「ものづくり」の3つの視点で考えようと、小松菜の種まき、料理作り、産地交流訪問の連続企画を実施しました。
99人の応募があり、ステップ1では応募者全員に小松菜の種を郵送して育ててもらいました。ステップ2では小松菜を使った天ぷらや蒸しパンなどの料理講習会を開催しました。
ステップ3では(農)埼玉産直センターへ出かけ、畑の見学と収穫体験、生産者の皆さんとの交流を行いました。
企画のまとめとして、参加者の「小松菜観察日記」のコンテストを行い、「東都生協文化祭」で展示しました。シリーズ企画としたことで参加者は継続して、興味を持って活動ができました。