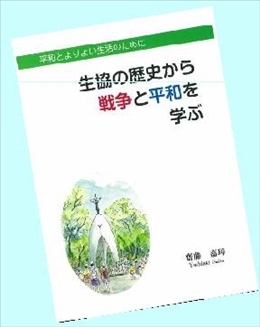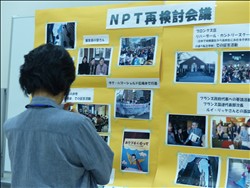平和
齋藤嘉璋さんを講師に「生協の歴史から戦争と平和を学ぶ学習会」を開催
生協がなぜ平和活動に取り組むのか、学びました
齋藤嘉璋講師 |
学習会の様子 |
参加者からは質問も |
齋藤さんは、自らが執筆したブックレット「生協の歴史から戦争と平和を学ぶ」(2016年4月東都生協発行)の内容に沿って講演しました。
日本では1879年(明治12年)、初めて生協が誕生します。イギリスのロッチデール先駆者協同組合に学び設立されましたが、日清戦争の開戦とともに労働組合や農民などの運動を規制する「治安警察法」が制定され、生協は解散に追い込まれます。
齋藤さんは、こうした明治、大正、昭和の時代背景の中で翻弄された生協の歴史とそれに携わった人々について解説しました。
また戦時中は、ものが自由に言える時代ではなかった上、女性の地位も低く、女性だけで集まることさえ禁止されていた時代でもあったと説明。
今回の講演では、単に戦争体験といった視点からではなく、生協がその時代、時代でどのような平和運動を進めてきたかについて、分かりやすく解説いただきました。
参加者からは、「生協がなぜ平和活動をしているのか、きちんと理解できた」「平和活動を進めていく上での指針となった」といった感想が寄せられました。
講演の後は、東都生協の古くからの定番商品「八千代牛乳」「国産丸大豆しょうゆ」「東都もめん豆腐」「東都たまごプリン」の試食も行い、東都生協の歴史にも少しだけ触れました。
"平和なくして生協なし"、平和あってこその生協を実感した一日となりました。
東都生協からナガサキ平和代表団を派遣
被爆者やナガサキの想いを共有し、平和を次世代につなげます
組合員が折った千羽鶴を手向ける |
ガイドの説明を聴きながら碑をめぐる |
日本生協連の虹のひろば |
1日目は長崎到着後、被爆者の方からご自身の被爆体験のお話を伺いました。被爆者の方も高齢化し、被爆体験を直接聴くことができる貴重な時間となりました。
2日目は、生協平和のまち歩きと日本生協連主催の「虹のひろば」に参加。
歩きでは、山王神社周辺をボランティアガイドの説明を聞きながらめぐりました。今も残る原爆の爪痕、原爆の熱線や爆風のすさまじさを感じました。
「虹のひろば」では、長崎市長から「広島・長崎の2つの市だけの話ではなく、全国の皆さんと核兵器をなくす想い、行動を共有していきたい」というメッセージがありました。
続いて、被爆者の手記の朗読や、被爆二世として継承活動を行っている長崎原爆被災者協議会の活動報告、高校生1万人署名活動実行委員会による「高校生平和大使」の取り組みなどが紹介されました。
3日目は長崎市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に参加しました。
参加者からは、
「中学2年生の孫と2人で参加しました。原爆資料館を見せたかったし、被爆者の話を直接聞かせたかった」
「被爆者のお話の中で最も心に残ったのは『お母さんの優しい手、お父さんの温かいまなざし、友達との会話、好きな人の笑顔...その全てを奪い去ってしまうのが戦争です』という言葉です。これを聞いたときに私は初めて鮮明に戦争の残酷さを思い知りました」との声が寄せられました。
参加者は、原爆の実相を学ぶとともに戦争の悲惨さを肌で感じ、平和への思いを新たにしました。
今回のナガサキ平和代表団の派遣には、組合員からお預かりした平和募金を活用させていただきました。東都生協は、安心して暮らせる平和な世界を次世代に引き継いていくため、これからもさまざまな活動に取り組んでいきます。
2016ピースアクションinヒロシマ報告
71年前のきのこ雲の下での出来事や高齢化が進む被爆者の想いを学びました
平和記念公園「原爆の子の像」 |
碑めぐりの様子 |
東都生協から参加した組合員・職員 |
1日目は広島到着後、元中国新聞社の記者で入市被爆をした浅野温生(あさの よしお)さんの講演をお聴きしました。浅野さんは原爆投下翌日に広島市内中心部に入りました。その際、市内の惨状を目撃しました。入市被爆者でもある浅野さんはご自身の体験と新聞記者として多くの被爆者を取材し得た、その苦悩について話されました。
2日目は、被爆の実相を伝える碑巡り。平和記念公園内の主な遺構や慰霊碑などをボランティアガイドの方の説明を聞きながら見学しました。
午後は日本生協連主催の「虹のひろば」に参加。全国から61生協1,200人の組合員とその家族、役職員が集まりました。
広島の松井市長のあいさつでは「核兵器も戦争もない平和な世界の実現のために、一緒に考え、行動しよう」との話がありました。
3日目は広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に参加。黙祷を捧げ、組合員が平和の願いを込めて折った千羽鶴を、平和記念公園内の「原爆の子の像」に手向けました。
参加者からは、「広島の現地に来て原爆の遺構や慰霊碑を見学して、原爆の恐ろしさを実感しました」「『平和の維持』は絶対に必要だと思いました」などの感想がありました。
最後に被爆者の方が語る証言の一部をご紹介します。
- 爆弾を落とした相手に対して憎しみが残っているとなかなか証言はできない。未来の皆さんに伝えたいことは-「あんな思いもうたくさん」-ただこれだけ。
- むごたらしい亡骸が散乱するなか必死で逃げました。あちこちから助けを求められましたが、見殺しにしました。水もあげませんでした。助けられなかった後悔が、ずっと抜けないとげのように心に刺さったままです。
- いまでも腕を高く上げるとやけどの跡が引きつって出血してしまう。がんの手術の傷跡だらけの身体です。
- 私たちが求めるのは核廃絶です。根気強くNPT再検討会議に働き掛けます。
つなげよう 子どもたちの笑顔 ~13回 東都生協 平和のつどい~を開催しました
迫力の堀絢子さんの反戦・反核一人芝居に引き込まれました
庭野理事長より開会あいさつ |
理事長があいさつで紹介した書籍 |
原爆雲の記憶を語る東條明子さん |
東友会の皆さまへ膝掛けを贈呈 |
堀絢子さんの一人芝居「朝ちゃん」 |
迫力の舞台に引き込まれます |
「とーと会」ブルーヘブンの展示 |
親子で展示を見ながら |
冒頭、庭野吉也理事長からの開会あいさつでは、戦争体験を伝えていく方が少なくなり、安全保障関連法の成立や憲法改正に向けた動きがある中、あらためて平和の問題について考えることの重要性を呼び掛けました。
併せて、なぜ生協が戦争に反対し、平和の活動に取り組むのか、東都生協発行「生協の歴史から戦争と平和を学ぶ」[齋藤嘉璋(さいとうよしあき)著]に触れ、「多くの組合員が考えていくきっかけに」と訴えました。
一般社団法人東友会の東條明子さんより被爆証言がありました。東京で生まれ、東京大空襲を体験し、疎開先の広島で被爆した東條さん。子どもの目線で語られる当時の様子や、原爆症で苦しむ中で仏門に入られたとのお話に、来場者は食い入るように聞きました。
モチーフ編みを膝掛け作りに取り組むとーと会「ピースニットカフェ」からは、東友会の皆さんにへ膝掛けの贈呈をしました。
東友会の家島さんから「毎年年末に贈られる膝掛けを心待ちにしている」との感謝の言葉をいただき、若い被爆者はいなくなり、東都生協のたくさんの若い後継者と平和活動を一緒に伝えていきたいとお話がありました。
ピースニットカフェの大河内さんからは、「組合員の皆さんから自宅で使わない毛糸を寄付していただき、モチーフを編み、つなげて膝掛けにして作ってお送りしている」と、膝掛けに込められた組合員の思いもお届けしていることを伝えました。
平和をテーマにしたとーと会「ブルーヘブン」は、パワーポイントを使いながら、原発事故での放射線汚染による子どもたの現状と「福島の子ども保養プロジェクト:杉並」について発表しました。
休憩をはさみ、山本真理子氏原作の「広島の母たち」より堀絢子さんの一人芝居「朝ちゃん」を上演。
舞台は原爆投下の翌朝。15歳の少女・秋子がひとりで焼け跡をさまよっていると、 焼け跡の中から全身が焼けただれた瀕死の朝子を見つけ出す。
秋子は、朝子の母を呼んできて朝子と再会させたが、朝子は「水がほしい」と言い続けながら母の手の中で徐々に弱っていく。朝子を早く休ませるために急いで家に向かう3人。そして、そんな朝子の家族を見て、秋子は自分の境遇について思いを巡らせる。
-秋子、朝子、朝子の母と兄、語りの部分と、堀さんは一人5役を見事に演じ分けました。
自分たちがまるでその場にいるかのような錯覚を覚えるほど、原爆の悲惨さが伝わりました。
続く「峠三吉 原爆詩集の序」の朗読では、作者それぞれの心の叫びが聞こえてくるかようでした。
併設された展示会場では「原爆と人間」「第五福竜丸」パネルや「戦争体験文集&平和募金企画参加者感想文集」から体験文、2015年度ヒロシマ・ナガサキ平和代表団の資料、東友会に贈る膝掛け、地雷のレプリカ、とーと会ブルーヘブンによる資料などを展示し、来場者が熱心に見入っていました。
戦争や平和についての絵本やモールのストラップ作り、折り鶴コーナーには子どもだけでなく、おとなも立ち寄っていました。
参加者からは
- 他人事じゃないんだなと思いました。これからはげんばくのことをわすれないでいきたいです(小学生)
- 私はなんにも知らないんだと思いました。私はとっても幸せだと思いました(小学生)
- 平和というものは、続いていくことに意義があると思います。皆さんの努力をお願いいたします。子ども、孫へと続くことを祈ります
- このようなつどいに参加することにより、平和への関心が高まると思います。いつまでも平和な世界でありますように
- 兵士・武器は、いらないと思いました
平和を伝えていくために、忘れてはいけない現実を、私たち一人ひとりが伝えていくことの大切さを実感した一日となりました。
2016 ピースアクション in TOKYO & ピースパレード に参加
東京から世界へ向けて、平和への思いと核兵器廃絶を訴えました
語り継ぐ「ヒロシマ・ナガサキ『あの日』 |
沿道の人たちに核兵器廃絶をアピール |
表参堂から原宿、 |
オープニングは、地域で音楽活動を行っている東都生協組合員のご夫妻、松林良晴さんの歌、松林潤子さんのピアノ伴奏のピースコンサートがありました。
語り継ぐ「ヒロシマ・ナガサキ『あの日』から生きて」では、東友会(東京都原爆被害者団体協議会)に寄せられた被爆者の相談事例を朗読で紹介。あの日を辛うじて生き延びた被爆者たちの心身の苦痛は生涯を通じて続き、その苦痛は計り知れないものだったことが語られました。朗読は各生協で分担しました。
続いて、松井一實広島市長、田上富久長崎市長からのメッセージが、それぞれ代読されました。両市の核廃絶へのさらなる決意と「ピースアクションin TOKYO 」への期待が表明されました。
「参加団体リレートーク」では、5団体が平和活動の取り組みについて発表し、日頃の活動について理解を深めました。
最後に「2016ピースアクションin TOKYOアピール」を東京地婦連(特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟)の山下陽枝さんが朗読し、拍手で採択されました。
続いて行われた「ピースパレード」では、表参道から原宿を通り神宮通り公園までの道のりを、宣伝カーからの平和アピールの呼び掛けとともに歩きました。行進者たちは笑顔で花の種を配りながら沿道の方たちに核兵器廃絶を訴えました。
第33回沖縄戦跡・基地めぐり報告
~現在の沖縄における諸問題や、これからの平和をめぐる課題について考えあう機会となりました~
沖縄の思いを受け止めた参加者 |
長年続く、辺野古新基地 |
辺野古の海 |
1日目はまず全体会が開催され、1944年8月、当時9歳の時に疎開のため対馬丸に乗船し、米国潜水艦の魚雷攻撃を受け船が沈没、6日間の漂流の後、奄美大島の無人島に流れ着き、一命をとりとめた体験を持つ平良啓子の講演。
地元の大学生、城間愛里さんによる「若者から見た沖縄の現状と本土の皆さんに訴えたいこと」の報告がありました。
全体会後、それぞれのコース(基本コース・辺野古・高江コース・親子コース)に分かれ分科会が行われました。
夜には、全国の生協の参加者と一緒に夕食懇親会が行われ、琉球舞踊、エイサーなど沖縄の文化と伝統を楽しみながら交流を深めました。
2日目からは、各コースに分かれ、普天間基地や辺野古などを見学しました。
参加者からは、
「沖縄戦、沖縄の基地問題を知り、沖縄の平和と安全、そして日本の平和を考えるのにとても良い企画でした」
「テレビや新聞で見たり聞いたりしただけでは、実感はなかなか分からないものだと思う。現地に行く、現地の人の話を聞く、そのことがとても大切です」
「とてもよい勉強になりました。ありがとうございます。多くの方々に、より深く沖縄戦や沖縄の現状、課題などを知っていただきたい」
との感想が寄せられました。参加者がそれぞれに沖縄の問題や平和について考える機会となりました。
憲法学者の木村草太さんを講師に学習会を開催
次世代のいのちとくらしを守るために、憲法について学習
講師:憲法学者(首都大学東京准教授)木村 草太さん
日時:2015年11月28日 場所:主婦会館プラザエフ(四谷)
参加者176人。開場30分以上前から行列ができ、また年齢層も10代から80代と幅広く、今回のテーマへの関心の高さがうかがえました。講演の冒頭、庭野吉也理事長の「お忙しい中、快くお引き受けいただき感謝しています」とのあいさつに対し、木村草太さんは「自分も東都生協の組合員であり、責務を果たそうと引き受けました」と話され、参加者との距離が一気に縮まりました。
お話は、身近でユーモアあふれる例えを随所にちりばめながら、日本国憲法について分かりやすく解説。また憲法学の観点から安全保障法制についても触れ、「集団的自衛権の何が問題なのか明確に分かった」「日本国憲法を一度読んでみたい」などの感想が見られ、憲法への関心を高める機会となりました。以下、講演内容と質疑応答を抜粋してご紹介します。
講師の木村 草太准教授
会場いっぱいの参加者
◆憲法と立憲主義
いかなる団体にも規約があり、国家という団体の規約が憲法です。立憲主義とは、国家権力の過去の失敗をリスト化し、同じ過ちを繰り返さないための構想です。過去に国家権力が犯してきた三大失敗とは、「無謀な戦争」「人権侵害」「独裁」。
これに対し「軍事力のコントロール」「人権保障」「権力分立」の要素を憲法に盛り込むことで、国家権力が良い方向に使われるようしようという立憲主義の構想に基づく政治が望ましいということが、今日の国際社会でも広く受け入れられています。
◆憲法改正について
このように憲法は、独裁防止や人権保障など大事な内容を持つため、普通の法律と比べて改正手続きを厳しく定めています。2013年前半、改憲手続きを定めた第96条を改正する動きが出た際に、"外国での改憲手続きよりも厳しい" などの議論がありました。
しかし、例えばフランス憲法では、改正できるのは日本でいう内閣法や国会法など統治機構に関わる部分だけで、フランス人権宣言は200年以上変わっていません。
国によって憲法で定める事項が違うため、改正手続きだけを単純に比較することはできません。国家体制の根幹や人権条項をも規定する日本国憲法では、改正手続きの厳しさも自ずと変わってきます。このため、現在では与野党の広範な合意があって初めて提案ができる、総議員の3分の2という発議要件を課しています。
◆日本国憲法の成り立ち
日本が受諾したポツダム宣言は、民主主義を復活・強化し、人権保障を確立することを求めるものでした。日本政府とGHQ(*)との話し合いの中で、ポツダム宣言の条項を実現するには大日本帝国憲法の改正が必要と一致。
そこで日本政府は当時の国務大臣を中心に憲法改正案を作成したところ、この案があまりに保守的なためGHQが草案を作成。それを翻訳していく過程で二院制を置くといった日本政府の希望も盛り込まれ、口語訳の日本国憲法改正草案ができました。そして第90回帝国議会(最後の帝国議会)で、初の男女平等普通選挙のもとで選ばれた議員によって議決されたのです。
*連合国最高司令官総司令部:第二次世界大戦後の1945年から1952年にかけて、日本を占領・統治した連合国の機関。
◆戦争放棄・平和主義
憲法第9条は、戦争の放棄、武力行使の放棄と、軍隊・戦力の不保持から成ります。これだけを見ると、個別的自衛権の行使も9条によって禁止されているように思えますが、歴代日本政府は、人権保障を定めた最も重要な条文「第13条」を根拠に、9条の例外として個別的自衛権の行使が認められるという解釈をしてきました。日本が侵略や攻撃を受けた時に、日本政府には国民を守る義務があるとするのです。
しかし、集団的自衛権の行使を認める根拠となる、外国政府を守る日本政府の義務について定めた条文は、日本国憲法には存在しません。また、政府・内閣は国民が憲法を通じて負託した権限、つまり第73条に列挙された権限しか行使できません。
個別的自衛権の行使は防衛行政として行政権に属し、その責任は政府にあるといえます。しかし、集団的自衛権の行使は外国同士の紛争に介入するのですから、国内作用である行政権には含まれません。
また、外交は他国の主権を尊重し対等の立場で行うものですが、集団的自衛権の行使は他国の主権を制圧・無視して行うものですから、外交にも含まれません。
集団的自衛権の行使は、政府に与えられていない軍事権に当たる行為と評価せざるを得ません。よって集団的自衛権の行使は越権行為であるという理由で違憲になります。
◆質疑応答
Q:自民党の憲法草案についてのご意見をお聞かせください。
A:自民党の改憲草案には、政府の権限を強くして、国民の権利を制限する傾向がありますが、それを望む国民は、復古趣味的なごく一部の人たちのみでしょう。憲法は、国民が政府に守らせるものですから、改正案は国民の間から沸き上がるものでなければならないと思います。
Q:集団的自衛権行使は違憲というルール違反なのですから、訴訟で現政権を何とかできないのでしょうか。
A:日本の訴訟制度では実際に集団的自衛権が行使されない限り、裁判所はそれが合法か違法かを判断できません。私としては行使する前から憲法判断を仰げる訴訟制度を作ろうと呼び掛けているところです。
Q:日本国憲法と日米地位協定ではどちらが上でしょうか。
A:日米地位協定は条約なので、憲法の方が優位です。日米地位協定が憲法違反の形で運用されたり、日米地位協定に憲法違反の部分があれば無効になります。
「憲法学習会~未来の子どもたちのいのちとくらしを守るために~」
首都大学東京准教授の木村草太氏を講師に憲法学習
憲法学者(首都大学東京准教授) |
当日の参加者は176人で、10代から80代以上の方まで、幅広い年代の方々が参加しました。
講師には憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏をお招きし、憲法と立憲主義、憲法改正、憲法の成り立ちなどについて講演いただきました。
木村氏は「憲法とは『無謀な戦争』『人権侵害』『独裁』など国家権力の過去の失敗をリスト化し、そうしたことを繰り返さないようにするために構想されたものです」と述べられました。
参加者からは、
「難しいと思われる憲法ですが、分かりやすい事例を挙げられて興味を持つことができました」
「歴史的な背景についても触れていただき、より理解が深まりました」
「自分でできることは何か考えて行動していきたいと思います」
「今日の先生のお話を広げていきたいと思いました」
などといった感想が寄せられました。
また、10代の参加者からは、
「学校で習う憲法はあまり詳しくないので、今回の講義で9条のことも含め、良く分かりました。学校では憲法を変更することについて習いません。今日来て本当に良かった」などたくさんの感想が寄せられました。
今回、憲法に興味・関心を持てる機会となり、未来の子どもたちに平和な社会をつなぐための学習機会となりました。
第12回 東都生協平和のつどいを開催しました
~戦後70年 つなげる平和への思い~
庭野理事長より開会のあいさつ |
東友会 堀場和子さんによる被爆証言 |
黒坂黒太郎さん、矢口周美さんによる |
奥田幸恵さん(組合員理事)による報告 |
東友会 家島昌志さんによる報告 |
展示コーナ |
被爆者の方による証言、NPT再検討会議の生協代表派遣団や被爆者の活動報告、組合員から寄せられた平和メッセージや平和カルタの展示のほか、コカリナ奏者の第一人者・黒坂黒太郎さんと矢口周美(かねみ)さんのうたとオートハープによる「コカリナとうたのコンサート」上演を行いました。約120人が参加しました。
冒頭、庭野理事長からの開会のあいさつでは、「今日、平和の大切さをかみしめて、戦争は二度と起こさないという思いを皆さまと一つにできればと思います」と呼び掛けました。
この後、一般社団法人東友会の堀場和子さんに、ナガサキでの被爆体験をお話しいただきました。
続いて、黒坂黒太郎さん、矢口周美さんによる「コカリナとうたのコンサート」を上演。黒坂さんの楽しいトークとコカリナの繊細な音、透き通る歌声、そしてオートハープの音色に、来場者は聞き入っていました。
休憩をはさみ、東都生協・奥田幸恵理事、一般社団法人東友会の家島昌志さんより、4月にニューヨークで開催されたNPT再検討会議での活動について報告。
併せて「親子ヒロシマ平和代表団」「ナガサキ平和代表団」「沖縄戦跡・基地めぐり」など東都生協の平和募金企画に参加した組合員に一言ずつ感想をいただきました。
最後は、黒坂黒太郎さんによる「コカリナミニ体験教室」。
呼吸法・音程・音の出し方をお教えいただいた後「なべなべそこぬけ」や「かっこう」を全員で合奏。会場が一体となりました。
会場ロビーなどでは、組合員から寄せられた平和メッセージ(254枚)や、東都生協平和カルタ(53枚)、「原爆と人間」に関するパネルなどを展示。東都平和カルタの優秀作品(11作品)にはプレゼントをお送りしました。
参加者からは、
・コカリナの演奏に興味がありました。戦争を無くすのが理想。まずは核を世界から無くしてほしい。
・戦争は無い方がいい。当たり前のくらしが一番幸せだと感謝している
などの声が聞かれました。
平和の大切さをかみしめ、今私たちはどのようなことをしていくべきなのか、考える一日となりました。
2015年東都生協 親子ヒロシマ平和代表団 報告
ヒロシマ被爆70年の歴史と復興への歩みを学び、平和の尊さを教えられました。
広島城の石垣 原爆の熱線で一部黒く変色 |
組合員が折った千羽鶴を手向けます |
「被爆樹」の前で説明を聞きます |
東都生協ヒロシマ平和代表団 |
「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、広島県生協連・長崎県生協連・日本生協連が、被爆体験の継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として毎年開催。1978年のスタートから、東都生協も毎年代表を派遣しています。
例年、ヒロシマ平和代表団派遣は1泊2日で開催してきましたが、今年は戦後70年という節目の年であるということもあり、ヒロシマの実相についてもっと深く学ぶため、2泊3日の行程としました。
8月4日広島到着後、一行は「碑巡り 広島城周遊コース」に参加。
広島城内には、旧陸軍の第5師団や当時の広島大本営の建物、地下には「防空作戦室」や「通信室」といった軍事施設の戦争遺跡が現存。
普段は入ることのできない「防空作戦室」や「通信室」の内部を地元のガイドの説明を受けながら見学しました。
8月5日は「碑巡り 白神社・袋町小学校コース」、日本生活協同組合連合会主催「虹のひろば」に参加しました。「虹のひろば」は全国の生協の参加者が集う場です。
メインステージでは、被爆ヴァイオリンと被爆ピアノでの演奏から始まり、松井広島市長のあいさつの他、被爆者代表、高校生代表のリレーメッセージが行われました。
また、夜は東京の生協が集う交流会に参加し、被爆者の方の貴重な証言を伺いました。
被爆者の方が、原爆投下当日一緒にいた友人の表情や町の様子などを淡々と話されていました。淡々としたその語り口に、当時の状況が一層リアルに伝わり恐ろしさを感じました。
8月6日最終日は、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に参列しました。
また、東都生協の組合員が折った千羽鶴を平和公園に手向けました。
今年、被爆者の平均年齢は80歳を超えました。年々体験を語る方の人数は減少していきます。より多くの人が被爆地を訪れ、被爆の実相や被爆体験を聞き、継承していくことが大切になっています。