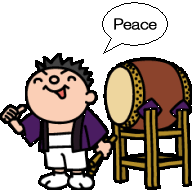平和
核兵器を巡る情勢と廃絶運動の最前線
核兵器を巡る情勢と核兵器禁止条約など核廃絶運動の最前線について学習
一人一人が関心を持ちましょう |
東都生協では「核兵器も戦争もない平和な未来を子どもたちに残したい...」との願いから、核兵器廃絶の署名運動に取り組みました。
これに合わせて、市民団体「ピースデポ」の梅林宏道さんを講師に招き「核兵器を巡る情勢と廃絶運動の最前線」というテーマで学習しました。参加は東都生協組合員8人。
現在地球上には約26,000発の核弾頭があり、これは全人類を滅ぼすのに十分すぎる量です。
核兵器の全面廃絶を義務付けた核不拡散条約が発効したにもかかわらず、米国はじめ核兵器保有国は履行しないばかりか、警報即発射や先制使用も辞さないのが現状です。
そんな中でこれからの核廃絶の道は、核兵器に頼らない安全保障政策への転換と核兵器禁止条約をどうつくっていくかが焦点となります。
核兵器の解体や、核兵器の使用や威嚇が禁止されている非核兵器地帯を広げていくために、自治体や市民社会の役割が大きいこと、そのために市民が声を出して行動していかなければいけないということを学びました。
上野公園で平和を学ぶ
第二次世界大戦の悲惨な記憶を風化させないために
平和委員が交代で説明したり |
2007年11月10日、平和委員会主催の「上野公園親子スタディーツアー」に、あいにくの雨にもかかわらず4組11人が参加。
海老名香葉子さんらが建立した「哀しみの東京大空襲」慰霊碑、核兵器廃絶を願い灯され続けている上野東照宮の「広島・長崎の火」、上野動物園内にある「動物慰霊碑」を回り、平和を祈念して千羽鶴を捧げました。
その後は園内の動物をよく観察しながらのスタンプラリーを行いました。
地下に眠る戦争の遺産
今も残る戦争遺跡で日本の植民地支配と侵略戦争の実相を学習
地元の長野俊英高校の生徒さんに |
実際に地下壕の中に入って見学 |
2007年8月20日、長野県の松代大本営地下壕見学会が行われました。今回は40組・71人の応募があり、東都生協組合員20人が参加しました。
松代大本営とは、太平洋戦争末期、現長野市松代町の三つの山「象山(ぞうざん)」「舞鶴山(まいづるやま)」「皆神山(みなかみやま)」を中心に、善光寺平(ぜんこうじだいら ※長野県長野市を中心とする長野盆地)一帯に分散して作られた地下壕などの地下軍事施設のことです。この日ガイドを務めていただいたのは、地元・長野俊英高等学校(学校法人 篠ノ井学園)の生徒さんたちです。
今回は、象山地下壕(ぞうざんちかごう)の見学をしました。
当時、この地下壕を作るのに、朝鮮半島や中国本土の人々が強制的に連行され、作業に従事させられたことなどの説明がありました。
当時のまま残されている大本営を見学し「平和についてあらためて考えさせられた」という参加者の感想がありました。フェアトレード 〜買うことによる国際協力〜
適正価格で継続的な取引を通じ、途上国の生産者のくらしを支える
講師の話に熱心に耳を傾けていました |
2007年6月14日、渋谷区立商工会館で長坂寿久さん(拓殖大学国際学部教授)を講師に、平和委員会主催でフェアトレード学習会が行われました。
フェアトレードは、途上国の人々が工場や共同組合を作って、自立した民主的運営ができるように支援するNGO運動からはじまりました。
具体的には、環境に配慮し、強制的児童労働などがないように人権に対応し、さらに地域の伝統や資源を活用して継続性のある生産活動ができるように支援して、生産物を公正な値段で買い取って、人々が生活できるようにする活動です。
IFATという国際組織がフェアトレード基準を作り、FLOというラベル認証制度が作られています。
欧州では、コーヒー、紅茶などの食品を中心に貿易量が増えていますが、日本では認知度が低く、取り扱い量も少ないのが現状です。
私たち消費者がフェアトレード商品を活用し、途上国の自立支援、開発協力意識を高めていくことの大切さを学びました。
東京から平和をアピール
核兵器廃絶と戦争のない平和な世界を目指して
行進をしながら沿道の人に |
2007年5月10日、核兵器廃絶と戦争のない平和な世界を目指して「2007ピースアクション in TOKYO & ピースパレード」が行われ、東都生協をはじめ各生協などの団体が参加しました。
午前中は東京ウイメンズプラザ(渋谷)で「2007ピースアクション in TOKYO」が開催されました。歌手横井久美子さんによるピースコンサートの他、参加団体リレートーク、今年亡くなられた伊藤一長長崎市長への黙祷などが行われました。
東都生協からはグループ「麦藁帽子」による朗読劇や、福永喜美代理事が平和の活動を報告しました。最後に核兵器廃絶に向けたアピール案の朗読が行われ、大きな拍手で採択されました。
午後からは、沿道の人たちに平和のメッセージが入った花の種を配りながらのパレードが行われました。各自思い思いのアピールをしながら参加。暑い中での行進でしたが、終点の宮下公園までの約40分間の道のりを、元気よく歩きました。
核兵器の恐ろしさを改めて認識させられたのと同時に、平和アピールの大切さを痛感したピースアクションでした。
東京で平和を大切に守り続ける
世界平和と核兵器廃絶への願い込めた平和募金企画
東都生協も第五福竜丸の |
2007年4月7日新木場駅に11人が集合、まず第五福竜丸展示館前広場で行われている「お花見平和のつどい・2007」に参加。第五福竜丸のエンジンをこの地に移送する運動をした各団体の報告を聞き、展示館内の見学をしました。
建造から60年たった第五福竜丸やさまざまな資料を目の当たりにし、原水爆の惨禍を学びました。
その後東京大空襲・戦災資料センターに移動。米国資料の公開による東京大空襲の実態のNHK番組ビデオを見て、米国が空襲を行った経過を生々しく知ることができました。
説明員の山本唯人さんからは、この戦災資料センターは民間の募金で運営管理されていて、館内に展示されている東京大空襲の資料は市民からの寄贈で集まった貴重なものと説明を受けました。建設のための募金活動には東都生協も協力しました。
次に横網町公園の東京都慰霊堂を見学しました。ここは関東大震災の時に避難した人々が焼死した場所で、震災犠牲者の霊を追悼しています。その後東京大空襲で亡くなられた方も慰霊堂裏の納骨堂に納められました。平和委員の永尾寿孝さんに慰霊堂や東京大空襲の話を聞き、平和を願う一日でした。
オキナワで平和を考える
二度と戦争の悲劇を繰り返さないために
樹木の葉っぱに覆われた |
ガイドの説明に熱心に |
2007年3月27日〜29日、日本生協連主催の沖縄戦跡・基地巡りが開催され、東都生協からは「沖縄を知ろう」コースに4人、「親子で沖縄を学ぶ」コースに1組2人が参加。
1日目は、事前学習として沖縄の生協の方から平和活動・戦争体験談などを聞き、夜は琉球舞踊を見学しながら他生協の人たちと交流しました。
2日目は、戦時中は病院や住民の隠れ場所になった「ガマ(壕)」や「平和祈念資料館」「ひめゆりの塔」などの戦跡を見て回りました。
3日目は、嘉手納町の83%を占める嘉手納基地を「安保の見える丘」から見学しました。
戦争の悲惨さを知るだけでなく、戦争の起こった歴史的背景を学び、二度と戦争の悲劇を繰り返さないために私たちがどうすればいいのかを深く考える機会になりました。
親子で考える「地球の抱える問題」
開発途上国の現状を知り、私たちにできることを考える
ボランティア隊員から |
外国の学校の制服を展示 |
2007年3月29日、平和委員会企画で「JICA地球ひろば見学会」が行われました。
参加者25人は渋谷区にあるJICA(ジャイカ:独立行政法人 国際協力機構)の施設「地球ひろば」を、4つのグループに分かれて見学。
国際ボランティアに参加した人の体験談を聞いたり、貧困に苦しんでいる国の現状の説明などを聞きました。
春休み中だったこともあって子どもも多数参加。「世界の中で、学校に行きたくても行けない子がいるなんてかわいそう」という参加した子どもの感想が印象的でした。
ヒロシマで平和への思いを新たに
親子で平和について考える平和募金企画
渡邉美代子さんより |
春休みに親子で平和について考えてみようと、2007年3月26日〜27日の1泊2日で「2007ピースアクション『親子ヒロシマの旅』」が行われ、7組14人の親子が参加しました。
初日は原爆ドームや、平和記念公園にある広島平和記念資料館・韓国人原爆犠牲者慰霊碑などを平和ガイドの説明を受けながら見学。原爆の子の像へは組合員から寄せられた千羽鶴を供えました。
夜は被爆された方から体験談を伺い、地獄を生き延びた方々の、平和を祈る気持ちの強さを肌で感じた交流会となりました。
翌日は広島市の南にある比治山の陸軍墓地などを訪れました。山頂にある(財)放射線影響研究所の施設を外から眺めた際、「元はアメリカが設置した施設。原爆病の調査が目的だったため、被爆者の治療には一切関わらなかった」というガイドの言葉が非常に印象的でした。
被爆の実相を学び受け継いでいくことの大切さを実感した旅でした。
2006年度の平和募金のご報告
平和な世界を次世代に引き継いでいくために
2006 親子ヒロシマの旅 |
|
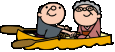
2006年度は、組合員の皆さまより 4,514,113円 もの募金をお寄せいただきました。
ご協力ありがとうございました。
2005年度より2,957,899円が繰り越され、2006年度募金と合わせて、収入合計は7,472,012円となりました。
お預かりした募金を活用した主な活動と支出金額をご報告します。残金6,075,463円は、2007年度に繰り越させていただきます。
2006年度活動報告(支出合計 1,396,549円)
◇親子ヒロシマの旅 (262,844円)
2006年4月2日(日)〜 4月3日(月) 参加9人(うち、子ども4人)
◇沖縄戦跡・基地巡り(293,600円)
2006年10月24日(火)〜 10月27日(金) 参加6人
◇松代大本営地下壕見学会 (79,170円)
2006年7月27日(木) 参加13人(うち、子ども2人)
◇ピースアクション2006 ヒロシマ平和代表団 (307,510円)
2006年8月5日(土)〜 8月7日(月) 参加4人(うち、子ども1人)
◇ピースアクション2006 ナガサキ平和代表団 (353,425円)
2006年8月7日(月)〜 8月9日(水) 参加6人(うち、子ども1人)
◇東京都原爆被爆者団体協議会(東友会)への支援 (100,000円)
1月新春の集い
◎ 2007年度 平和募金企画の予定
・親子ヒロシマの旅 実施済み 2007年3月26日(月)〜 3月27日(火)
・沖縄戦跡・基地巡り 実施済み 2007年3月27日(火)〜 3月29日(木)
・お花見平和のつどい&東京大空襲・戦災資料センターツアー 2007年4月7日(土)実施済み
・松代大本営地下壕見学会
・ヒロシマ平和代表団 8月
・ナガサキ平和代表団 8月
・都内企画(親子平和企画) 10月
・東友会への支援 1月
・3・1ビキニデーへの参加 3月
・戦争体験文集編纂
など