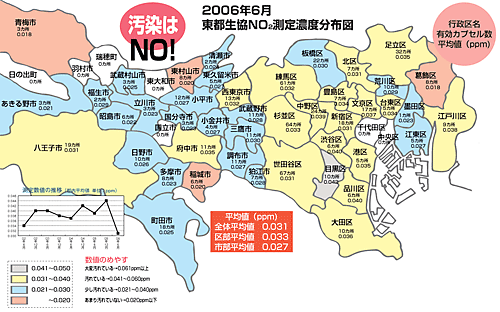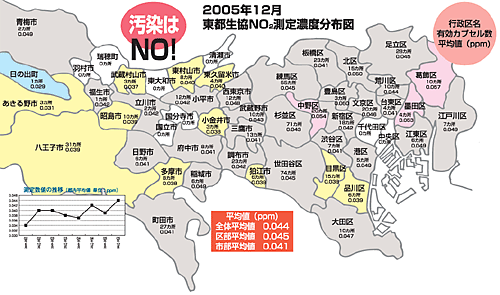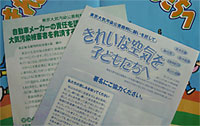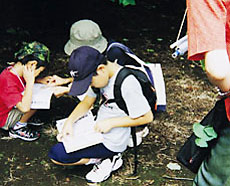環境
2006年6月のNO₂の測定結果
機関誌 『東都生協だより』 2006年9月号より
東都生協(コープ)では、組合員が空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動に取り組んでいます。
年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどを目的としています。2006年6月1日(木)午後6時〜6月2日(金)午後6時の24時間、簡易カプセルでNO₂測定を行いました。その結果をご報告します。
■2006年6月の測定結果は以下の通りでした。
測定日時:2006年6月1日(木)午後6時〜6月2日(金)午後6時
配付数:912個
回収数:613個
有効カプセル数:573個
回収率:67.2%
※環境省が定めたNO₂の基準値は「0.04〜0.06ppmのゾーン、またはそれ以下であること」とされています。
人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。
東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。
測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。
情勢学習会 〜気もちいいロハスな生活してみませんか〜
機関誌 『東都生協だより』 2006年8月号より
2006年6月1日、東都生協は東都生協の環境監査委員長・原 早苗さんを講師に、環境問題に関する学習会を開催。組合員15人が参加しました。
地球温暖化と進化する文明との関係に始まり、世界的な課題や、東都生協での取り組みが話されました。
参加者は、東都生協のリユースびん商品や東都みのり野菜などを利用することがすでにロハス(健康と持続可能な社会に配慮したライフスタイル)な生活を送っていることだと気づかされました。
講師は「自分だけが快適というのではなく、社会へ目を向けてほしい」と話されました。
どうする? 「リユースびん回収率65%」!
機関誌 『東都生協だより』 2006年5月号より
坂井職員から作業工程 |
環境委員会は2006年3月15日、参加者8人でリサイクル洗びんセンターと石川酒造㈱を訪問しました。
「ここは東都生協ときょうされんが作ったリユースびんを洗う工場であり、障害者の働く施設です。リユースびんは洗って繰り返し使うのでCO₂排出量が少なく、地球温暖化防止にも役立っています。ここ何年か東都生協でのリユースびんの回収率が下がっていて、働く人たちの仕事が減っています。リユースびんの良さを見直して利用し、東都生協に返してほしい」と、リサイクル洗びんセンターの坂井俊次氏から工場の案内とともにお話を伺いました。
リサイクル洗びんセンターを利用している石川酒造㈱の北川賢志氏からは、東京の酒造メーカーが統一びんにし、リサイクル洗びんセンターで洗ってもらうという構想を聞き、参加者は「早く実現すればうれしい。まずは、リユースびんの回収率100%になるように伝えていきたい」と話していました。
慣れれば優しい生ごみリサイクル
機関誌 『東都生協だより』 2006年3月号より
庭がなくても、 |
2006年1月13日、環境委員会主催で生ごみの有効利用を広く進めるために「生ごみリサイクル教室」がさんぼんすぎセンターで開かれました。
講師は「NPOたい肥化協会」の会田節子氏と浅井民雄氏。ビデオも交え、プランターやダンボールを使うなど、いろいろな事例でのぼかし肥を使った堆肥の作り方を教えていただきました。
13人の参加者は熱心に聞き、講習会が終ってからも講師の周りには個人的に質問する人の輪ができました。
明かりを消して「100万人のキャンドルナイト2005冬至」
夏至と冬至の午後8時〜10時の2時間、照明を消しロウソクを灯して過ごすスローライフ運動を進めています
東都生協では、環境を大切にする、さまざまな活動を進めています。2005年は6月21日(夏至の日)に続き、12月22日(冬至の日)に環境活動の一環として「キャンドルナイト」に取り組みました。「キャンドルナイト」は、アメリカでのエネルギー政策に抗議する自主停電の運動から始まりました。夜8時から10時の2時間、明かりを消した暮らしを呼び掛けています。
◆取り組みに参加した組合員からの声
--------------------------------
今回も、ろうそくの火をつけて食事をしました。
電気の有り難さを(便利で快適な生活を送れるので)つくづく感じました。実は、うちでは、キャンドルナイトを始めてから夕食の時の、落ちつく感じがとても気に入って、時々、やっています。
電気の有り難みを考える良い機会でもあり、無駄な電気を使わないように気を付けるようにもなりました。
これからも「キャンドルの光で夕食」を続けていこうと思っています。
(調布市 Tさん)
12月のキャンドルナイトには、アロマのろうそくなどたくさん用意しておいて楽しみました。それ以来、夜、茶わん洗いする時などは、あまり明るくなくても良いので、ろうそくを並べて、洗ったりして楽しむようになりました。
(目黒区 Tさん)
外が明るいので(他の家の光ですが)、電気が無くても過ごせました。他の人も地球のことを考えながら過ごしていると思うと、つながっているみたいでちょっと楽しい(でも、外が明るいということは、周りの人はやってない‥?!)。
子どもがもう少し大きくなったらキャンドルをともし、語り合って過ごしてみたいなぁ、と思いました。
(世田谷区 Kさん)
◆参加した職員からの声
--------------------------------
家の明かりを全て消して、8階から外を見て、どんなに街が明るいか見てみました。予想以上に外は明るく、無駄と思われる明かりがキラキラしていました。
防犯上のこともあると思うので、明かりの使い方を家族と話し合いました。
(足立センター M職員)
--------------------------------
2005年12月東都生協NO₂測定結果のご報告
東都生協組合員による二酸化窒素(NO₂)測定活動
2005年12月1日(木)午後6時~12月2日(金)午後6時の24時間、
簡易カプセルでNO₂測定を行いました。その結果をご報告します。
東都生協は1988年から二酸化窒素(NO₂)測定に取り組み、測定結果を「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供しています。この連絡会では生協のほか、さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定の積み重ねが大きな運動を支えています。
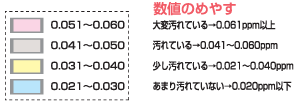
測定日時:2005年12月1日(木)午後6時~12月2日(金)午後6時
配付数:1033個
回収数:701個
有効カプセル数:610個
回収率:67.9%
※環境省が定めたNO₂の基準値は「0.04~0.06ppmのゾーン、またはそれ以下であること」とされています。
探検しよう!! 高尾山
森林インストラクターが、普段では見過ごしがちな高尾山の自然を丁寧にガイド
インストラクターの指す |
2005年11月8日、環境委員会主催「秋の自然環境教室in高尾山」の企画で山歩きをしました。
参加者26人は3つの班に分かれて山頂を目指します。
各班にはインストラクターが付き、山道でのマナーや安全、動植物の生態、周囲の地形などを詳しく学びました。
見て、聞いて、触れて、感覚を充分に働かせながら自然を満喫しました。
「素晴らしい高尾山の環境をこれからも守りたい」「今日はたくさんのことを学びました」などの感想が寄せられました。
「東京大気汚染公害裁判」を支援する署名の報告
東都生協は「東京大気汚染公害裁判」を支援するための署名に...
|
東都生協は「東京大気汚染公害裁判」を支援するための署名に取り組み、936筆の署名が集まりました。
署名用紙の配付対象は、NO₂測定活動の参加者、環境委員、ブロック運営委員や役職員などとしました。
2005年8月31日、集まった署名を要請団体である東京大気汚染公害裁判原告団・弁護団・勝利を目指す実行委員会に手渡しました。ご協力ありがとうございました。
8月26日に「ナゾの木をさがせ! 自然たんけんラリー」を開催
2005年8月26日に実施した"ナゾの木をさがせ!自然たんけんラリー" ナゾの木...
2005年8月26日に実施した"ナゾの木をさがせ!自然たんけんラリー"
ナゾの木の正体は、なんだったのでしょうか?

答え その1【ラ】

答え その2【ク】

答え その3【ウ】

答え その4【ショウ】

ナゾの木は【ラクウショウ】でした。環境学習研究会の先生が説明しています。
とても変わった木です。興味のある方は、図鑑を調べたり、新宿御苑へ来てみてね。
先生の足もとにもラクウショウの木の一部が見えてます。

新宿からわずか10分程度。深い森ような中も歩きました。

とても大きな木もありました。
ご参加ありがとうございました。
日程変更でご迷惑おかけしたことをお詫び申し上げます。
新宿御苑でネイチャーゲーム
機関誌 『東都生協だより』 2005年10月号より
葉の匂いを嗅いで、 |
2005年8月26日、東都生協の環境委員会は「ナゾの木をさがせ! 自然たんけんラリー」を開催。
講師も含めた20人が、都会の真ん中にある森の中で親子でゲームを楽しみながら、自然や環境を考えた1日でした。
匂い、葉、木肌や根など、木についてさまざまなことを発見しました。前日に通った台風が落としたいろいろな枝や実は、珍しいおみやげになりました。