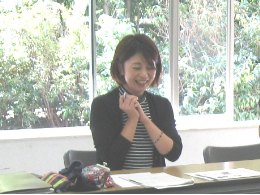魚のこと、もっと知ろう!!
2019年10月16日 豊平ブロック委員会
2020.01.23
千倉水産加工販売㈱の古川信利さん |
魚は皮目から焼くと身崩れしない |
「東都しめさば」で押し寿司作り |
魚は皮目から焼くと身が崩れないなどヒント満載のお話を伺い、「東都しめさば」を使った押し寿司作りにも挑戦。地球温暖化による海水温の上昇や海洋生物への影響など、漁業関連は年々厳しくなってきています。
豊かな資源を残すためにも「今何ができるのか」を考える一日になりました。
夏休み! 親子で鈴廣かまぼこ工場見学!
東都生協 第9地域委員会「鈴廣かまぼこ㈱交流訪問」の報告
2018.08.12



行きのバスの中では鈴廣かまぼこ㈱の学習に加え、食育クイズも行い食への興味につなげました。参加者は全員、自己紹介しましたが、小学生からは「今回の訪問を夏休みの自由研究にしたい」との声もありました。
鈴廣かまぼこ㈱の恵水(めぐみ)工場では、かまぼこを実際に作っている生産ラインを見学し、1本のかまぼこに5~6尾分の魚(グチ)が使われていること、小田原のきれいな地下水がかまぼこ作りに大切なことなどを学習しました。
市販のかまぼことの食べ比べを行い、鈴廣かまぼこ㈱の弾力の違いにみんなで驚きました。
同社イチオシのお薦めは、白かまぼこの「小田原っこ」ですが、実はお正月用と思われがちな「伊達巻」もお薦めです。年間通して需要があり、不定期ながらも企画していますので、商品案内をしっかりチェックして注文してくださいね。
「手作り体験」では、職人さんのようにはうまくできず苦心。小さいお子さんは、お母さんに手伝ってもらいながら最後まで頑張りました。
環境にも配慮し、化学調味料、保存料不使用に徹した本物の味・鈴廣かまぼこ㈱の製品を、皆さんもどうぞご利用ください。
平和募金企画「ユニセフハウスで平和について考えよう!~世界の子どもたちの今~」
まずは知ること、そして考え、自分にできる行動に移すことの大切さを学びました
2018.01.16
組合員など参加者は13人で、そのうち初参加者は1人でした。車内では東都生協の平和活動への取り組みを学習し、その大切さを確認し合いました。
ユニセフハウスには、活動の歴史・子どもの権利条約などのパネル展示のほか、現地の診療所や学校、避難所テントなどが再現されています。また、水瓶や子ども兵士が持つ銃の重さなどを体験できるコーナーもあります。
一行は、ボランティアさんによる1時間半のガイドツアーに参加し、一つ一つ丁寧な説明を聞きながら見学しました。
かつて日本も、第二次世界大戦後には粉ミルクや綿・薬などの支援を受けていました。近年では、東日本大震災の際にユニセフの支援を受けながら日本ユニセフ協会が支援活動を行っています。
「貧困・紛争・自然災害、さまざまな厳しい状況下に置かれた子どもたちの命と健康を守るために、私たちは何ができるのか?」
難しく考えずに、まずは知ること、そして考え自分にできる行動に移すことの大切さを、感じることができました。
私たちは支え合っています。世界の子どもたちが平和でありますように...。ユニセフハウスは品川駅徒歩7分 ぜひ訪問してみてください。
- 【参加者の感想】
- 一歩を踏み出す体験ができました
- 今までは募金して終わりでしたが、訪問して募金の使途や意義がよく分かりました
- 「予防」と「自立」という言葉が印象に残った。自立できるよう支援することが大切だと分かった
真っ赤なトマトに会いに行きました!!
高原露地トマトの里を久保産直会を交流訪問
2018.01.11


生産者の大半は70〜80代と高齢ですが、最年少の伊藤さん(28歳)は、観光で訪れて久保産直会のトマトに出会い、そのおいしさに魅了されて2017年4月、就農者里親制度で仲間入りしたそうです。
また、40代の終わりに脱サラして就農し7年目の高橋さんは、「これからは、若い人に農業に興味を持ってもらうことが大事。若者を支援する制度ももっと必要」と話しました。
昼食交流会では、「久保産直会の高原露地トマト」を初めて味わった参加者もいて、「昔懐かしい味!」「もう他のトマトは食べられない」など感嘆の声が上がっていました。
畑の見学から昼食交流まであっという間の短い滞在時間でしたが、まるで親戚の家に遊びに来たような心温まる雰囲気の、楽しくも懐かしい交流訪問となりました。
「わたしのこだわり」商品にはたくさんのこだわりがあふれている
東都生協プライベートブランド「わたしのこだわり」商品の誕生秘話なども聴きました
2017.06.12
商品のこだわりを学習
テーブルいっぱいに並ぶこだわり商品
第9地域委員会は2017年3月14日、商品事業部の林秀明職員を講師に招き「わたしのこだわり」学習&試食会を開催。誕生秘話を聞きながら商品を試食し、国産原料へのこだわりや作っている人のこだわりに加え、環境に優しい商品であることを確認しました。
参加者からは「東都生協でしか味わえないものを実際に口にすると説得力がある」「食べたことのなかった商品、今度注文してみたい」とうれしい感想が寄せられました。
こだわりすぎて産地・メーカーには苦労もあるそうですが、そこは妥協をしないプロ集団。「毎日口にするものだから安全・安心なものを...」と届けてくれていることに感謝したいものです。
組合員、生産者、メーカーが一緒になって作り上げた「わたしのこだわり」商品。今後もみんなが納得するおいしい商品が誕生するのが楽しみですね。
おいしくてヘルシー、みんな大満足
東都生協の食材を使用して8品目を調理・試食
2017.03.02
作り方も分かり参考になりました |
いずれも有機野菜・雑穀を使用 |
毎年試食会を開催して毎回異なるメニューを作ってきましたが、今回はれんこんステーキ、おからのポテサラ風、手巻き寿司、キャベツとひじきの重ね煮、ミニ玄米ハンバーグ、かぼちゃのサモサ、おからと豆腐の濃厚ガトーショコラなど8品目。
いずれも有機野菜と雑穀を使用し、ヘルシーでおいしい料理が出来上がりました。
参加者は「ヘルシー料理の作り方が大変参考になった」「家でも早速作りたい」と満足そうでした。
委員長の松本桂子さんは、「今年もヘルシー料理を皆さんに満足していただきうれしい。各家庭に戻ってぜひ実践してほしい」と語っていました。
(株)ニッコー訪問で加工食品へのこだわりを実感
国産原料にこだわり、素材の良さを生かした安全・安心な商品作りを学びました
2017.01.04
㈱ニッコーの自社農場を視察 |
来年再訪門したいとの声も出ました |
従業員の皆さんに笑顔で歓迎いただき、工場見学では熱意を感じる担当の青柳さんの説明、社長の奥様が準備された試食会に至るまで、全てにアットホームな雰囲気がとても印象的でした。
試食・交流の後は原材料の一部となる野菜を栽培する自社農場を見学。ここでは加工した際に出る野菜くずなどを肥料に利用しています。同社の国産原料にこだわった製品作り、循環型農業の実践をはじめ生産かける思いを実感することができました。
参加者からは「材料の下ごしらえから製造・出荷工程を間近で見て、会社のモットーが良く分かった」などさまざまな感想が聞かれ、主催者は「来年は自社農場に女性農業担当者が入るそうなので、収穫体験に行きたい」と同社への再訪問を楽しみにしていました。
地元で愛されるこだわりのメーカー・㈱ポールスタアを交流訪問
こだわった頑固なまでの職人魂に共感!
2016.09.14
圧巻の充填ライン |
試食しながら交流会 |
説明を聞いた後、白衣に帽子・マスクを装着し、いざ工場内へ...。すぐそばで見学できたソースやたれの生産ライン、充てんラインは圧巻でした!
また、「おばあちゃんの油なすのたれ」「胡麻ぽん」を使ったアレンジ試食会ではみんなおいしいと大絶賛。国産野菜を使用、無添加にこだわった頑固なまでの職人魂に、ますます同社の商品が好きになりました。
交流会では、「ソースのびんはリユースできないの?」と問題提起する場面もあり、参加者の関心の高さを知ることもできました。
萩山ブロックとしてはお膝元(東村山市)の魅力あるメーカーに出会えて大満足。お忙しい中、案内してくださった同社の伊東則昭さん、酒井康博さん、ありがとうございました。
おいしく食べよう「冷凍あさり」
海の環境を守りながら安定供給される国産あさりについて学習&試食
2016.02.08
講師の岩本千秋さん |
あさりづくしの料理 |
国内産冷凍あさりの主な産地や製法を学習した後は試食会。あさりご飯と、委員手作りのおみそを使ったあさりのみそ汁も花を添えました。冷凍あさりをおいしく食べるポイントは、やさしく洗い、冷凍のまま沸騰した鍋に入れること。
旬の3月~5月にパックするから、栄養もおいしさも一年中味わえます。参加者からは「身がふっくらとしておいしい」「使いたいときに使いたい分だけ出せて便利」と人気も上々でした。
ただ、国産あさりもピーク時に比べて漁獲数量は半分以下なのだとか。日本人の食生活に欠かせない貴重な海の幸。ぜひこれからも冷凍庫に常備したいですね。
子どもを災害から守るために、私たちにできること!
女性目線での子連れ・孫連れ防災対策を学びました
2016.01.11
「ママプラグ」設立は3・11被災者 |
防災食品「安心米」「えいようかん」 |
被災地ではどんな問題が起きるか、子ども・孫を守るために必要な対策を考えました。いざというときには想像もつかないこと...。例えば携帯電話が通じない場合、子どもは公衆電話をかけた経験がないと使えないということも起こります。
「電話のかけ方は、子どもに伝えておく大切な情報の一つ」とは、講師のNPO法人ママプラグ・富川万美副理事長の言葉。
さらに、家族で共通ルールを作る、避難場所を事前に決めておく、命を大切にする、の3つが重要とのことでした。参加者からは「体験者のお話が聞けてとても勉強になった」「備えることの大切さを感じた」などの声が聞かれました。