

酢
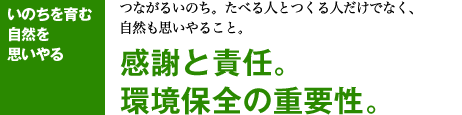
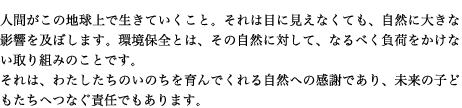

『大正末期には、地元福島県にも十数件のお酢屋さんがありました。しかし、現代ですら難しい酢の製造は、「大きなタンク10本中7~8本成功すればよい」と言われるくらいで、その効率の悪さからほとんどのお酢屋さんが廃業していきました』。そう語るのは太田酢店の太田実さん。
ほとんどのお酢屋は、こうじはこうじ屋から仕入れますが、ここ太田酢店ではこうじ造り、酒造りからはじめています。酒米は契約栽培された新米のひとめぼれ一等米を使用。それに酢酸菌を添加し、約3~4カ月かけて発酵させます。その後、さらに約3~10カ月熟成させることで、ますます旨みと風味がでてくるのです。明治のはじめに開業して以来、太田酢店は伝統の製法を守り、本物の酢をつくり続けています。
ほとんどのお酢屋は、こうじはこうじ屋から仕入れますが、ここ太田酢店ではこうじ造り、酒造りからはじめています。酒米は契約栽培された新米のひとめぼれ一等米を使用。それに酢酸菌を添加し、約3~4カ月かけて発酵させます。その後、さらに約3~10カ月熟成させることで、ますます旨みと風味がでてくるのです。明治のはじめに開業して以来、太田酢店は伝統の製法を守り、本物の酢をつくり続けています。
明治の開業以来、守り続ける伝統の製法

太田さんは語ります。『大量生産・大量消費の時代だから、使い捨てるのではなく、資源を循環させて使うことが大切だと思います。自分たちにできること、そのひとつがびんのリユース。合成酢全盛の今、本来の製法を守ってくれた先代には本当に感謝していますし、びんのリユースを続けている東都生協も立派だと思います。いつまでも頑固に守り続けていきたいですね。』と。

東都生協も加盟、「びん再使用ネットワーク」が、環境大臣賞受賞!
東都生協が加盟する「びん再使用ネットワーク」(※1)が、環境省が2006年度から設けた「容器包装3R推進環境大臣賞」(※2)の「地域の連携協働部門」で最優秀賞を受賞しました。
限りある地球資源を、有効に繰り返し使う持続可能な社会(=循環型社会)をつくろうと、東都生協は設立以来、リユースびんの普及に取り組んでいます。
ペットボトル全盛の時代、リユースびんを使う方が、商品の値段が高くなり、利用の低迷につながりかねません。
しかしそれでもリユースびんを使うのは、自然環境を守る気持ちを強く持っているからにほかなりません。
限りある地球資源を、有効に繰り返し使う持続可能な社会(=循環型社会)をつくろうと、東都生協は設立以来、リユースびんの普及に取り組んでいます。
ペットボトル全盛の時代、リユースびんを使う方が、商品の値段が高くなり、利用の低迷につながりかねません。
しかしそれでもリユースびんを使うのは、自然環境を守る気持ちを強く持っているからにほかなりません。
※1 びん再使用ネットワークとは
環境保全・資源循環型社会の構築をめざした生協団体のネットワークとして、1994年4月に設立。現在、東都生協をはじめ、6団体(合計組合員数190万人)で構成しています。
※2 容器包装3R推進環境大臣賞とは
容器包装廃棄物のReduce(リデュース/廃棄分を少なくする)、Reuse(リユース/再使用)、Recycle(リサイクル/再生資源として再生利用)の3R活動を奨励・普及を図るために、2006年度から環境省が創設したもの。「地域の連携協働部門」「小売部門」「製品部門」の3部門があります。また、今回贈られたロゴマークは、最優秀賞受賞団体だけが使用することができます。
環境保全・資源循環型社会の構築をめざした生協団体のネットワークとして、1994年4月に設立。現在、東都生協をはじめ、6団体(合計組合員数190万人)で構成しています。
※2 容器包装3R推進環境大臣賞とは
容器包装廃棄物のReduce(リデュース/廃棄分を少なくする)、Reuse(リユース/再使用)、Recycle(リサイクル/再生資源として再生利用)の3R活動を奨励・普及を図るために、2006年度から環境省が創設したもの。「地域の連携協働部門」「小売部門」「製品部門」の3部門があります。また、今回贈られたロゴマークは、最優秀賞受賞団体だけが使用することができます。
-
乾物・調味料・加工品
-
産直肉・ハム・ウィンナー類
-
牛乳・卵
-
パン
-
豆腐・納豆
-
その他