

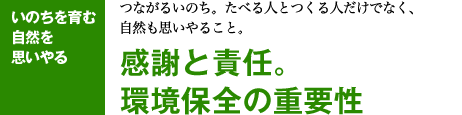
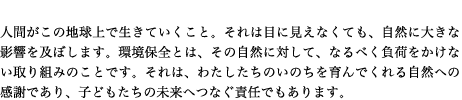

化学合成農薬・化学肥料を使用せずに栽培した「東都みのり」もそのひとつです。そして、商品案内ではすべての青果物に、産地の環境保全への取り組みへの到達点として「栽培区分表示」をおこなっています。
私たちが有機栽培をはじめたきっかけは、にんじんの連作障害が多発し、その対策として強い化学合成農薬を使用するという普及機関・JA経済連への不信からでした。栽培途中に農薬散布をすることは、生産者自体が一番危険であり健康被害が出るということです。
しかし、いざ有機栽培をはじめると除草剤・化学合成農薬などが使用できませんので、雑草が繁茂し作物が雑草に埋まってしまい、当然のことながら害虫が大発生し、手のつけようがないことも多々あり、何も収穫ができないときもありました。
現在は、栽培技術も少しずつ向上し、理解していただける消費者や取引先と産直をおこなう上で大事な契約栽培出荷ができるようになってきました。
私たちの先代の時代には、有機栽培という言葉はなかったように思います。食料の大量生産をするために化学肥料を使い、手段を選ばず結果だけを求めた栽培にいたった。その結果、畑の荒廃がはじまり、自然の循環が崩され農業自体が環境負荷を与えるようになっています。
私たちは、野菜が食卓に並ぶのは当たり前だと思っています。しかし、現状は就農者不足、耕作放棄地の拡大と、国産農産物の生産が危ぶまれています。私は継続して野菜を生産できるのが有機栽培であると確信します。自然界にあるものを循環させる、これが一番であると考えます。土に戻らないものは「生命」が宿っていないのです。
現状の社会を昔に戻せとは言いません。けれど、自然環境は人間だけのものではありません。「手のひらを太陽に」ではありませんが、みみずだって、あめんぼうだってみんな生きているのです。次の代にきれいな自然を渡す義務が私たちにはあります。
生産者にとって、丹精込めて栽培した野菜が皆さんの食卓に並べられることが、いちばんの幸せです。天候に大きく左右される野菜の栽培において、東都生協さんの「サポート」はまさに天の助けと言えます。
他生協では、契約時期と数量が枠にきっちりと組み込まれてしまうため、収穫時期がずれたり余剰にとれた野菜は、出荷調整(産地廃棄)となってしまいます。これでは、契約があるからと作付けしても出荷できないのでは、と生産者は不安になりますが、「サポート」があれれば作付けの際も安心して種を蒔くことができるのです。
組合員のみなさんにしてみれば、夏場はなすやピーマンなどのオンパレード。春や秋は葉物のオンパレードと「あらまた来たの?」と思われるのでしょうが、生産者にとっての「サポート」は、ただ野菜を多く売るためのものではなく、安心して野菜を生産できるシステムのひとつだと思っています。
物価高騰と言われているなか、農産物は30年もの間、価格は上がらず、生産者は農業を継続できるかどうかの瀬戸際です。今こそ地域農業を守っていかなければならないときではないでしょうか。今後も「サポート」を利用する組合員さんが増えて、農家が安心して野菜生産に励めればと思います。
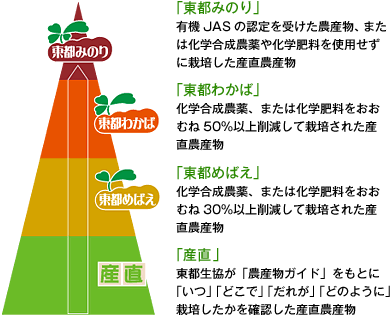
東都生協の農産物は、「いつ」「どこで」「だれが」「どのように」つくったのかが明らかな「産直品」です。
そして、商品案内ではすべての野菜・果物・米に、産地の環境保全への取り組みの到達点として、栽培区分表示がされています。
東都生協が産直をすすめるうえで欠かせないこと、それは「産地との計画栽培」です。しかし、天候不順や注文数量のばらつきなどから、計画どおりに出荷できるわけではありません。また、産地では余ったときだけ市場に出すということもできず、そのまま畑に残ってしまうのが現状です。 東都生協の産直青果物サポートは、「大切に育てた青果物を余すことなく組合員に届けたい」という生産者の気持ちと、「愛情込めてつくられた青果物をむだなく利用したい」という組合員の気持ちから生まれました。 商品案内4ページにて毎回、同じ注文番号でご案内しています。
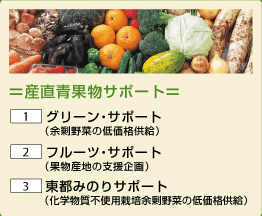
-
乾物・調味料・加工品
-
産直肉・ハム・ウィンナー類
-
牛乳・卵
-
パン
-
豆腐・納豆
-
その他