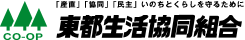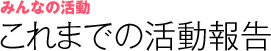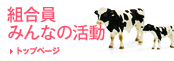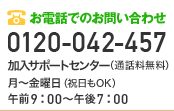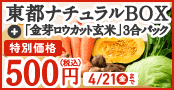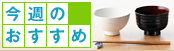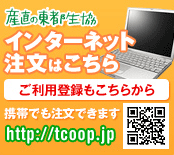- 高齢者福祉・子育て支援などに取り組んでいます。
- 保育ママ委員会を中心に、保育ママ制度の充実をすすめています。
- 東都生協くらしの助け合いの会「ほっとはんど」(組合員相互の自主的な家事援助活動)の活動を広げています。
「ほっとはんど」について詳しくはこちら - 視覚障害者と協同するボランティアの会「やまびこの会」の活動を行っています。
「やまびこの会」について詳しくはこちら
高齢者が安心して暮らしていける地域づくりを目指します
|
|
|
グループに分かれ、さまざまな事例を演習 |
各グループから発表 |
|
|
認知症を正しく理解することで適切な対応や予防につなげることを目的とした、東都生協組合員に向けた学習・教育企画です。
認知症サポーターとは、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人やそのご家族を支援する人のこと。
認知症サポーターになるには、各地域で実施している「認知症サポーター養成講座」を受講する必要があり、受講者にはサポーターの証としてオレンジリング(画像)が渡されます。
講座の前半は、冊子・ビデオを用いて説明。休憩時間には「ころばん体操」や「脳トレ」を行いました。
後半は、会場によってさまざまな内容についてグループワーク。事例ごとに取るべき対処方法について話し合い、発表しました。
最後に、認知症サポーター養成講座受講の証として参加者全員にオレンジリングが授与されました。
<参加者の年代>
30代…3人 40代…23人 50代…48人 60代…15人 70歳以上…10人
<参加者の声(抜粋)>
・家族が認知症の症状が出てきたので参加しました。対応や改善のため学びたかった。
・ご近所のお年寄りと接していてどの時点で認知症を疑い、家族と連絡したら良いか分かった。
・グループワークは他人の考えに触れられて良かった。
・同じグループに実際に介護に当たっている方たちがいて、お話が聞けて良かった。
・認知症は深いし判断するのは難しいけれど、あわてずゆっくり対応したいと思ったが、これで正しいのか不安。
・介護も育児も共通点があることが分かった。これから役立つかも…。
・地域でさまざまな支援があることが分かった。周りの人にも伝えていきたい。
・認知症は若年層にもなることを知って大変参考になった。
日程・会場 | 講師 | 人数 | 後半の内容 |
|---|---|---|---|
| 7月3日(火)午前あんさんぶる荻窪(杉並区) | 杉並区役所高齢者在宅支援課地域連携推進係・保健師 | 31人 | 1つの事例についてどんな声掛けや関わりができるか話し合い、発表 |
| 7月3日(火)午前多摩消費生活センター(立川市) | 南部西ふじみ包括支援センター・社会福祉士、看護士 | 16人 | グループごとに認知症患者のごみ出しへの対応方法を模擬体験 |
| 7月5日(木)午後東京芸術センター(足立区) | 地域包括センター千住本町・キャラバンメイト | 18人 | 設問について意見交換し答えを発表。認知症についての小テスト・答え合わせ |
| 7月5日(木)午後下北沢区民集会所(世田谷区) | 北沢あんしんすこやかセンター・職員、キャラバンメイト | 21人 | 学習内容を踏まえ、参加の動機や話したいこと・聞いてもらいたいことを話し合い |
| 7月12日(木)午後渋谷商工会館(渋谷区) | 地域包括センター・職員、キャラバンメイト | 26人 | グループで対応方法のシミュレーションを実施。対応が正しいか検証し講師が説明 |