6生協が食料・農業・農村基本計画策定に伴う院内集会を開催
農業を守るために、消費者・生産者の声を反映させましょう!

農水省に6生協による新基本計画への提言を提出
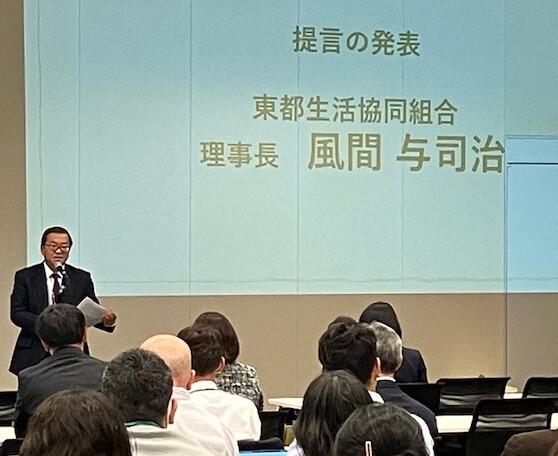
提言について説明する風間理事長
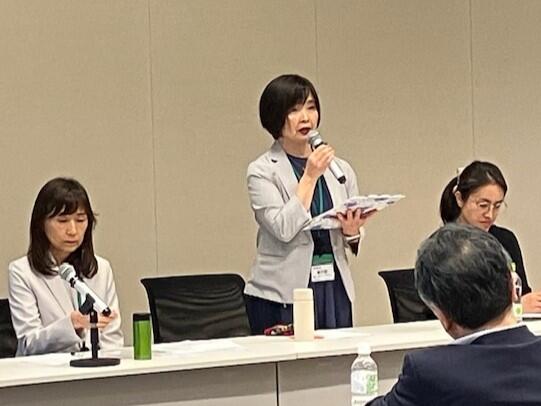
消費者の立場から橋本組合員常任理事が発言

紀ノ川農協副組合長理事 西野文敏氏
生産現場からの要求・要望を発言

院内集会の第1部をまとめる石渡副理事長
生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、生活協同組合連合会コープ自然派事業連合、生活協同組合連合会アイチョイス、グリーンコープ生活協同組合連合会、パルシステム生活協同組合連合会、東都生協の6生協は2025年3月27日午後、合同で衆議院第二議員会館で食料・農業・農村基本計画策定に伴う意見交換会(以下、院内集会)を開催しました。
2024年6月に施行された改正食料・農業・農村基本法に基づく新たな食料・農業・農村基本計画が、近く閣議決定される見込みです。近年、食料・農業を取り巻く状況は大きく変化しており、新基本計画が国内の農畜水産業を守り、日本の食料自給率を向上させる重要な転機となる可能性があります。
今回の集会に先立ち「農業を守るために、消費者・生産者の声を反映させましょう!」をテーマに掲げ、6生協が思いを共有し、10月の学習会で得た成果を基に取りまとめた「食料・農業・農村基本計画」策定に関する提言(PDF)を、農林水産大臣へ正式に提出しました。
院内集会では、6生協より消費者団体の立場から共同で策定した新しい基本計画に対する提言を発表するとともに、農林水産省や国会議員、参加者と意見交換。消費者、組合員、生産者団体の声を伝え、提言が食料・農業政策や新基本計画に反映されるように取り組みました。
食料・農業への社会的関心が高まる中、集会にはオンラインを含めて約300人が参加。6生協からは96人、国会会期中にもかかわらず国会議員17人、農林水産省9人が参加するなど、6生協合計320万世帯の思いを結集した提言の影響力が感じられる場となりました。
生産者の意見を積極的に取り上げ、国内農業の現状を伝えることで、政策形成での生産者視点の重要性を改めて認識させられる機会となりました。6生協は今後、提言に対する政策動向を継続的に注視しながら対応していきます。
「食料・農業・農村基本計画」策定に関する提言(PDF)はこちら
院内集会の概要
開会に当たり生活クラブ事業連合生活協同組合連合会会長 村上彰一氏は「国際情勢が緊迫する中で、日本が食料を調達できなくなることは目に見えている。『令和の米騒動』は供給不足が要因で、米不足は来年も続くと考える。担い手にとって再生産できることが最低限の課題であり、夢を持てる政策にすることが必要。日本の農業を元気にして、国の存立基盤である食料の自給、農業・農村の再生を実現するために、消費者・生産者と政府が協力し合っていきたい」と述べました。
続いて東都生協の風間理事長から、院内集会に先立って農林水産省に提出した提言を説明。食料自給率目標の明示と実現に向けた対策、国内農業を守るための適正な価格形成、環境保全型農業とみどりの食料システム戦略、消費者の立場に立った食料の安全確保の強化、農村政策の5つの柱から成る提言の概要を示しました。
消費者を代表してグリーンコープ生活協同組合ふくおか理事長 坂本寛子氏、東都生協・橋本組合員常任理事、パルシステム生産者・消費者協議会 副代表幹事渡部さと子氏、生活クラブ生活協同組合連合会・東京副理事長 豊崎千津美氏、生活協同組合コープ自然派しこく理事長 泉川香氏、生活協同組合連合会アイチョイス専務理事 見崎一石氏が登壇。
「食料を輸入に頼ることを当たり前とせず、国内で賄えるようにしてほしい」「生産者が持続できるように農山村地域の活性化を」「持続可能な食と農を農政の基本に」「国産品を安心して利用できるように、生産者をしっかり支える仕組みを」「こだわって作った商品を消費者が主体的に選べるように、原料原産地、遺伝子組換え、ゲノム編集食品など消費者目線の表示を」「農業は生産者だけの問題ではない。政府と生産者・消費者が一体となって行動すべき」「国民に情報を開示し、生産者・消費者の声を農政に反映させる仕組み作りを」「国民の命を守るためには、まず苦境にある国内生産者を支援し、安心して農業を続けられる環境整備を」「自給率向上と食料の安定供給に向け農林水産関連予算の大幅な増額を」「地域の農畜水産業の多様な担い手をしっかり支えられる直接支払い制度を」「優良種子の安定確保のために農家の自家採種を認めるべき」「有機農業推進と出口戦略としての学校給食での活用、食育の強化を」など、新基本計画への消費者の切実な願いを訴えました。
生産者からは、長野県・のらくら農場代表の萩原紀行氏、山形県・庄内みどり農業協同組合・遊佐町共同開発米部会事務局長の池田恒紀氏、和歌山県・紀ノ川農業協同組合副組合長理事の西野文敏氏が発言。
「資材高騰や異常気象の常態化で若手の廃業が相次いでいる。農産物が不足しない限り価格転嫁が進まないのが現状」「生産と消費が対立しない、生協などが実践する持続可能な仕組みを取り入れてほしい」「担い手不足は喫緊の課題。新たな担い手の育成に向けた目標設定と切れ目のない支援制度を」「中山間地域の小規模な農地にも支援制度を」「輸出促進よりも国内の消費者への安定供給に向け計画の再考を」など、生産現場の実情を踏まえた発言がありました。
提言を受けて、農林水産省の各担当者が回答。「食料自給率は新基本計画では『5年後45%』に設定し、国内生産の増大に向けて施策を講じていきたい」「自給率目標と併せて、食料安全保障を確保するために農地面積、49歳以下の担い手人口、単収などで数値目標を設定する」「新規就農は規模の大小を問わず支援している」「生産者、食品事業者が持続できる適正なコストを話し合い、消費者の商品選択に資する活動を進める事業者を支援する仕組みづくりを行う」「有機農業に安心して取り組めるような支援や学校給食への活用、販路の確保に向けて関係省庁、地域間、事業者間での連携を進める」など新基本計画策定に向けた考えを説明しました。
最後に生活協同組合連合会コープ自然派事業連合理事長 岸健二氏は「学習会や協議など3年にわたる取り組みを踏まえて取りまとめた」と提言に至る経過を説明。「米の高騰など物価上昇が進み、エンゲル係数は半世紀ぶりの水準にある。近年のインフレは供給不足が原因。生産基盤の縮小が加速する中で『5年後の自給率45%』は並大抵の努力では達成できない。食料を支える農業の再生に向けて、これからが議論の始まりと受け止めている。引き続き消費者・組合員の声に応えて取り組んでいきたい」と締めくくりました。
