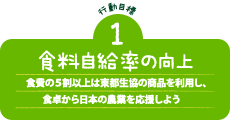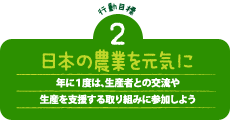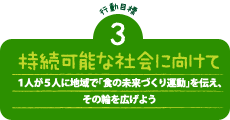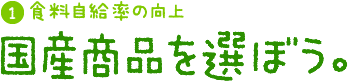
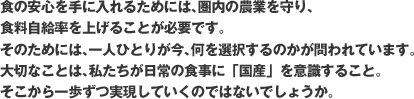
食卓の変化と食料自給率
戦後、食生活が洋風化し、また食の外部化(外食や加工食品への依存)が急速に進みました。日本の食料自給率低下の大きな要因として、この食卓の急激な変化があげられます。
1965年度(昭和40年度)に73%だった日本の食料自給率(カロリーベース)は今や41%(2008年度概算)です。その間、私たちの食生活は、摂取カロリーが増加しましたが、その中身は、自給率の高い米の消費が減り、自給率の低い肉や乳製品、油脂、小麦などの消費を増やしてしまいました。その結果、食料全体の自給率を低下させてしまったのです。
1965年度(昭和40年度)に73%だった日本の食料自給率(カロリーベース)は今や41%(2008年度概算)です。その間、私たちの食生活は、摂取カロリーが増加しましたが、その中身は、自給率の高い米の消費が減り、自給率の低い肉や乳製品、油脂、小麦などの消費を増やしてしまいました。その結果、食料全体の自給率を低下させてしまったのです。
国産応援商品を選んで食卓の自給率アップ!
昔ながらのごはん食を中心とした食事は、それだけでも自然と食料自給率が高くなるのでおすすめですが、味噌や豆腐などを国産原料の商品にすると、さらに自給率を上げることができます。
おなじように、パン食や洋風麺などを中心としたメニューでも、食材の選び方ひとつで簡単に食卓の自給率をアップさせることができます。ポイントは自給率の低い小麦、肉や乳製品、卵などに東都生協(コープ)の国産応援商品を取り入れること。小麦の自給率は14%と大変低いため、パスタの原料に国産小麦粉を使用している商品を選ぶと、自給率が大幅にアップします。
おなじように、パン食や洋風麺などを中心としたメニューでも、食材の選び方ひとつで簡単に食卓の自給率をアップさせることができます。ポイントは自給率の低い小麦、肉や乳製品、卵などに東都生協(コープ)の国産応援商品を取り入れること。小麦の自給率は14%と大変低いため、パスタの原料に国産小麦粉を使用している商品を選ぶと、自給率が大幅にアップします。
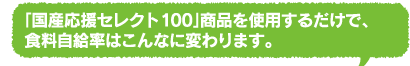

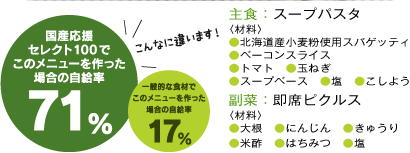
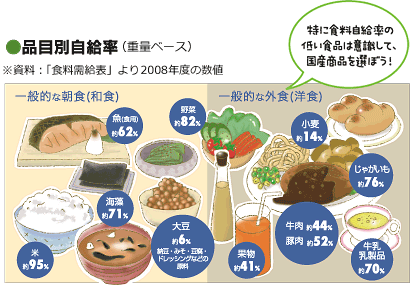
《食料自給率の向上のために東都生協が行っていること》