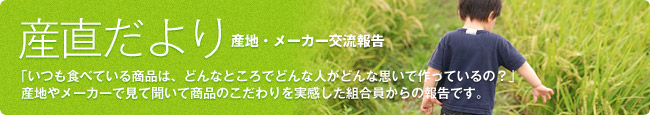2009
07
JAみどりの 田んぼの生きもの調査③
7月の産地交流訪問
一定の区画内の羽化殻を採取します |
羽化したばかりのトンボ |
水路での調査 |
ちょっと見えにくいかもしれませんが、水路にはたくさんのメダカが群れていました |
ドジョウもいました |
ペットボトルに入れた、ドジョウやメダカ |
ペーハーの簡易検査 |
生産者の佐々木さんと参加した佐藤組合員理事 |
佐々木さんの田んぼにはトンボがたくさん
まずは、前回できなかったトンボの羽化殻調査を、農薬や化学肥料を使用していない佐々木さんの田んぼで行いました。羽化したばかりの白いトンボやもうすぐ飛び立ちそうなトンボなど、稲にはたくさんの羽化殻とトンボが見られました。
メダカやドジョウがいっぱい
今回は、プロジェクトの「生きもの調査」の田んぼとは異なり、農薬や化学肥料を使用しないもしくは半分に抑えた5~6カ所の田んぼを調査しました。プロジェクトの調査に比べると簡易ではありますが、生産者自身が自らの田んぼの生きものに目を向け、それを稲の栽培に役立てるのだそうです。
水路にはたくさんのメダカ、そしてその水路から田んぼに登ろうとしている小さなドジョウなどもいました。
おいしいお米づくりには多角的な視点が必要
ペーハー(pH)※の簡易検査では、1つの田んぼでも場所によってペーハーの値が異なることがわかりました。例えば藻が繁茂するところでは、水中の二酸化炭素を消費するためペーハーが高く(アルカリ性)なるそうです。
稲の状態や天候だけでなく、田んぼの生きものや水質などより多くの情報から状況を判断し、おいしいお米をたくさん作る努力をしているのですね。
※ペーハー…水素イオン濃度指数のことで、0~14の数値で酸性度やアルカリ性度を表します。
ただお米を食べるのではなく、そのお米を育んだ田んぼにも思いをはせてほしい。
そんな願いを込めてこれからも田んぼのようすを伝えていきます。

2009
07
JAみどりの 田んぼの生きもの調査②
6月の産地交流訪問
田んぼは自然にあふれています |
ヤゴを探す参加者たち |
調査範囲の外に羽化殻を発見 |
田んぼの中の生きもの調査では一定面積の中の生きものをできる限り数えます |
オタマジャクシはもうすぐカエルに |
水路では両側から追って網で捕まえます |
ザリガニがたくさんとれました |
ドジョウやオタマジャクシ、ゲンゴロウの仲間なども見られました |
最後に、調査のまとめをして終了です |
宮城県のJAみどりの(田尻)で「田んぼの生きもの調査」2回目(6月29日)は、前回の調査内容に加え、トンボの羽化殻調査も行いました。
前の調査から3週間が経ち、田んぼのようすもずいぶんと変わっていました。
今年はトンボの羽化が遅い
「田んぼはどのくらいのヤゴを育んでいるのか」を調べるため、トンボの羽化殻調査を行いました。田んぼの中に区画を決め、トンボの羽化の期間中、羽化殻を採取していくのです。しかし、今年はトンボの羽化が1週間程度遅れており、調査範囲の中には見つけることができませんでした。
その後、前回同様にカエル調査、水路・田んぼ・田んぼの土の中にいる生きもの調査、そしてあぜに生える植物調査を手分けして行いました。稲が育っているのは当然ですが、田んぼの中にいる生きものにも変化が見られました。前回見られたタマカイエビはぐんと減り、クモがたくさん見られました。稲についている虫が多くなったようです。
参加者の感想
「今回の調査は、トンボの羽化殻調査も加わったものとなりました。赤トンボが田んぼで育っているということも今回の調査ではじめて知りました。トンボの脱皮が時期的に例年よりも遅れているもようで、羽化殻を数えるに至りませんでしたが、ちょうど脱皮したばかりの赤トンボと羽化殻を見られて感激です! このように赤トンボの時期が遅れている年は冷害の年が多いのだそうで、生きものからも農業が見えるのだということです。」
「ふたたび訪れた田んぼは、もう懐かしい我が家の田んぼのようでした。
梅雨の晴れ間の暑い一日、早朝のヤゴの抜け殻調査では、ひとつだけの発見でしたが、20センチ程に伸びた稲の上を何匹かのトンボがス~っと飛んでいました。
『ヤゴの羽化が一週間ほど遅れている・・・6月の低温の影響だと思いますよ。』という、生産者の方の言葉が印象的でした。
ほかにも田んぼの水の温度のこと、飛んでいる鳥の種類からのいろいろな気候の変化の読み方など、生産者の方は自然のすべてをその経験のなかに活かしくらしていることを知らされました。
劇的変化のない生きものの数(当たり前ですが)。しかし、ゆっくり、ゆっくり田んぼの土も熟成していき、幾世代にも引き継がれるものがつくられるんだとあらためて実感!!
私たちもあわてず、騒がず、じいっ~と目をこらしユスリカの幼虫を数えなければ…」

2009
07
JAみどりの 田んぼの生きもの調査①
6月の産地交流訪問
 宮城県大崎市田尻の風景
宮城県大崎市田尻の風景
1日目 学習会のようす |
朝 田尻支店に集合 |
現地に着いての説明 |
水路での生きもの調査 |
畔にはえる植物調査 |
採取したすべての植物の名前を調べます |
田んぼの中の生きもの調査 |
タマカイエビがたくさんいました。写真では点にしか見えませんが、すべてタマカイエビです。 |
ヤゴもいました |
最後に、調査のまとめをして終了です |
6月8日~9日、宮城県のJAみどりの(田尻)で「田んぼの生きもの調査」が行われました。
ひとめぼれやササニシキでおなじみのJAみどりのでは、多様な生きものを育む田んぼの価値をきちんと知るために、生きもの調査を数年前から行っています。
そんな田んぼで作られたお米の価値を、生き物を通して伝えられないかと、産地、お米の流通業者、生協などがプロジェクトをつくり、生きもの調査を行うことになりました。今回は、その1回目です。
1日目 田んぼの生きものについて学びました
1日目は、JAみどりの田尻支店の会議室で、プロジェクトメンバーの紹介や生きもの調査について学習を行いました。
2日目 2カ所の田んぼで動植物の調査をおこないました
2日目は、いよいよ田んぼの生きもの調査本番です。田尻支店に集合したあと、参加者は田んぼに向かいました。
今回の調査は5項目。あぜを歩いてのカエル調査、水路の生きもの調査、田んぼの中の生きもの調査、田んぼの土の中にいる生きもの調査、そしてあぜに生える植物調査です。それらを手分けして行いました。
田んぼには実にさまざまな生きものたちが息づいています。カエル、オタマジャクシ、ヤゴ、カイエビ、イトミミズ…、用水路にはザリガニ、フナ、ドジョウ、メダカなど。
すべての生きものは単独ではなく、ほかの生きものと複雑に関係しあいながら生きていることをあらめて実感しました。これからもたくさんの生きものとかかわってできたお米の価値を伝えていきます。
参加者の感想
「田んぼの中の生き物とお米づくりとの関係に興味があり参加しました。人手の問題で機械化のために圃場整備がすすんでいると感じましたが、昔ながらの田んぼと整備をした田んぼでは生き物の状態に違いが出ること、自然の中で微生物からの生き物連鎖がある田んぼは生き物の宝庫でもあり、稲の生育にも大切な役割を持つのではないかと感じました。
限られた時間の中での調査でしたが、ひばりが鳴き、すがすがしい空気の中、青々とした田んぼが連なる風景に癒されました。今後の調査が楽しみです。」
「畦を歩くと、きれいな緑色のあまがえるがピョン! ピョン! と田んぼに飛び込みます。畦には、黄色や白、紫の小さな小さな花をつけた草花がたくさんありました。
生きもの調査のはじまりです!
消費者と生産者が、一緒にひとつの目標をもちコツコツと積み上げていくという現代のスピードに逆行するような歩み。
でもそれこそ、食の未来をゆたかなものにしていく丁寧なすすみ方だと思います。
はだしで田んぼに入ると、すっぽりと柔らかにつつまれてまるで稲になったよう。
その田んぼをふきぬける風は、さわやかで気持ちよくみんなに感じてほしいと思うほどの新鮮な感覚でした。
これから、どんな生きものとどれくらい出会えるのか?
生産者の方は、なにを考えこの田んぼに立つのか?
そして、私たち消費者の使命は・・・?
これから続いていく調査にワクワクのわたしです。」

2009
07
おいしさに感激!!
7月の産地交流訪問
畑で試食 |
新鮮なすいかだ! |
採れたてのとうもろこし、すいたを試食した参加者の中には「今まで食べた中で、一番おいしかった」という人も。昼食のカレーライス、サラダ、かぼちゃの煮付け、枝豆などごちそうになり、参加者一同大感激でした。
2009
07
農家の忙しさを実感
機関誌『東都生協だより』より
自然がたくさん残っています |
わあ、かわいい!! |
思い出深い訪問になりました |
2009
07
84人でいちご狩りに!!
機関誌『東都生協だより』より
どれがおいしそうかな? |
うれしいおみやげ |
2009
07
楽しいお祭り!
7月の産地・メーカー交流活動
生産者も気合いが入っています |
生産者・メーカーの人と話ができるのも、お祭の大きな楽しみです |
産地・メーカーの出展はもちろん、すいか割り、ゼリーのつかみ取りなどののイベントもあり、会場は大盛り上がり。
楽しい1日となりました。
2009
07
汗をかきながら、笑顔がいっぱい
機関誌『東都生協だより』より
生産者のお話も熱がこもります |
おいしいいちご、とれたかな? |
2009
07
こだわりを知った おいしい交流!
機関誌『東都生協だより』より
ギョーザのおいしい焼き方を習いました |
みんなで試食「いただきます!」 |
2009
07
自分で作った味は?
機関誌『東都生協だより』より
ゆっくり煮詰めていきます |
おいしいソースができました |